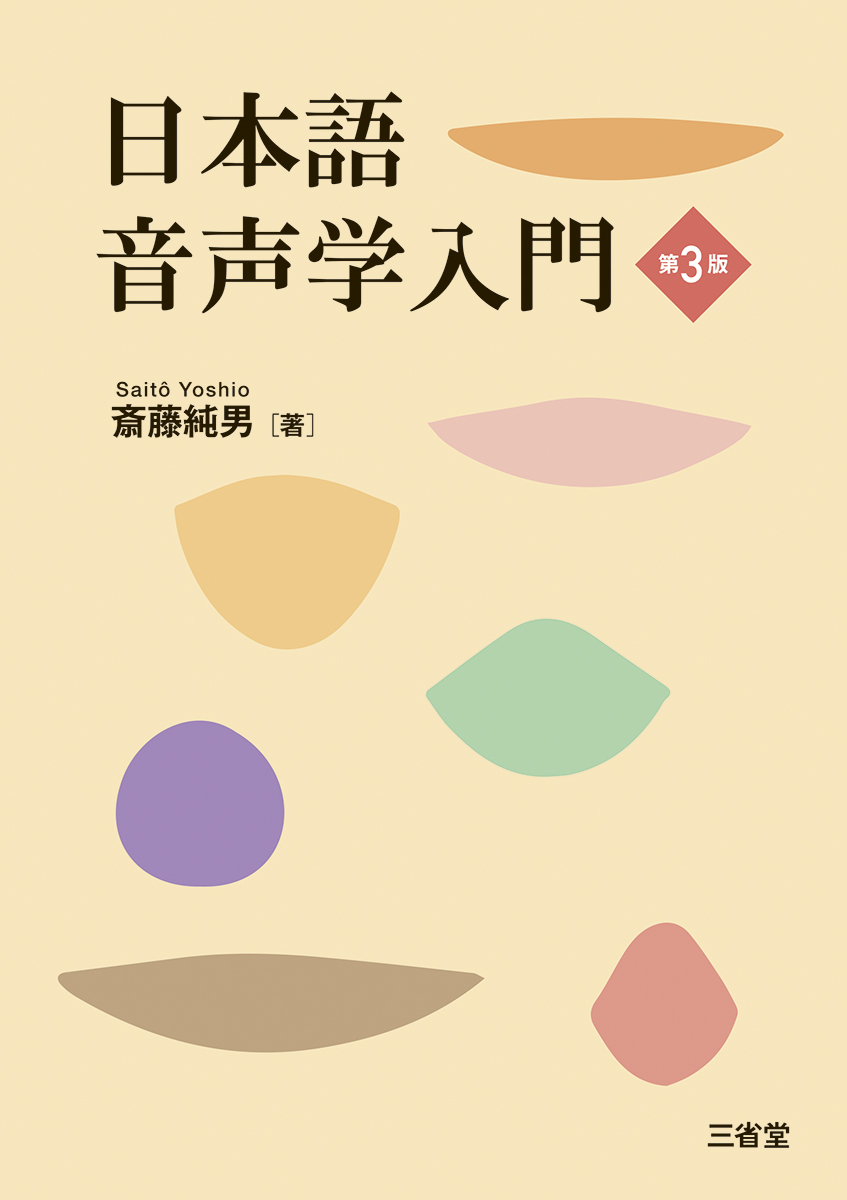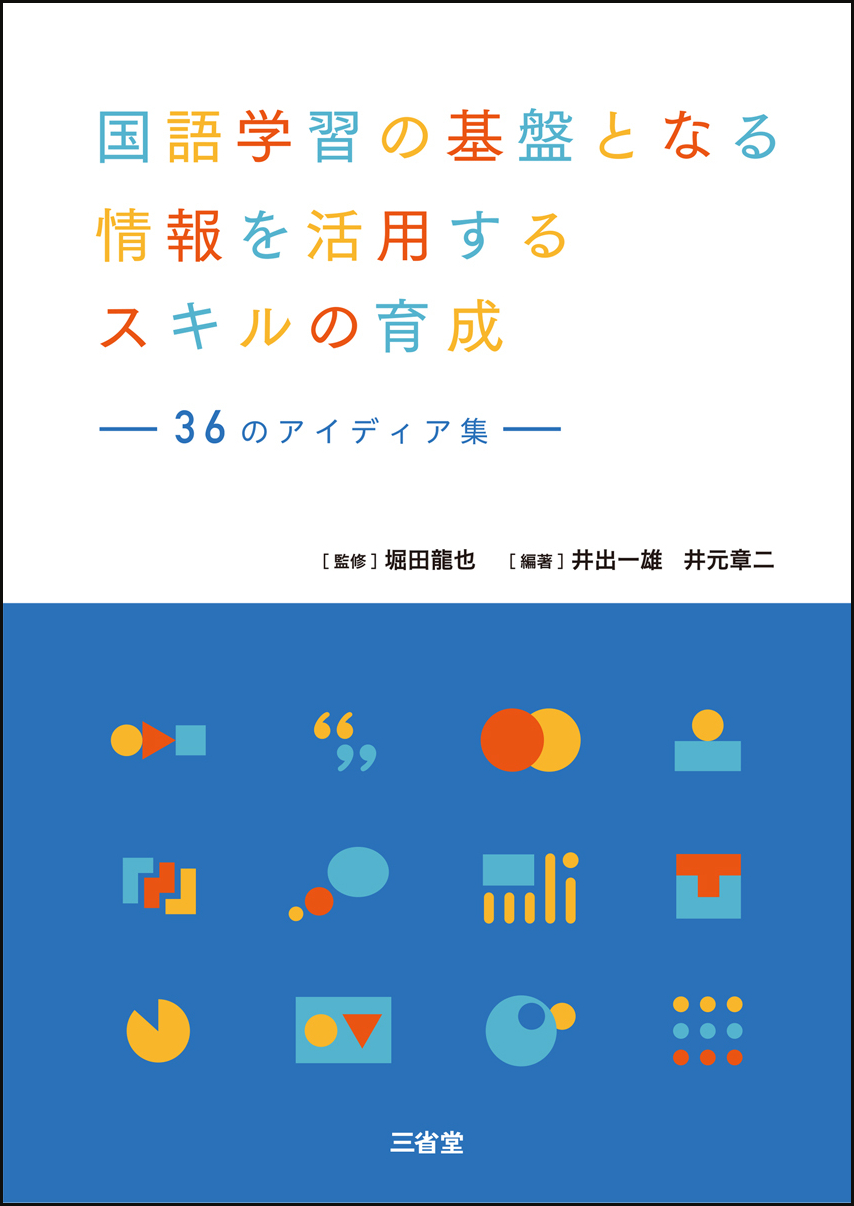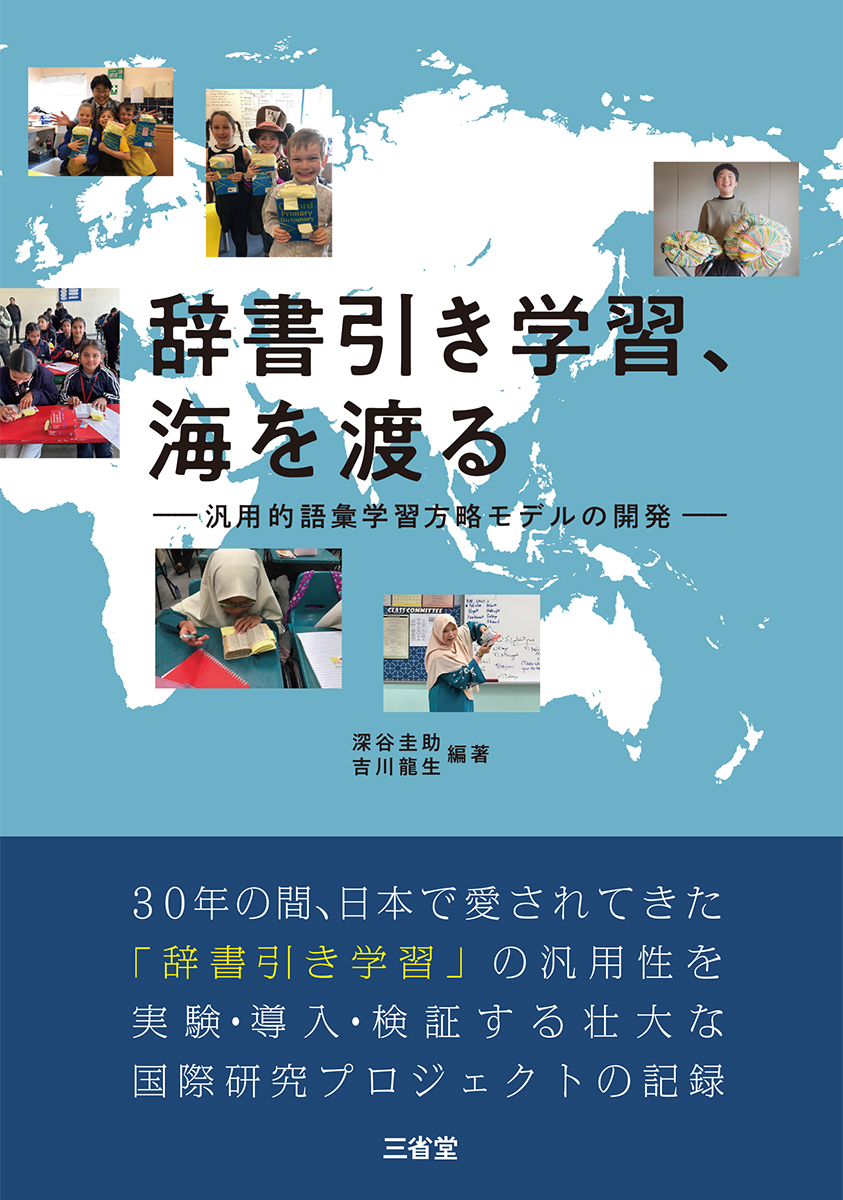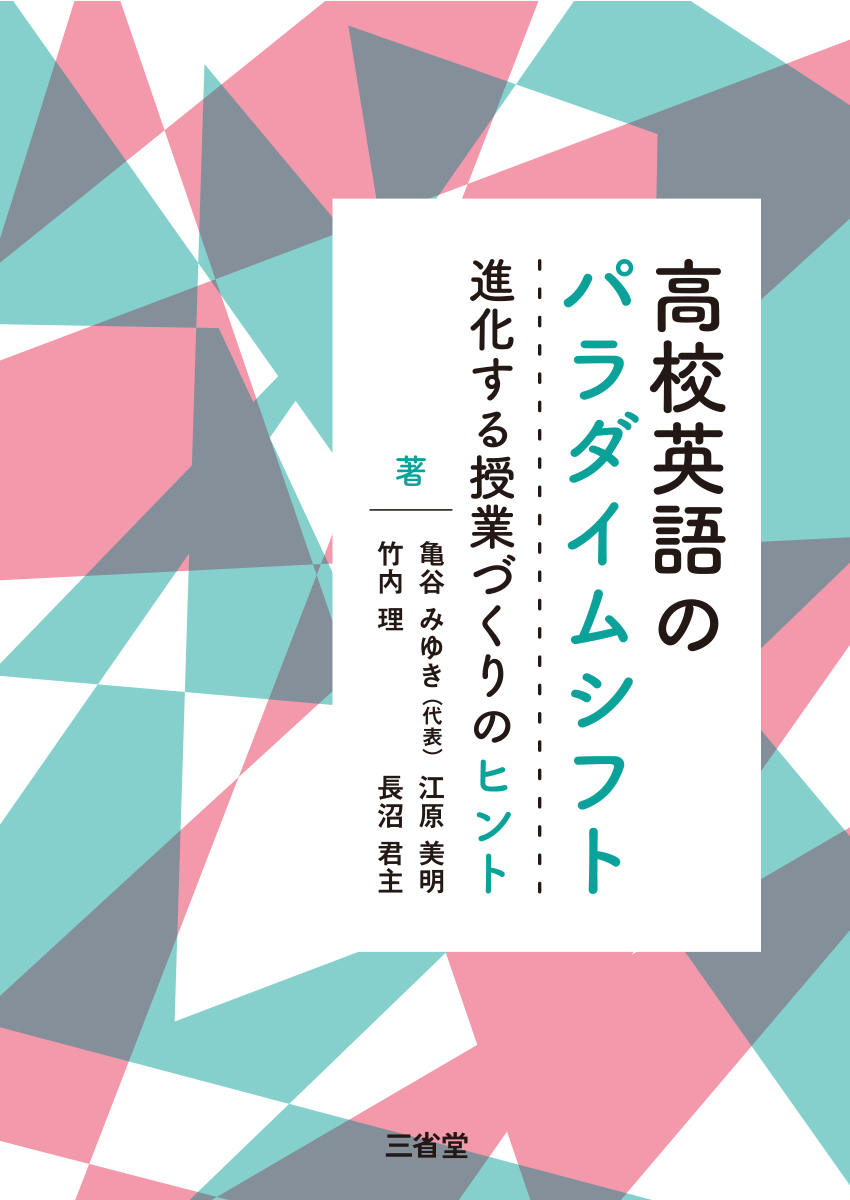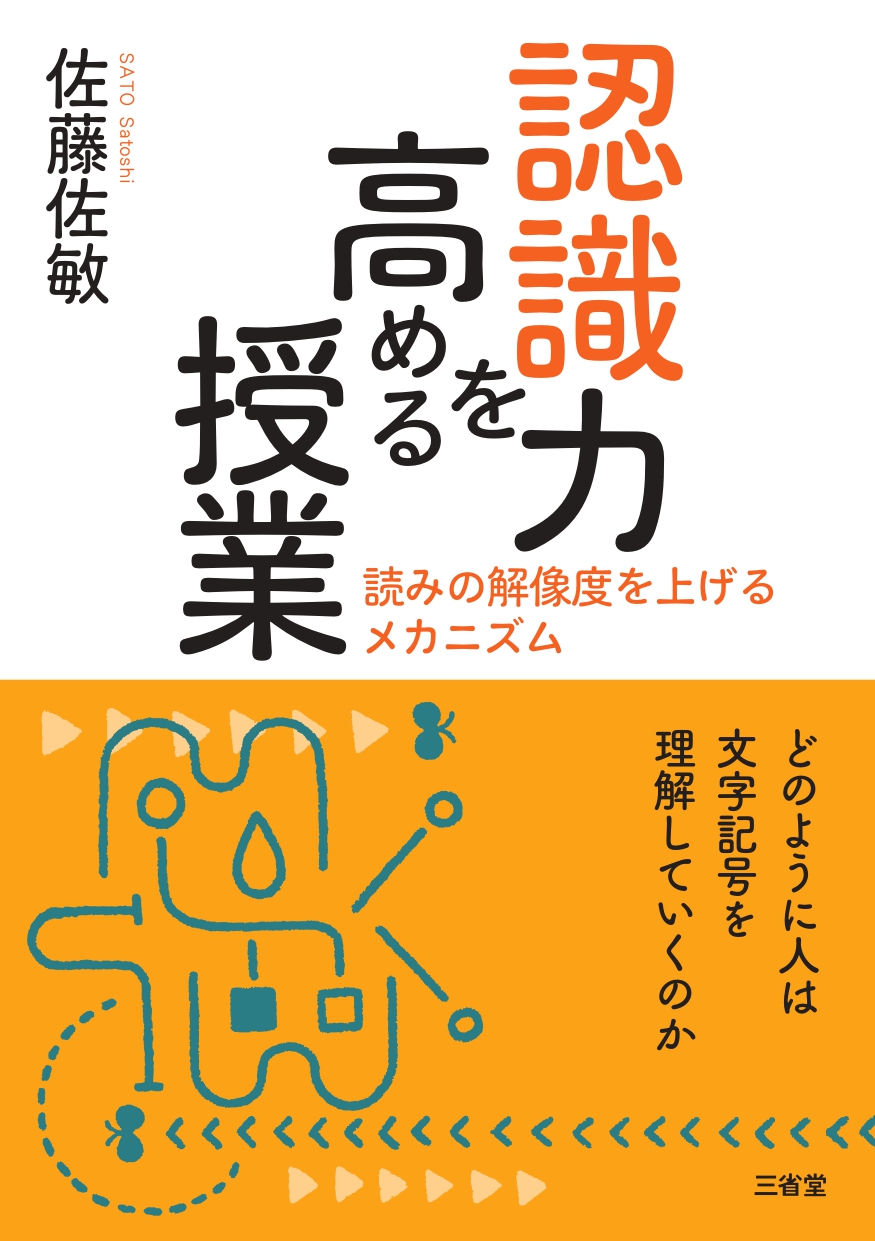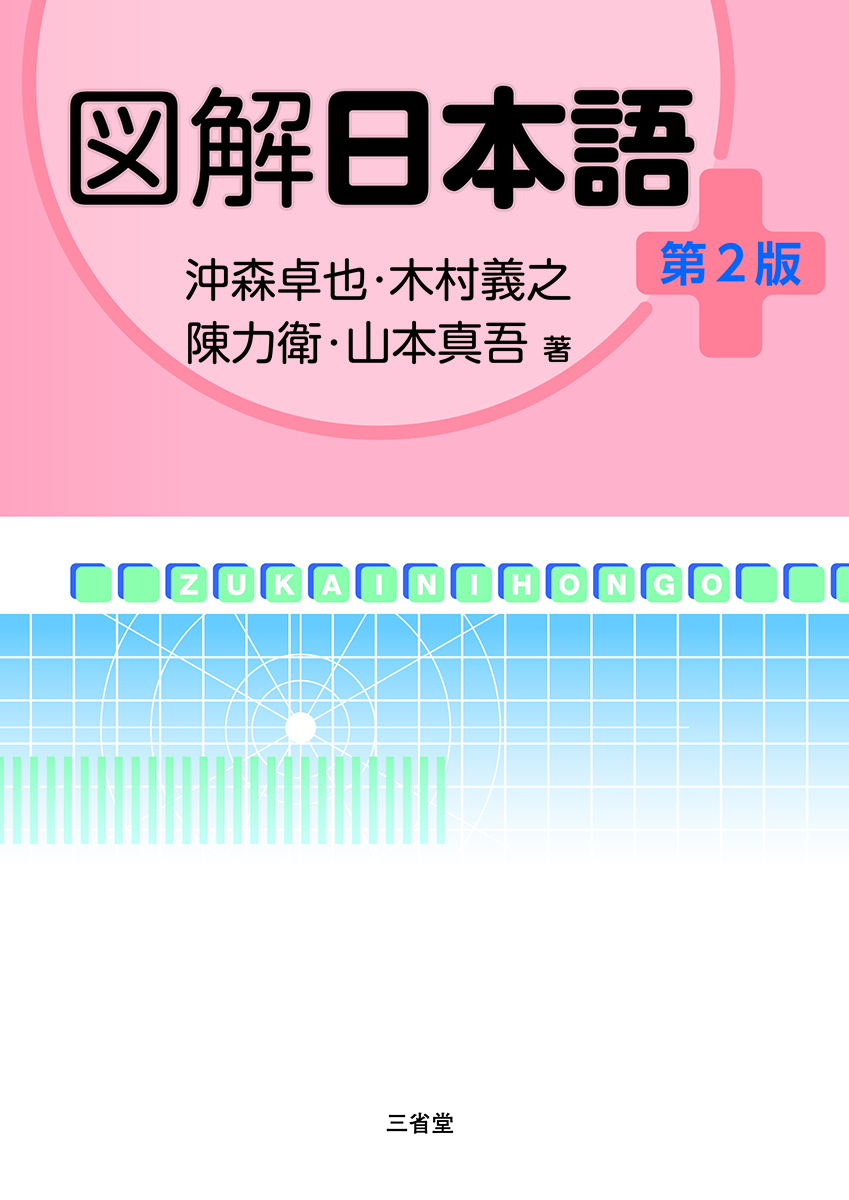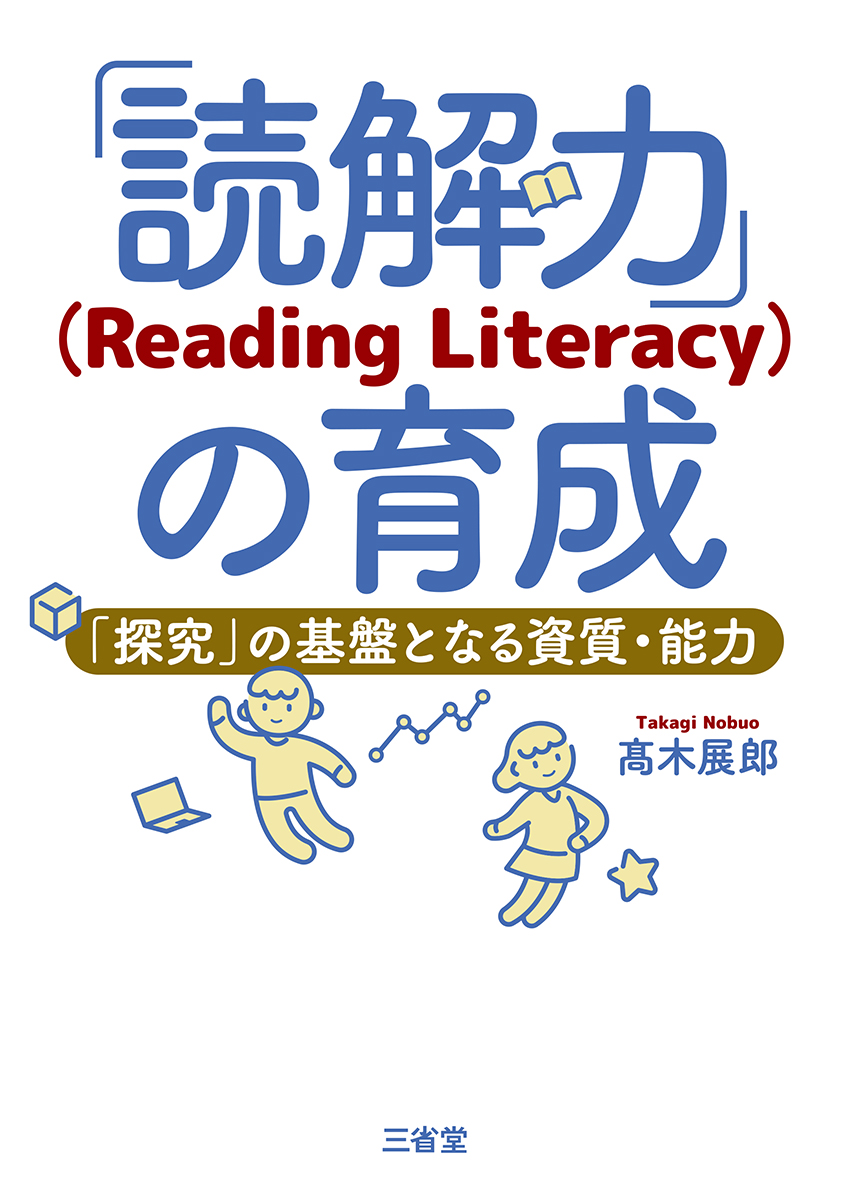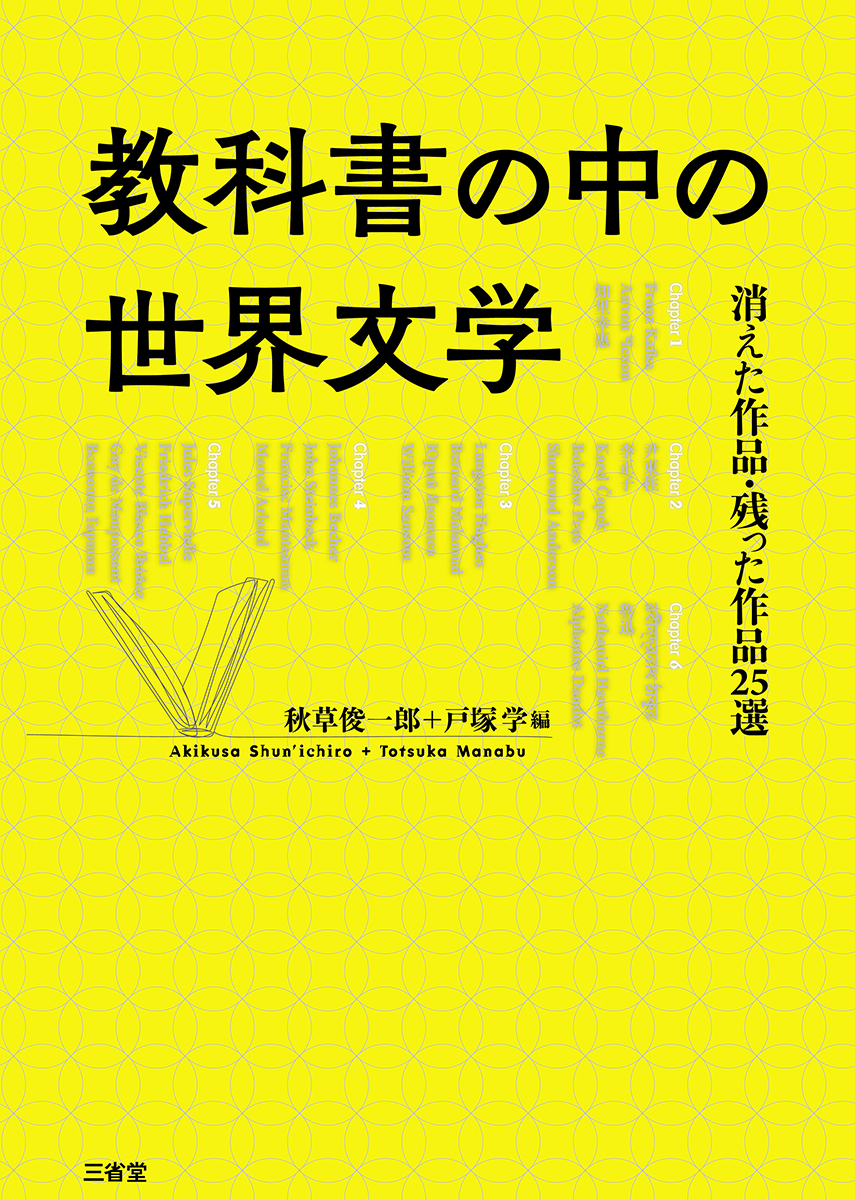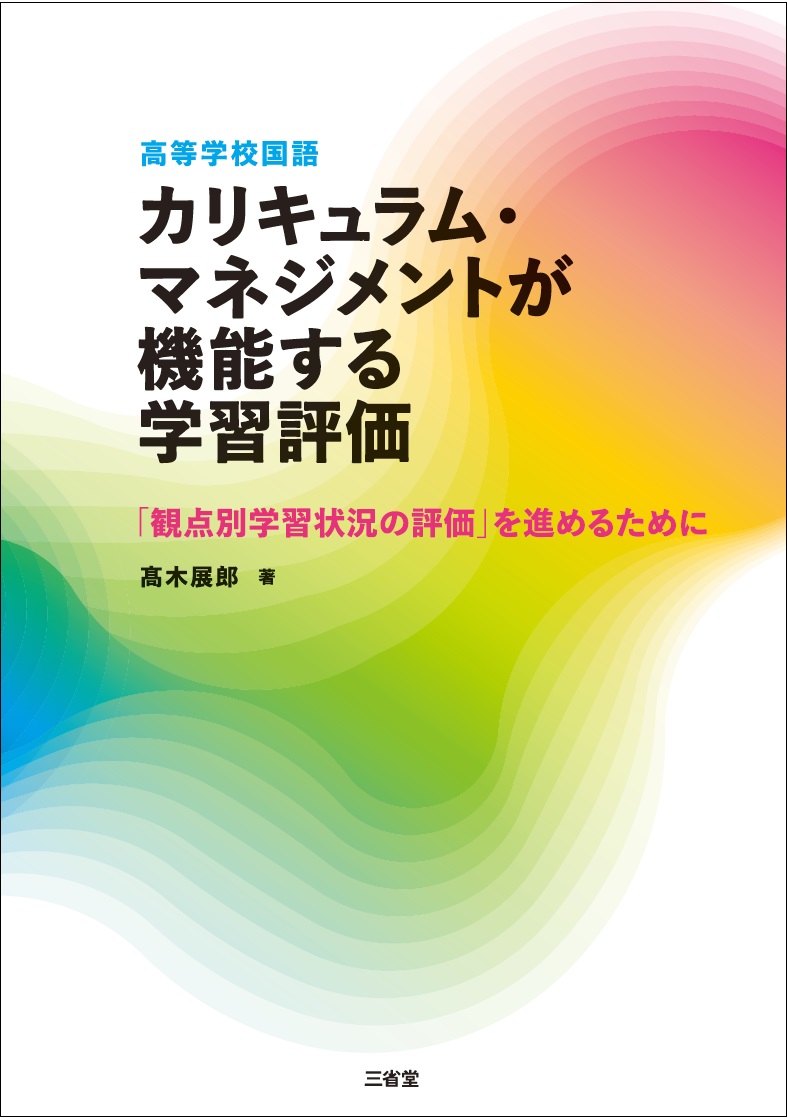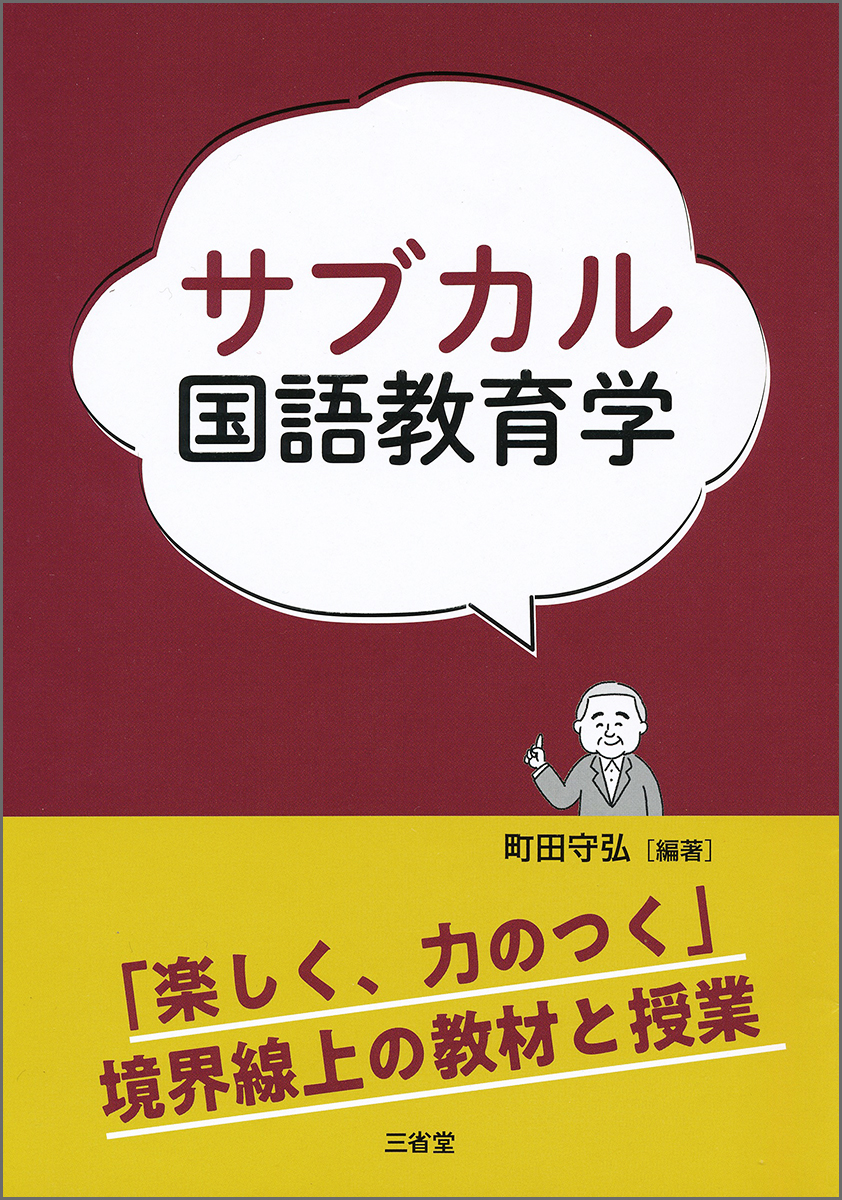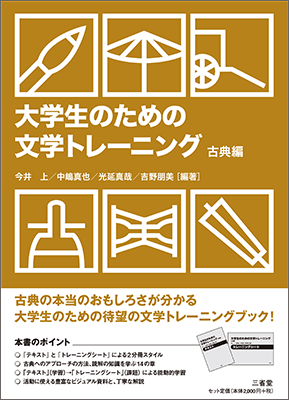大学生のための 文学トレーニング 古典編
- 大学生
- 著者名
- 今井 上・中嶋 真也・光延 真哉・吉野 朋美 編著
- 判型
- A5
- ページ数
- 160頁
- ISBN
- 978-4-385-36552-7
「テキスト」と「トレーニングシート」の2分冊スタイルで、古典へのアプローチの方法、読解の知識を学ぶ。『伊勢物語』『古今和歌集』『平家物語』、『源氏物語』『新古今和歌集』『雨月物語』、『万葉集』『百人一首』『東海道四谷怪談』等、14章による古典作品と丁寧な解説。活動に使える豊富なビジュアル資料付き。
*「文学トレーニング 古典編 教師用解説集」(非売品)を、ご採用者でご希望の先生にお送りいたします。下記の申込みフォームに入力の上、ご送信ください。
*なお、採用ご検討の際には、下記「〈大学向けテキスト〉一覧/見本請求」のページにて採用見本のご請求を承っておりますので、是非ご利用ください。
目次
Section 1 文学作品のさまざまな貌
008 1 時代と文化を越えて 『伊勢物語』
015 2 花と紅葉と和歌 『古今和歌集』
025 3 異本の世界をのぞく 『狭衣物語』
032 4 「先帝身投」の叙述と諸本 『平家物語』
043 5 芭蕉の推敲の跡をたどる 『おくのほそ道』
Section 2 オリジナルとその変容
052 6 三輪山伝説をめぐって 『日本書紀』
063 7 誤読か? 創造か? 『源氏物語』 葵巻
070 8 「宇治の橋姫」をめぐって 『新古今和歌集』 他
080 9 「宇治の橋姫」の変容 謡曲『江口』 他
095 10 よみがえる魔王 『雨月物語』
Section 3 文体・メディア・あそび
108 11 漢字であそび、漢字とたたかう 『万葉集』
117 12 絵は何を語るか 『源氏物語』 柏木巻
123 13 百首から広がる豊かな世界 『百人一首』
136 14 古典怪談の決定版 『東海道四谷怪談』
146 主要参考文献一覧
156 旧国名・都道府県名対照図
はじめに
一 本書の成り立ち
この本は、日本の古典文学を学ぶ大学生を対象とした、新しいタイプの教材集です。先に刊行された『大学生のための文学トレーニング 近代編』の姉妹編にあたります。その本の基本姿勢「学生が参加できる授業作りを」というものは、この本にも共通しています。ただ、古典は、近代と比べ、知識・個々のスキルを元にした読解がより必要となる側面があります。この本はその点を意識した内容となっています。古典を読む上で、どうしても知っておきたい知識や、感覚を、要領よく習得しうるよう、工夫しています。
また、一言で古典と言っても、時代別に上代(主に奈良時代)、中古(平安時代)、中世(鎌倉~室町時代)、近世(江戸時代)という四つの区分で捉えられています。全時代を網羅すべく、各時代を専攻とする四名が集まり、自分たちの日々の指導経験を生かせるよう、教材を持ち寄り、議論し、結実させたのがこの本です。
古典を学ぶというと、品詞分解や単語の暗記に終始するイメージがあるかもしれません。確かにそのような作業が全く無意味なわけではありません。しかし、言葉が単なる記号の羅列のように見えては、作品を読めたことにはなりません。長い年数をかけ、育まれた豊饒な古典の世界が存在します。この本が、それを満喫する一助となってほしいという思いは執筆者全員の願いであります。
二 古典文学を学ぶ礎
ここで、大学で古典文学を学ぶ上での基本スタンスに触れておきましょう。次の文章を読んでください。
春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく山ぎは、すこしあかりてむらさきだちたる雲のほそくたなびきたる。
夏はよる。月の比はさらなり。やみも猶、ほたるとびちがひたる。雨など降るさへおかし。
秋は夕暮。夕日花やかにさして、山ぎはいと近くなりたるに、からすのねどころへ行とて、みつ、よつ、ふたつなど、とびゆくさへあはれなり。まして雁などの つらねたるが、いとちいさく見ゆる、いとおかし。日いりはてゝ、風の音、虫の音など。
冬はつとめて。雪のふりたるはいふべきにもあらず。霜などのいとしろく、又さらでもいとさむきに、火などいそぎをこして、すみもてわたるも、いとつきづきし。ひるになりて、ぬるくゆるびもて行ば、すびつ・火おけの火も、しろきはいがちになりぬるはわろし。
「春はあけぼの」と始まり、一読して有名な『枕草子』冒頭と判断できたでしょうが、みなさんが知っている『枕草子』とは、どこか違いませんか? 例えば、夏に関しては「蛍の多く飛び違ひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし。雨など降るもをかし」と記憶している人も少なくないのではないでしょうか?その「蛍の多く~」も『枕草子』ならば、「ほたるとびちがひたる」も『枕草子』なのです。仮名遣いも異なります。なぜこのような状況が生じたのでしょうか? 古典文学は、江戸時代に出版が普及するまで、書写され受け継がれ行くものでした。単なる誤写もあったかもしれませんが、写し手たちの理解を反映させたり、わかりやすくしようとする思いで、本文は変わり行く可能性を秘めるものでした。このような存在を知ること、その作品を読むために、どの本文を選ぶか、そして本来のあるべきテキストを作成していくこと、これらが実は古典文学を学ぶ上での究極的な基礎作業なのです。
ここで引用した『枕草子』は「能因本」と呼ばれます。現在ポピュラーな系統は「三巻本」と呼ばれます。その他に編纂方針自体も異なる本も『枕草子』にはあります。有名な作品ゆえ、抱え込む問題とも言えます。江戸時代に普及した『枕草子』は「能因本」の方でした。唯一無二なテキストが存在するとは限らないのが古典作品であるということ。我々解説執筆者が伝えたい大切な考えの一つです。そしてそれは大学で古典文学を学ぶ礎に他ならないのです。
三 本書の構成
この本は、以下の三部構成になっています。
セクション1 文学作品のさまざまな貌
セクション2 オリジナルとその変容
セクション3 文体・メディア・あそび
これらは、相互に独立していますので、どこから読み始めてもかまいません。今述べた礎を重視して、段階を踏んで学習しようという場合は、セクション1から読み進めてください。そして、また各セクション内の配列は、作品の成立順を基本としています。いろいろな時代の作品を、さまざまなアプローチから学べるようにしています。
セクション1「文学作品のさまざまな貌」では、多くの古典作品が、一つの作品のようで、実はさまざまな貌を見せることを実感してもらう構成にしました。有名な章段の背景や享受の様相を学ぶ『伊勢物語』、読解を通して作品の構成などが見えてくる『古今和歌集』、表現の揺れ動きを実体験する『狭衣物語』、諸本による細かい描写の異なりを味わう『平家物語』、推敲と虚構とが織り交ぜられた『おくのほそ道』。これらのさまざまな貌を学びます。
セクション2「オリジナルとその変容」では、一つのテーマが、同時代の別の作品や、時代を越えた作品でどのように捉えられているのかを学びます。蛇と神話のありようを辿る『日本書紀』、能や後代の絵画との関係をあぶり出す『源氏物語』、『古今和歌集』『源氏物語』と受け継がれていく「宇治の橋姫」に関わる言説の行方を追跡する『新古今和歌集』・謡曲『江口』、西行の諸伝を江戸時代の上田秋成がどのように作品に取り込んでいるかを把握する『雨月物語』。古典文学が、前代の作品の享受と深く関わり生まれることもつかんでください。
セクション3「文体・メディア・あそび」は、多様なアプローチから古典作品を楽しもうというねらいのもと構成しました。漢字で日本語を書く時代を探求する『万葉集』、絵巻と物語の距離を歩む『源氏物語』、カルタとして親しまれてゆく『百人一首』、歌舞伎、絵画と複合的に立ち上がる『東海道四谷怪談』。人々の心を楽しませる娯楽ともなっていた古典文学を味わいましょう。
どこから学んでもかまいません。ゆたけき古典の世界の扉を、自らの手で開いてほしいと願っています。
本書の使い方
本書は「テキスト」と、その内容に対応した「トレーニングシート」の二冊からなり、作品の読解や研究方法を、具体的な作業を通じて習得できるように工夫されています。一回一作一テーマで全十四章の構成は、大学での講義や演習用に適しておりますが、個人学習用や、鑑賞の手引きとしても幅広く楽しめるよう配慮しています。
「テキスト」と「トレーニングシート」は連動するようになっています。基本的に次のようにお使いください。
(1) テキスト「本文」を読む。
(2) トレーニングシート「おもて」を解く。
(3) テキスト「解説」を読む。
(4) トレーニングシート「うら」を解く。
《テキスト》
・「テキスト」は「本文」「解説」と「参考資料」からなります。
・「本文」は上段に古典作品の本文を掲出し、原則下段にその通釈を載せています。
・「本文」は、まずは上段の本文を読んで、トレーニングシート「おもて」を解いてください。
・「解説」は「本文」を読解、分析する際のアプローチを紹介したものです。
・「解説」の中にある(鉛筆)マークは、対応する設問や作業項目がトレーニングシートにあることを示しています。必ずしも「解説」の読解を中断してトレーニングシートに取り組む必要はありませんが、そこで取り組んだ方が、より理解が深まるでしょう。
・「セクション○-○参照」として他の章との関連を示した箇所についても、適宜予習や復習に役立ててください。
・「解説」のあとにはさまざまな「参考資料」を収録しました。読解のためのいろいろな古典作品や、諸資料を掲載し、時代状況や古典世界をイメージしやすくしました。多くはトレーニングシートと連動しています。大学の演習では、自分で選んだ対象作について調べ、発表する機会も増えますが、その際準備する資料(レジュメ)作りの参考としても活用してください。
・トレーニングシートは「テキスト」の各章に対応した両面シートからなります。一回につき複数の設問・作業項目を用意してあります。
・トレーニングシート「おもて」には「解説」を読む前に、まず解いてほしい設問が並んでいます。
・トレーニングシート「うら」には「解説」を読んだ後に、もしくは「解説」を読みながら解いてほしい設問が並んでいます。
・本書を授業の教科書として使う場合は、先生の指示にしたがって各設問に取り組んでください。
・本書を教科書として採用してくださる先生方には解説集を提供する予定です。
編著者紹介
今井上(いまい たかし)
東洋大学文学部准教授
担当:Section1扉、1章、3章、7章、12章
中嶋真也(なかじま しんや)
駒澤大学文学部准教授
担当:はじめに、2章、6章、11章
光延真哉(みつのぶ しんや)
東京女子大学現代教養学部准教授
担当:Section3扉、5章、10章、14章
吉野朋美(よしの ともみ)
中央大学文学部准教授
担当:Section2扉、4章、8章、9章、13章