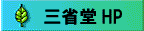品田雄吉(しなだ・ゆうきち)
「ぶっくれっと」129号から153号にかけて24回連載された「ぶっくれっと名画座」のなかから、映画解説の25編をアップしました。
『荒野の決闘』
『第三の男』
『天井桟敷の人々』
『東京物語』
『北北西に進路を取れ』
『七人の侍』
『アラビアのロレンス』
『甘い生活』
『大人は判ってくれない』
『俺たちに明日はない』
『市民ケーン』
『カサブランカ』
『自転車泥棒』
『ローマの休日』
『街の灯』
『仁義なき戦い』
『美女と野獣』
『勝手にしやがれ』
『明日に向かって撃て!』
『ティファニーで朝食を』
『お熱いのがお好き』
『ひまわり』
『キューポラのある街』
『にっぽん昆虫記』
『ショート・カッツ』
『荒野の決闘』MY DARLING CLEMENTINE(130号)
監督 ジョン・フォード
主演 ヘンリー・フォンダ、ヴィクター・マチュア、リンダ・ダーネル
製作 二十世紀フォックス、1946年、98分
【物語】
1880年代、アリゾナの平原で移送中の牛を奪われ、見張りの末弟を殺されたアープ三兄弟。長兄のワイアット(ヘンリー・フォンダ)は無法の町トゥームストーンの保安官となり、牛泥棒のクラントン一家と対決する。さらに弟のヴァージルまで殺されたワイアットとモーガン(ワード・ボンド)の兄弟は、ドク・ホリデイ(ヴィクター・マチュア)を助っ人に、クラントン一家のたてこもるOK牧場での決闘にのぞむ。
【解説】
ワイアット・アープ兄弟とクラントン一家との決闘を題材とした映画には、この作品のあとも『OK牧場の決斗』(1957)、『墓石と決闘』(1967)、『トゥームストーン』(1993)があり、ケヴィン・コスナー主演『ワイアット・アープ』(1994)という作品もありました。実伝ということで、『荒野の決闘』以前にも製作されたものがあります。ちなみに、OK牧場(コーラル)のコーラルとは、われわれが思い浮べる牧場ではなく馬の置き場のことで、たしかに映画を見ていると、馬を一時的に置いている場所という感じがする。だから「馬囲い」と翻訳する人もいます。
このようにいろいろな映画が作られているわけですが、ジョン・フォード作品が実話に近いかというと、決してそうではないようです。ワイアット・アープは拳銃の名手で保安官という理想的な人物として登場しますが、実際はあんなにいい人間ではなかったという説もあり、『トゥームストーン』などはそれに近い描き方でした。しかし『荒野の決闘』には、西部の人間の友情とか心意気というものがよく出ていたと思う。西部劇のエッセンスという感じがします。
ジョン・フォードが目ざしたものは男の映画であり、「男とは何か」ということが『荒野の決闘』でよく描かれていると思います。ワイアット・アープは一家の長男として弟たちの面倒をみる。寡黙で、やることはきちんとやって、沈着冷静、しかも行動は素早い。面白いのは女性に対して非常に紳士的です。これはヨーロッパ中世の騎士道精神の流れだという人もいますが、やはり西欧の紳士(ジェントルマン)というもの、その理想像なのでしょう。それが根底にある。
それは、一昔前の人間がイメージしていた男らしさというものかもしれませんが、しかしアメリカだけのものではなく、かつて日本の男たちがもっていた男らしさにも通じると思います。だからこそ、私がワイアット・アープという男に惹かれ、今でもあの映画が好きなのだと思うのです。
ワイアット・アープに対するにドク・ホリデイは非常に派手な役作りです。西部の朴訥な人間ワイアットに対し、東部で学んだ医者くずれの賭博師ドク、こちらはシェークスピアをそらんじていたり、恰好も通俗な感じで、コントラストとしての人物造形になっている。同じように女性も、対照的な二つのタイプの典型が描かれます。一方は淑女のクレメンタイン(キャシー・ダウンズ)であり、他方あばずれのチワワ(リンダ・ダーネル)、一目でわかる対比です。
この一種の明快な単純さ、わかりやすさはかつての映画がもっていた素晴しい長所であり、強みだったと思います。今、そういうものはできない時代になってきました。その意味では、そういう人物造形をクリアに作りあげることができた時代、それは映画にとって幸福な時代だったと思うのです。
敵役のクラントン一家の父親(ウォルター・ブレナン)も、今だったらもっとどぎつく演じるでしょうが、意外とあっさりしてしかも残酷なところがある。本当に悪い人間とはこういう人かもしれないと、そんな人物の造形の仕方が面白いと思う。また目立たない人物ですが、ワイアットの弟役のワード・ボンドも、地味ではあるけれど燻銀の演技です。
ジョン・フォードはアイルランド民謡を効果的に使います。この作品でも「マイ・ダーリング・クレメンタイン」、また『黄色いリボン』(1949)などでも使いますし、民謡によって一種の素朴な詩情を感じさせるのがうまい監督です。アイルランド気質といったものがそこにあるのかなと思いますが、一種懐しい感じがします。
最近でこそ減ってきましたが、西部劇というのはアメリカ映画が確立した素晴しいジャンルだと思う。アメリカ映画は、西部劇とミュージカルとを自分たちの固有のジャンルとして作り出した。その西部劇のなかで、『荒野の決闘』は三本の指に入るのではないか。何べん見ても、いい映画です。
(ビデオ フォックスビデオ・ジャパン発売)
監督 キャロル・リード
主演 ジョセフ・コットン、オーソン・ウェルズ、アリダ・ヴァリ
音楽 アントン・カラス
製作 ロンドン・フィルム、1949年、100分
【物語】
第二次大戦直後、英米仏ソ四か国の分割管理下にあったウィーンが舞台。アメリカの作家ホリー・マーティンス(ジョセフ・コットン)は旧友ハリー・ライム(オーソン・ウェルズ)に招かれウィーンに来るが、ハリーの突然の死を知らされ葬儀に立ち会う。しかし、その死に疑問を持ち真相を究明しようと行動するうち、ついにハリーの生存をつきとめる。そして、国際警察の英国代表からハリーの犯罪を知らされた彼は、警察に協力し友人を追いつめる。
【解説】
ちょうど『第三の男』が公開されたころ、私は映画のジャーナリズムの世界に入りました。個人的な思い出話になりますが、当時『キネマ旬報』の若手の編集者が故荻昌弘氏で、荻さんはこの映画のシナリオを採録したり、今ふうにいうと大いに入れ込んでいたというか、傑作だと語っていたのをまざまざと覚えています。私は若気の至りで、そんなに傑作かなと眉唾の思いで見ましたら、やはり傑作だったという作品です。しかし、ちょっとうまく出来すぎの感もしましたが。
キャロル・リード監督、ロバート・クラスカーの撮影で、戦争直後の廃墟のようなウィーンの街、そして四か国に支配されていた、そういうやりきれない状況というのが非常によくわかりました。戦後のヨーロッパの雰囲気がよく出ていたと思います。クラスカーはモノクロの撮影では第一人者といわれた人です。
キャロル・リード作品では、『第三の男』と同じころに見た『邪魔者は殺せ』(1947)に感心しました。彼の映画にはサスペンスがあり、次に何が起こるかと、その期待感で引き込まれていく。そういう演出のうまい監督です。『第三の男』でも、ジョセフ・コットン演じる売れない作家が、車で何かわけのわからないところへ連れて行かれる場面があって、そういう不安感を描き出すのがうまい。観客はついつい引き込まれてしまいます。映画の展開の仕方が実に映画的だと思うのです。
私は今でも同じ考えをもっていますが、映画というものは結局、基本的には時間の流れで流れていくわけですけれども、次に何が起こるか、そういう期待感をもって流れていくときに、映画は成功するのではないか。次に起こることが見えてしまうと、観客は緊張しません。どうなるかわからないという緊張感が常にあることが、映画にとって重要な条件だと思います。その意味で『第三の男』はまさに映画です。
そして、オーソン・ウェルズの顔が暗闇からすっと浮び上がる、有名なシーンです。彼が『市民ケーン』(1941)を作った奇才だということは、本などで情報としては知っていましたが、『市民ケーン』の日本公開はもっと後になります。ですから『第三の男』ではじめて見て、いかにも悪党面といいますか、しかも知的な感じがある、すごい俳優だと思いました。「スイス五百年の同胞愛と平和が生み出したものは鳩時計だけだ」、これは原作にあるせりふで、別にオーソン・ウェルズが作り出したものではないでしょうが、彼が口にすると、いかにも彼の言葉という感じがします。
また、最後の場面も有名です。並木道をアリダ・ヴァリが遠くから歩いて来て、手前で待っているジョセフ・コットンを一顧だにせず去って行く。あの別れの場面など、雰囲気がよく出ている映画だと思います。全編に流れるアントン・カラスのチターの音楽もその雰囲気を生かしましたし、あらゆる意味で、当時は衝撃的な作品であり、キャロル・リードの傑作と思います。
余談ですが、イギリス映画はアメリカ映画と違って独特の雰囲気があったと思います。それは、湿度と水の問題ではないか。アメリカ映画はカラッと乾いていて、湿度が低い感じが強いのですが、反対にイギリス映画はジメッとしている。その湿り方が、日本の湿気とはまた違って、冷え冷えとしています。冷たい感じがする。カラーになってくるといっそうそれがはっきりします。それは、撮影所の空気と現像に使う水とがデリケートに映像に反映していると思うのです。
個人的な思い出をもう一つ。私はこの映画を見た後、ずっとたってウィーンに行きました。あの有名な観覧車にも乗りましたが、あれは大きいものです。四、五人でいっぱいになるような日本の観覧車を想像していたら、十人以上も乗れるようなだだっ広い、殺風景で無愛想なものでした。知人と二人だけで乗っていると、心細くて高所恐怖症になったような感じで、窓のほうへ行くのが怖かったのを覚えています。
映画に出てくる「カフェ・モーツァルト」へも行きたいと思い、そのウィーンの知人に話しますと、あのカフェは映画ができてから作られたものだといいます。映画は所詮は虚構の世界ですから、嘘をついてもいいわけです。その映画の嘘が実物を作り出してしまう。それが本当になってしまう。映画はそういう力を持っているのです。
(ビデオ アイ・ヴィー・シー発売)
『天井桟敷の人々』LES ENFANTS DU PARADIS(131号)
(第一部 犯罪大通り、第二部 白い男)
監督 マルセル・カルネ
主演 アルレッティ、ジャン=ルイ・バロー、マリア・カザレス、ピエール・ブラッスール
製作 パテ・シネマ、1944年、190分
【物語】
《第一部》
1840年代のパリ。犯罪大通りと呼ばれた、見世物小屋や劇場の立ち並ぶ街を舞台として、パントマイム役者バティスト(ジャン=ルイ・バロー)と女芸人ギャランス(アルレッティ)の恋を中心に多彩な人物が織り成す人間模様。野心家の役者ルメートル(ピエール・ブラッスール)やモントレー伯爵(ルイ・サルー)などがギャランスに熱を上げる一方、座長の娘ナタリー(マリア・カザレス)はバティストに思いをよせていた。
《第二部》
数年後、バティストはナタリーと、ギャランスは伯爵と、それぞれ結婚していたが、その二人がはじめて一夜を共にする。が、翌朝、ナタリーの訴えにギャランスはバティストを振りきり、カーニヴァルの雑踏の中に消えてゆく。
【解説】
天井桟敷(パラディ)というのは劇場の三階席のこと、料金も一番安い大衆席で、そこの子供たちという原題ですが、要するに芸能の世界の物語になります。ストーリーは錯綜していて、登場人物も多く、一種の群像ドラマといえる。今ふうにいえば大河ドラマでしょうが、マルセル・カルネ監督はひそかなレジスタンスの思いを込めて作った。ナチ占領下の製作で、あの群集にはそういう心意気があると思うのです。ただ、時代は百年ほど古い時代に設定して、一種の暗喩といいますか、そんな意味合いが込められている。
ロマンとかロマネスクという言葉があります。男女の恋愛という意味に受けとられることが多いのですが、そうではなく、物語的世界という意味でのロマネスクな感じというものが、この作品では力づよい流れで展開されていきます。時代のうねりのようなものが見えてくる。しかもその力づよさというものは荒っぽさではなく、登場人物の感情とか心理が非常にデリケートに、きっちり描かれていて、見る人にそれが伝わってきます。そのへんの完成度の高さというのはすごいと思います。
大河ドラマといいますと、しばしば登場人物ばかり多くて、ドラマの骨格がすぐ透けて見えてしまうような、図式的なものが多いわけですが、この作品では生命力をもって人物が動いている。人物に血が通っています。物語も深い豊かな水量の川が流れているような、まさに大河という感じでゆるやかに、しかしまた確実に流れていきます。フランスらしく、惚れたはれたの話が多いのですが、登場人物が生きていますから、その思いがちゃんと伝わる。
ジャン=ルイ・バローをはじめフランス演劇界の名優たちが出てきて、今でもこれほどのキャストを組むことは難しいのではないかという顔ぶれです。われわれの世代ですとおそらく、ジャン=ルイ・バロー演ずるパントマイム役者、バティストに相当の感情移入をして見ていたと思います。彼はギャランスが好きなのに、思うように打ち明けられない。好きだと言えないとか、自分の思うとおりにはいかなくて、羨望とコンプレックスをもって女性を見ているという感じは、多分われわれの時代の青春だと思うのです。
バティストがギャランスに惹かれる、年上の女を好きになるというところもフランス的です。アルレッティというのは年増の魅力にあふれた女優で、日本でも江戸時代にはいたかなというような、粋といいますか、ちょっとあだっぽい感じのある人です。そういう女性は若者にとって手の届かないところにいる、憧れなのだと思います。ですから、ギャランスのとりこになると、すぐそばにいるナタリーの良さはわからなくなってしまう。このナタリー役のマリア・カザレスも舞台女優で、映画出演は初めてということですが、非常な好演です。
人生は、役者も作家くずれの無頼漢も、あるいは富で女をものにする貴族も、どちらが良いということはなく、それもまた充実した生き方なのだということ。そういう生きている感じというのが、それぞれの人物をとおして表現されているということです。これぞフランス映画というか、人間のキャラクターとか感情のとらえ方はさすがという感じがします。脚本・台詞は詩人のジャック・プレヴェール。
1989(平成元)年、マルセル・カルネは第一回高松宮殿下記念世界文化賞を受賞しました。私は同賞の映画部門の専門委員をやっておりまして、その授賞式に出席するためマルセル・カルネが日本へ来たとき、一緒に食事をしたことがあります。八十歳のおじいさんでしたが、まだ映画を作りたいと熱をこめて語っていた。その執念はすごいものだと思いました。
(ビデオ CICビクタービデオ発売)
監督 小津安二郎
主演 笠智衆、原節子、東山千栄子、杉村春子、山村聡、中村伸郎
製作 松竹、1953年、140分
【物語】
七月初旬、広島県尾道で末娘と暮す周吉(笠智衆)、とみ(東山千栄子)の老夫婦が、東京下町で町医者をしている長男(山村聡)と、美容師の長女(杉村春子)のもとを訪れる。日々忙しくしている長男、長女は表面は歓迎するものの、いささか迷惑な話でもあった。そんなとき、戦死した次男の嫁(原節子)だけは老夫婦にやさしく接し、一日東京見物に案内する。長男、長女の勧めで熱海に一泊した老夫婦だが、予定を切り上げ尾道へ帰って間もなく、とみは亡くなってしまう。
【解説】
小津安二郎の作品では、この映画をベストとするか、あるいは『晩春』(1949)を一番とするか、どちらかに分かれることが多いと思いますが、登場人物が多く、しかも全体の物語の膨らみがありバランスがとれている点で、『東京物語』はナンバーワンといえる。人物像の描き込みもしっかりしていて、スケールといいドラマの厚みといい、『東京物語』は小津安二郎の最高作ではないかと私は思っています。
昭和28年の映画ですけれども、家族が解体していく、家族制度が崩壊していくという話をそのころすでに何気なく、さりげなく描いている。その後、日本の社会が変化し、高度成長があり昔の家族制度が壊れ、大家族が分解していくという事態になって今日に至っているわけで、この映画はいわばその予言的な内容になっています。
老夫婦が尾道から、東京で暮している子供たちに会いに来る、それを迎える側は、うわべは歓迎しながら、それぞれの生活で忙しく、有り難迷惑に思うという話です。結論的なテーマというのは、老夫婦にとって、血のつながった自分の子供よりも、血のつながっていない嫁のほうがよほど親身になって面倒を見てくれる。自分たちのことを考えてくれる。気持ちも、子供より嫁とのほうが通い合うという皮肉なテーマで、そういう人間関係が描かれています。
つまり、世の中の人間関係はそう単純ではない、気持ちの通い合いというのは血のつながりとは別だという、いわば平凡な哲学ですが、それがさりげない描写のなかで、説得力をもってうまく描かれている。そこが『東京物語』の一番の勘所ではないかという気がします。当時、小津さんは四十九歳、老境の気持ちというものが実に的確に描き出されているのはすごいと思います。
俳優陣も、笠智衆をはじめ山村聡、東山千栄子、杉村春子といういわゆる小津組といわれるベテラン俳優が多数出ています。笠智衆も四十代で七十歳の役を演じているわけで、背中がまるく見えるようにと、着物の下に布団を入れたという話があります。長女役の杉村春子がうまいし、東山千栄子もよかったと思います。
それにつけても不思議に思うことは、小津安二郎にしても溝口健二にしても、名作を作った時期は四十代です。完成した、すぐれた作品を作って、四十代で巨匠と呼ばれている。彼らが早熟だったのかもしれませんが、ところがその後の監督たちは、いつまでたっても若さを失わないというと褒め言葉になるけれど、若気が抜けないというか、成熟しない。あのころは社会状態そのものが成熟していたのでしょうか、実に大人の目をもって世の中を見ています。その点、今見ても感心させられるところです。
しかし、そうした小津さんの映画の良さが本当にわかるようになったのは、正直のところずっとあとになってからのことです。学生のころには、どこがいいのかよくわからなかった。映画評論家はいいというけれども、テンポは遅いし、事件は起こらないし、座って話をしている場面が多く、アクションがない。さらにフェイド・インとかフェイド・アウト、暗くなって終りという場面転換ではなくて、全部カットでつないでいく。そのカットの切れ目切れ目がなめらかではなく、一回ごとにパチッとシャッターが落ちるような、そんな印象をもちました。
私も若いころは、映画はアクションである、映画は動きだと勝手に決めていたわけです。映画は写真ではないのだから、アクションが物語を進めていくと思っていた。ですから小津さんの映画で、座り方もバランスがとれてシンメトリックという、何か記念撮影をしているような、そんな画面のどこがいいのか、よくわからなかったのです。つまり、アクションのない映画を感知できるアンテナを持っていなかったということでしょう。
それは私自身がまだ未熟で無知だった、映画に対してだけではなくて、自分を取り巻く世界に対していまだ成熟していず無知な部分があった、ということだと思います。小津さんの良さがわかってくると、一つ一つの画面に気配りと味が仕込まれているといいますか、きっちりと作られていることに感心します。どうしてそれに気がつかなかったのか、自分には目がなかったのか、はじめからそれが見抜けるようでないといけないのではないかと反省したものです。
(ビデオ 松竹ホームビデオ発売)
『北北西に進路を取れ』NORTH BY NORTHWEST(132号)
監督 アルフレッド・ヒッチコック
主演 ケーリー・グラント、ジェームズ・メイスン、エヴァ・マリー・セイント
製作 MGM、1959年、136分
【物語】
広告代理店社長ロジャー(ケーリー・グラント)はある日、別の人物と間違えられて誘拐され、タウンゼント(ジェームズ・メイスン)と名乗る男に協力するよう強要され、あやうく殺されかける。翌日、タウンゼントを訪ねると、まったくの別人で、しかもロジャーの目の前で殺され、ロジャー自身が犯人として追われる身になってしまう。謎の美女イヴ(エヴァ・マリー・セイント)の助けを得たロジャーはニセのタウンゼントを追う。
【解説】
ヒッチコックの代表作となりますと、たとえば戦前からのヒッチコック・ファンである双葉十三郎氏は『疑惑の影』(1942)に高い点を与えています。(『ぼくの採点表I』)それは、イギリス映画時代から見ていると、その流れで『疑惑の影』の良さというのがよくわかると思うのです。しかし私は戦後から見たので、ちょっと受けとり方は違ってきます。イングリッド・バーグマン主演の『白い恐怖』(1945)や長いキスシーンのある『汚名』(1946)など、あまり成功していなかったと思う。そのころ見はじめた限りでいいますと、ヒッチコックは面白いものもあるけれど失敗作もあるぞと、うまく出来ていない作品もある、という感じで見ていました。
私がこれぞヒッチコックと思ったのは、『北北西に進路を取れ』とか『鳥』(1963)です。とくに、『北北西』はヒッチコック・ワールドの集大成といえるのではないか。まずスパイ・アクションであり、ヒッチコックが得意とした巻き込まれ型、関係のない人物がある事件に否応なく巻き込まれてしまうという話です。『間違えられた男』(1956)の系列で、人違いで事件に巻き込まれて、次々に事件に遭遇するという、その段取り、趣向が面白い。
それに、ヒッチコック映画では案外珍しいのではないかと思うのが、だだっ広いトウモロコシ畑で、飛行機から襲われる有名な場面です。指定されてバスを降りて待っていると、だれも現れなくて、はるか彼方を農薬散布の飛行機が飛んでいる。一体何が起こるのかと、逃げ場のないところでの恐怖感というのがまずうまいし、点景として飛んでいた飛行機が実はあとで襲ってくるという意外性、そしてその逃げ方、あの場面の演出はすごいと思います。
ヒッチコックはどちらかというとスタジオで撮る人で、ロケをやらない。だから今の学生たちにヒッチコック映画を見せると、カーチェイス・シーンなどスクリーンプロセスを使っているので、ちゃちだという。手抜きだといいます。しかし『北北西に進路を取れ』ではそういう手抜きは感じられません。つまり映像的な広がりというか、ヒッチコック映画としてはスケールがあり、迫力もありますし、この畑の場面や最後の、岩肌に四人の大統領の顔が刻まれたラシュモア山での追いかけシーンなど、映画史に残る名場面だと思います。
ラシュモア山の場面はセットで撮った部分がかなりあるようですが、前に『逃走迷路』(1942)では自由の女神像での追いかけシーンがありました。また、列車のなかでのサスペンスというのも『バルカン超特急』(1938)でやっています。だから『北北西』にはヒッチコック的サスペンス、スリルというものがほとんど全部入っているといっていいでしょう。
俳優はヒッチコック好みのブロンド女優、エヴァ・マリー・セイント、おしゃれでスマートなケーリー・グラントが主役、ジェームズ・メイスンの悪役と、それぞれがはまり役です。俳優の面白い使い方の例では、『裏窓』(1954)のジェームズ・スチュアートがある。足を骨折していて全然動けない状態という、ヒッチコック的な表現技巧がさえわたった作品でした。そういう意味では、ヒッチコックの作品はそれぞれ面白さがあるし、失敗作も含めてあれくらい映画的な技巧に工夫を凝らした作家もちょっと珍しい。
アンソニー・パーキンスが主演した『サイコ』公開のときに、ヒッチコックは日本に来て、小林信彦さんが編集していた『ヒッチコック・マガジン』の座談会に出たことがあります。そのときの出席者は淀川長治、双葉十三郎、野口久光、それから字幕の清水俊二の諸氏という錚々たる顔ぶれで、実はそういう人たちにまじって私も出ました。小林さんと親しかったものですから、同じ世代の仲間が一人いたほうがいいと、私を呼んだらしい。ですからその座談会で、ヒッチコックに会って話を聞いたことを懐しく思い出します。
(ビデオ CICビクタービデオ発売)
監督 黒澤明
主演 三船敏郎、志村喬、加東大介、宮口精二、木村功、千秋実、稲葉義男、土屋嘉男
製作 東宝、1954年、207分
【物語】
戦国時代、山間の貧しい村が舞台。野武士の一団の襲撃を受け、収穫物を掠奪される村では自衛のため侍を雇うことにする、ただし、報酬は腹一杯米のメシを食わせるというだけで。それだけの条件に命をかける侍はなかなか見つからなかったが、やがて勘兵衛(志村喬)という侍がこれを引き受け、勘兵衛の魅力にひかれて七郎次(加東大介)、若侍・勝四郎(木村功)、百姓あがりの菊千代(三船敏郎)など六人が集まる。そして野武士と七人の侍との戦いが始まり、最後はどしゃぶりの雨の中で、すさまじい合戦となる。
【解説】
この作品の脚本は黒澤さんと橋本忍、小国英雄の三人の手になるものです。絶体絶命のシチュエーションをつくって、そこをどう切り抜けるかということを宿題に、翌日みんなそれぞれに答案を出し、そのなかでいちばんいいのをとって、そこからまた話を進めてゆく。そういう集団制作をやったようです。その成果でしょうか、脚本がよくできています。
まず、七人を集めるエピソードがおもしろい。それぞれタイプの違う七人の描きわけも巧みです。七人のなかでは、三船を三枚目的、コメディ・リリーフ的に使って、しかも見せ場をちゃんとつくっている。それから、七人の侍が百姓相手に戦闘訓練をし、勘兵衛を軍師として敵の襲撃に対する作戦を、図面を描きながら周到に練っていく。西部劇パターンといいますか、村にたてこもって敵の来襲を待ち、その間にも敵を一人ずつ倒していくというような、あのへんのコンストラクションはすごいと思います。
『七人の侍』は黒澤映画の集大成といってよいでしょう。この作品がいかにすごい映画かということは、これをもとに作られた西部劇『荒野の七人』(1960)と比べればよくわかります。『七人の侍』を見たあとでは、『荒野の七人』はそれなりにまとまっているけれど、いかにも軽いという感じがする。ディテールの描きこみが段違いです。あれだけの描きこみをしていけば、三時間半の長い映画になったのもやむをえないと思います。
製作費も製作日数もかかりすぎるということで、製作会社の東宝と一悶着あって、一時、撮影中止になったりします。東宝はそこまでのフィルムをまとめて上映すればいいと思ったらしい。黒澤さんは、それならフィルムを見せようと、見せたらやっぱりまだ撮らなければいけないとわかって、また撮影が始まったという話です。未完成でも、たとえ半分でもこの作品を見れば、その先を見たくなるのは当然です。私など、子供のころにワクワクして読んだものに講談本がありますが、そういう講談的なおもしろさが『七人の侍』にはまぎれもなくあると思うのです。
テストをして侍を集めていくところや宮口精二が演じた剣豪の人物像など、まるで講談のようです。ただし、講談調といっても黒澤作品は張り扇でポンポンとリズムよく展開していくわけではない。稲垣浩監督であれば、テンポよく軽快な時代劇になったかもしれませんが、黒澤さんはどうしてもヘビー級です、軽くは弾まず、どっしりと腰をすえた感じで物語が展開します。百姓たちの描写もしっかりしていますし、黒澤さん自ら、女を描くのはあまりうまくないといっていたけれども、この作品では村の女たちをうまくこなしています。
百姓といえば、最後の場面で勘兵衛が「勝ったのはあの百姓たちだ。儂たちではない」とつぶやきます。こういう、侍たちは傭兵として利用されただけではないかといった黒澤さんの解釈、時代のとらえ方は間違っているという人もいます。しかし、小村の農民が自分たちの生き残りのために、どんなことを考えていたかということはよく出ていると思う。侍についても、あの時代は混乱期です。生産手段をもたない武士が安定した生活はえられない、そういう状況のなかで苦労していただろうということは、的確にとらえています。
また、村の長老を高堂国典(『姿三四郎』の和尚役です)が演じています。昔から活躍してきたバイプレイヤーですが、そういう古い俳優に対し敬愛の念をもって起用する。黒澤さんは俳優を大事にする監督だった、それは映画マニアにはうれしいところです。
そして、この作品のころから黒澤さんは意図的に望遠レンズとか複数のカメラを使いはじめます。『七人の侍』にはその効果がよく出ていると思う。かつて黒澤さんに、映画の仕事のなかでいちばん好きな部分はどこですかと聞きましたら、「編集だ」という答えです。たとえば、三台のカメラを使って撮ったフィルムを並べて見ていきながら、「この場面はこのフィルムのこことここから」という形でまとめていく。それがいちばん楽しいというのです。
それだけに、そうしたショットとショットのつなぎ方の緊密な感じは黒澤映画の特徴といえます。息詰まるくらい緊密に感じられることもある。他の監督の映画だったら、もうちょっと息の抜ける場面になるところを、黒澤さんの場合はもっぱら豪速球を投げるタイプで途中でカーブなど投げたりしない。もちろんストーリーの上では変化をつけますが、こと描写になりますと、スピードを落とすようなことはしません。このエネルギーはふつうの日本人よりも、一回り大きかったという気がします、
そこのところが、黒澤作品が外国で理解されたり、受け入れられたりした大きな要因になったのではないか。黒澤さんのスケールの大きさ、あの一種のパワーのありようというのは、日本サイズではなく外国サイズだったのではないか。ですから外国人には何の不思議もなく、すんなりと受け入れられたのではないかと私は思います。
『七人の侍』は娯楽映画としても、またいわゆる活劇としても、それからまた人間のドラマとして、農民と武士の関係をきっちりおさえて描いた点でも、完璧な映画ではないかと思っています。
(ビデオ 東宝株式会社発売)
『アラビアのロレンス』LAWRENCE OF ARABIA(135号)
監督 デヴィッド・リーン
主演 ピーター・オトゥール、アレック・ギネス、アンソニー・クイン、オマー・シャリフ
製作 英・コロムビア、1962年、222分
【物語】
英国陸軍退役士官T・E・ロレンス(ピーター・オトゥール)の事故死から物語は始まり、その人物像と行動が描かれる。第一次大戦中、ドイツと同盟を結んだトルコの侵略に抗し、アラブの独立を目指すファイサル王子(アレック・ギネス)の参謀となったロレンスは、ハウェイタトの酋長アウダ(アンソニー・クイン)やベドウィンの酋長アリ(オマー・シャリフ)と共にトルコ軍の基地アカバを攻略、ダマスカスを奪回する。しかし、アラブ民族内部の反目抗争と、英国政府の中東支配という政治的駆引きに敗れたロレンスは失意のうちに戦場をあとにする。
【解説】
『アラビアのロレンス』でいちばん感心したのはやはり砂漠の美しさであり、砂漠そのものがドラマになっていることです。自然を見る視点がしっかりしていて、砂漠の美と砂漠の怖さをとらえる、その描写の力にひじょうに感心しました。(撮影はフレッド・A・ヤング)デヴィッド・リーンの自然描写では『ライアンの娘』(1971)のアイルランドの風景、断崖絶壁の大ロングショットがありますし、『インドへの道』(1984)での描写も心に残るものです。
『アラビアのロレンス』では、砂漠のなかの井戸のところにロレンスが立っていると、はるか彼方からゆらゆらと小さな米粒のような影が、蜃気楼みたいな形で揺れながらだんだん近づいて来て、ラクダにのった人物がオマー・シャリフだとわかる。ワンショットのこの描写には、これぞ映画と、魅入られるというか、すごいものだと感動しました。このシーンがあるだけで、『アラビアのロレンス』は不滅といえるのではないか。
また人物描写も見事なものです。人物の造形力がしっかりしていて、自然の美しさ、厳しさに拮抗しながらロレンス以下の人物像が、そして人間関係がきめ細かく描かれていきます。
ピーター・オトゥールの演じたロレンス、その薄い青い目に象徴される一種の狂気に通じた情熱とか、アレック・ギネスのファイサル王子、オマー・シャリフやアンソニー・クインのアラブの族長など個性的な人物が客観的に描かれます。デヴィッド・リーンの演出は正攻法で、オーソドックスな映像のなかに力強さとか、叙情的な美しさを表現する。ひじょうにバランスのとれた映画作家、スケールの大きい作家であり、そのリーンの代表作が『アラビアのロレンス』だと思うのです。
ロレンスのアラブ世界に対する情熱というものが、イギリス政府の政治的思惑のなかで巧妙に利用され、捨てられていくというストーリーで、そうした政治の動きをかなり辛辣に描きながら、しかし政治劇になっているわけではない。政治をきっちりとらえると同時に、そのなかで個人の情熱がどんなふうに燃焼してゆくか、トルコ軍将校とのホモセクシュアルの場面まで描きながら、ロレンス像を造形していきます。
その場合も、ロレンスはこういう人間だったというはっきりした解釈は、デヴィッド・リーンは出していません。ふつう作家というのは、自分が抱えている問題のほうへ流れていくものですけれど、リーンはいろいろ問題を出し、要所要所をしっかり押さえながら、そのいずれにも偏らないところがある。そういうバランス感覚は見事です。しかも内容の濃い大作であり、名作である。映画のお手本という感じのする映画です。 主演のピーター・オトゥールはこのときが最初の本格的な主演映画でしたし、オマー・シャリフも、エジプト映画では大スターだったわけですけれど、このようなメジャーな作品は初めての出演です。それをああいう形で世界的に知らせたというのは、やはり監督の力量が大きいと思うのです。
私はデヴィッド・リーンに一度会ったことがあります。『インドへの道』という映画ができたとき、配給会社からロンドンへ行ってインタビューしてほしいと頼まれ、一人でロンドンへ行きました。最高級ホテルを定宿にしているとのことで、通訳の人と一緒に訪ねたら、もう七十歳はすぎていましたが、若々しく気さくな人でした。
「何を飲むか」と聞きます、「コーヒーをいただきます」といったら、「ここのコーヒーはまずいから、ネスカフェにしなさい」という。それで電話で注文しています。何が出てくるかと思いましたら、しばらくしてボーイがもってきたものは、白い紙ナプキンに山型に盛りつけたネスカフェです。リーンがスプーンをとって、「何杯?」といいます。「二杯」と答えますと、「ずいぶん濃いのが好きなんだね」といいながらカップに入れて、お湯をついでくれた。そんな思い出があります。
(ビデオ ソニー・ピクチャーズエンタテインメント発売)
監督 フェデリコ・フェリーニ
主演 マルチェロ・マストロヤンニ、アヌーク・エーメ、アニタ・エクバーグ、アラン・キュニー
製作 伊・リアマフィルム、1959年、173分
【物語】
作家志望のジャーナリスト、マルチェロ(マルチェロ・マストロヤンニ)は享楽的な生活に身をゆだねている。ナイトクラブで知り合った富豪の娘(アヌーク・エーメ)と一夜をともにしたり、ハリウッドの女優(アニタ・エクバーグ)と狂乱の夜を過ごしたり。インテリの友人(アラン・キュニー)の自殺にショックをうけ、作家になる夢もやぶれ、上流社会の甘い生活に溺れるマルチェロ。そんなパーティーの夜明け、海辺に出ると腐った大魚がころがっている。浜をへだてる川の対岸には清純な少女がほほえんでいるが、しかし彼はまた倦怠と頽廃の世界へ戻ってゆく。
【解説】
『甘い生活』の冒頭に、ヘリコプターが大きなキリスト像を吊り下げて飛んでいく場面があります。それを、ビルの屋上でビキニ姿の若い女たちが、日光浴をしながら眺めている。つまり、宗教と現代生活というもの、その爛熟とか頽廃といったものを、このワンショットでずばりとらえています。こういう感覚がフェリーニのすごいところと思うのです。
映画というのは、全体がよくできているとか、あるいはすぐれた俳優が名演技をみせているとか、いろいろありますけれど、結局、最終的に記憶されるのは鮮烈なワンショットだけではないか。あの映画のストーリーも忘れた、監督の名前も忘れた、俳優が誰かも忘れた、しかし、あの場面だけは忘れない――という名場面を一つもった映画は、大げさな表現ですが、永遠に生きつづけるのかなという感じがします。
『甘い生活』にはほかにも名場面があり、たとえばラストシーンもすぐれたものですが、やはりキリスト像が空を飛ぶオープニングのシーンは強烈な印象として残っています。また、現代的な風俗を映像としてとらえるのがうまい作家で、アニタ・エクバーグが深夜トレヴィの泉のなかへ入って行く場面など、古代ローマの遺跡と現代のグラマーな女優の取り合せという、そこから生まれる強いインパクトがあります。それを一枚の絵にしてしまう。
この作品は、キリスト教、カトリックというものに対する作者の関心が強く出ていると思います。聖母を見たという子供の取材に、主人公のジャーナリストをはじめ報道陣が殺到する。そして、奇跡を求めてそこに群れ集う人々を描くことで、現代における宗教というもののもつ、一種のうさん臭さをとらえています。人々が宗教の虜になるのは、情報操作によってあやつられているだけではないのか。そういう作者の醒めた目を感じられると思うのです。
マストロヤンニの演じる主人公は、フェリーニの分身と思いますが、現代版地獄巡りでいろいろな経験をする、それがエピソード形式で描かれていきます。あの時代の頽廃というものが一つの大きなモチーフになっていて、たとえばアラン・キュニーというフランスの俳優が演じたインテリ、主人公の友人が突然自殺してしまうエピソードは、そういう知的な人物が行きづまってしまう時代状況を的確に描き出します。
最後の場面、これは非常にわかりやすいのですが、遊びほうけた朝、砂浜に出ると、川をへだてた向こう岸に清純な少女がいて心ひかれる。が、波の音が高く互いに言葉が聞き取れない。清純な少女は救いなのですが、こちら側は腐りきった世界であり、その象徴のような不気味な怪魚、腐った大きな魚が砂浜に打ち上げられています。
こういう、何の説明もなく映像のみで現代を象徴してみせるあたり、フェリーニはやはりすごい作家と思います。フェリーニの映像的なイマジネーションの豊かさ、それはひょっとすると、ルネッサンス以来のイタリア芸術文化、その伝統が現れているということなのかもしれません。
『世にも怪奇な物語』(1968)という、ロジェ・ヴァディム、ルイ・マルとフェリーニの三人で撮ったオムニバス映画があります。ルイ・マルも立派な映画作家ですが、しかしフェリーニに比べると、いかにもマイナーに見えてしまう。三つの短い作品を並べて見ると、フェリーニの作品の内容の豊かさ、映像の力強さ、イマジネーションの大きさ、深さ、そういったものが歴然としているように思うのです。
よく大芸術家を「マエストロ」と呼びます。英語で「マスター」ですが、この呼び名に真にふさわしい作家がフェリーニだと思います。どんな小品を作っても、それが大作になってしまう。非常に豊かな作品になっています。まぎれもないマエストロです。
(ビデオ 日本ヘラルド映画株式会社発売)
『大人は判ってくれない』LES QUATRE CENTS COUPS(138号)
監督 フランソワ・トリュフォー
主演 ジャン=ピエール・レオ、クレール・モーリエ、アルベール・レミ
製作 レ・フィルム・デュ・キャロッス、1959年、98分
【物語】
十二歳の少年アントワーヌ(ジャン=ピエール・レオ)は、共稼ぎの両親の不和や学校の先生から問題児扱いされていることもあり、面白くなく、悪友と小さな悪事を重ねていた。ある日、自分の作文を酷評されたことから先生と衝突し、そのまま家出をしてしまう。父親の勤めるオフィスからタイプライターを盗み出したものの、うまく捌けず、そのタイプライターを返そうとするところを捕まり、両親にも見放されて少年感化院に入れられてしまう。そして、脱走するが……。
【解説】
フランスでは1950年代末に若い映画作家が登場し、それまでのフランス映画――ジュリアン・デュヴィヴィエとかジャック・フェデー、マルセル・カルネというフランス映画の伝統をつくってきた人たち――にたいする批判をこめた作品を相次いで発表します。もともと映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」に寄稿していた批評家出身のクロード・シャブロール、フランソワ・トリュフォー、ジャン=リュック・ゴダールといった人たちであり、彼らの作風はヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)と呼ばれるようになります。
考えてみますと、そのすぐ後で日本でも大島渚、篠田正浩という人たちが出てきて、いわゆる松竹ヌーヴェル・ヴァーグと名づけられたり、またイギリスではトニー・リチャードソンを筆頭にフリーシネマ運動とか、演劇では「怒れる若者たち」が出てくるわけです。そうした動きを見ると、単にフランス映画だけの狭い世界の地殻変動だったのではなく、文化の状況というものが、やはり世界的に変革期だったのではないか。そうでなければ、そんなふうに申し合わせたように、あちこちで同じような動きが出てくるわけがないと思うのです。
1950年代の終わりといえば、第二次大戦後も十五年になります。ここで、あるいは戦前から確立されていた社会的、文化的な意味での制度といものが崩壊したのではないか、そういう時期だったのではないかという気がします。そして新しいものが出てくる、そういう時期にフランス映画はすばらしい才能を生み出したということではなかったか。
シャブロールの『いとこ同志』(1959)では、大学入学をめざす従兄弟の二人、一方は金持ちの遊び人で、もう一方は田舎から出てきてまじめに勉強をしている。ところが、遊び人がすべてに成功するのにたいし、勉強家のほうは受験に失敗し、最後はロシアン・ルーレットのようなことをしてピストルで死んでしまう。救いのない話であり、秩序とか体制というものへの反逆、反発がモチーフになっています。
トリュフォーの『大人は判ってくれない』と、ゴダールの『勝手にしやがれ』という同年(1959)の作品も新しい映画のつくり方を示したものといえます。とくにゴダールは映画の表現に革命を起こした感がありますが、トリュフォーの作品は、手法的にはいろいろ新しいことを試みたり、若い世代の表現を主張しながら、ドラマの内容そのものはオーソドックスなものです。そして、以後トリュフォーは恋愛ドラマのほうへ進んだこともあり、映画作家として正統的なコースを歩んだような印象があります。
『大人は判ってくれない』はトリュフォー自身の少年時代を題材にして、少年の屈折した気持ちとか、ドロップアウトしてゆく少年の人生が的確にきっちりと描かれます。(主人公を演じたジャン=ピエール・レオは成長するにしたがって、トリュフォーの自伝的な作品「アントワーヌ・ドワネル」ものに、ずっと主演することになります。)
そして、この映画がのちのちまで新鮮な感度を残しているのは、ラストシーンで、少年が孤児院を脱け出して海岸を走って行くところがストップモーションで終わっていることです。これは当時の映画の表現の仕方として、ひじょうに新しかったと思うのです。ふつう映画では、画面が暗くなって(フェイド・アウトして)終わりになる。一つのドラマがそこで終わるわけですが、ストップモーションというのはそれまで提示してきた問題をそのまま止めてしまう、結論を出さないのです。
少年はその後どうやって生きていくのか、ひょっとして死んでしまうのか、主人公に感情移入をしている観客は考えざるをえないわけで、なるほど、こういう終わり方もあるのかと当時は感心したものです。ただ、その後ストップモーションが流行して、いろいろな形で使われるようになり、いい加減な映画で、最後にストップモーションで逃げるというようなものもずいぶんありました。しかし『大人は判ってくれない』に関しては、あの終わり方が正しかったと、トリュフォーのオリジナリティがそこに出ていたと思います。
後年のトリュフォーでは、私の好きな作品に『隣の女』(1981)があります。妻子と幸せに暮らしている主人公の隣に、彼のかつて愛した女が越してくる。焼け棒杭に火がつくといいますか、彼のほうははじめ避けていたのが、デパートの駐車場で会ったときに女が気を失う。それくらいの情熱的な表現というものを、トリュフォーはうまく描きます。そうなると男はやはり放っておけない。結局、日本の「道行もの」にも似て、最後は無理心中ということになりますが、そういう一種の恋愛至上主義のような作品を見ますと、トリュフォーという人はロマンティシズムとか愛とかいうものが好きだったのだとあらためて気づきます。
(ビデオ ポニー キャニオン発売)
『俺たちに明日はない』BONNIE AND CLYDE(139号)
監督 アーサー・ペン
主演 ウォーレン・ビーティ、フェイ・ダナウェイ、マイケル・J・ポラード、ジーン・ハックマン
製作 タティラ/ヒラー・プロ(ワーナー)、111分、1967年
【物語】
1930年代の不況下、テキサスで刑務所に二年服役したクライド(ウォーレン・ビーティ)はウェイトレスのボニー(フェイ・ダナウェイ)と出会い、二人は次々と強盗を働く。少年院出の若者C・W(マイケル・J・ポラード)と、さらにクライドの兄夫婦(ジーン・ハックマン、エステル・パーソンズ)を仲間に加え、銀行強盗など犯罪を重ねていたある日、五人は警察に包囲され兄が射殺されてしまう。ボニー、クライド、C・Wの三人は辛くも逃げるが、それも束の間、C・Wの父親の密告によって警察の待ち伏せに遭ったボニーとクライドは数十発の弾丸を浴び倒れていく。
【解説】
アメリカン・ニューシネマといいますと『イージー・ライダー』(1969)のイメージが強いのですが、じつはその二年前に、『タイム』誌が『俺たちに明日はない』の特集をして「ニューシネマ」と命名したので、ニューシネマはこの作品から始まったといえます。しかし同じ67年に、マイク・ニコルズ監督『卒業』も公開されているものの、この流れが本格的になるのは、『イージー・ライダー』や『真夜中のカーボーイ』『明日に向って撃て!』の公開される1969年からといってよいでしょう。
ボニーとクライドという実在した男女の銀行強盗の話はすでに何度か映画化されていて、私もみていますが、アーサー・ペンの作品は最初の場面から「すごい映画だぞ」という印象をもちました。通りすがりに自動車を盗もうとする素振りのウォーレン・ビーティを二階の窓からみたフェイ・ダナウェイが、声をかけてあわてて階段をおりてくる。その姿を階段下の正面から仰角で撮るという変ったアングルを使っています。スカートの奥はみえないにしても、危険なアングルというか、大胆だなという感じをまず受けたのです。
この主演の二人は溌剌として、ひじょうに新鮮に感じられた。たしか、フェイ・ダナウェイはこの作品が三本目の映画出演です。けっして美人型とはいえない、悪女が似合う個性的な女優で、その後も多くの映画に出ています。そうしたフェイ・ダナウェイの作品のなかでも、『俺たちに明日はない』の彼女は生き生きとして、いちばんよかったように思います。
そして二人が強盗をはじめると、なにか間が悪くてうまくいかない。気負って銀行へ押し込むと、その銀行は破産していたり、そういう一種の間のはずし方がまたおもしろかったのです。これはいわゆる銀行強盗ものの、型通りの犯罪映画ではないなとみていると、クライドは不能だという。アンチヒーローというか、これまでのボニーとクライドものにはなかった話です。ただ、そういう人間的な欠陥を描いても、そこになにかやわらかい感受性のようなものが見受けられます。
それは周りの人物についてもいえるので、クライドの兄夫婦が途中から合流して犯罪に加担するようになりますが、義理の姉がけっこうヒステリックで、いつもボニーと口論したり、トラブルを起こしたり(姉役のパーソンズはこの作品でアカデミー助演女優賞を受賞)。それは単に話をおもしろくするための描写ということではなく、みんなそれぞれどこか性格の破綻した人物が集まっている、そういうところがまた、私には新鮮に思われたのです。
映像も、とてもきれいだったと思います。とりわけ私の好きな場面で、警察の追っ手を逃れてボニーの一家と広い草原で会う。ボニーと母親が再会するところなど、叙事詩のような、かつ悲しみに満ちあふれた素晴らしい情景と思います。ロングショットとアップとの組み合せもよかったし、その画面から、なにか詩的な感じを受けました。ボニーが詩を書くこともあり、犯罪映画のなかに文学的な、人間的な感じがうまく盛り込まれています。
それにユーモア感覚があります。銀行に押し入ったら破産していたというのもそうですし、マイケル・J・ポラードを運転手に使うと、彼が車の置き所を間違えてうまく逃げらないとか、一種の滑稽感です。しかも、マイケル・J・ポラードの存在も、単なる三枚目として描かれるのではなく、最後には彼の父親が警察に密告するわけで、滑稽さがあとで美しい悲劇に昇華していく。そんな印象をもちました。
そして「死のダンス」といわれる最後の場面。スローモーションの撮影で、八十七発の銃弾を撃たれて踊るようにして死んでいく。真っ白な車も穴だらけになるという場面も、やはり美しくみせるという、青春の終わりにふさわしい美しさです。
アーサー・ペンという監督はわりにムラのある人で、いい作品もあれば、あまり成功していない映画もあるのですが、そのなかで『俺たちに明日はない』は、人間関係が密接に組み立てられていて、きっちりとよくできた映画です。何度みても、名作だなと思います。 (ビデオ ワーナー・ホーム・ビデオ発売)
監督 オーソン・ウェルズ
主演 オーソン・ウェルズ、ドロシー・カミンガー
ジョゼフ・コットン、ウィリアム・オランド
製作 RKO、119分、1941年
【物語】
マスコミを牛耳ってきた新聞王ケーン(オーソン・ウェルズ)が「ローズバッド(バラの蕾)」という謎の言葉を残して亡くなった。ニュース映画の製作者トンプソン(ウィリアム・オランド)はケーンの生涯を知ろうと前妻や友人たちへの取材を始める。六歳で伯父の遺産を継いだケーンはやがて新聞社を買い取り、親友リーランド(ジョゼフ・コットン)と協力して巨万の富を築くが、私生活では妻にも愛人(ドロシー・カミンガー)にも去られ、一人寂しく死んでいったのだ。そしてトンプソンが荒廃した邸宅を訪ねたとき、暖炉に子供用のソリが投げ込まれた。静かに燃えるそれには「ローズバッド」という文字が刻まれていた。
【解説】
この作品は名作の誉れが高かったのですが、日本公開は――アートシアターギルドが輸入して映画館でみることができたのは――ずいぶん遅れて1966年になります。それまでにオーソン・ウェルズについては、天才とか鬼才という噂は前から聞いていましたので、どんな映画かと期待をもってみたものでした。私がひじょうにおもしろいと思ったのは、映画の構造がハードボイルドの探偵小説に似ていたことです。
ハードボイルドの探偵小説では、ひとつのパターンとして、何か事件が起こると、私立探偵がそこへ聞き込みに行くことから始まって、事件に関係のありそうな場所や人物のところへ行っては調べてくる。そしてだんだん真実の核心に迫っていく、という構造が圧倒的に多いと思います。『市民ケーン』でも同様に、新聞王ケーンの死から、「いったいケーンとは何者だったのか」と、記録映画のプロデューサーが関係者に会ってインタビューし、核心に迫っていくという構造になっています。こうしたつくり方に、アメリカ文化のひとつの特色を見ることができるのではないか。
そしてケーンが死んだときに、ニュース映画の特集のような形で、彼の業績を紹介する。今でいうと、テレビのドキュメンタリーみたいなものですが、劇映画のなかにドキュメンタリーの手法を入れてしまう。つまり、物語としての映画という枠にしばられない、そういう新しさが、公開当時の観客に衝撃を与えただろうことはよくわかりました。
名高い新聞王のハーストをモデルにしたケーンという人物は、人生の勝利者としてザナドゥという大邸宅に住んで、大統領の姪を妻にし、さらに愛人をオペラ歌手に仕立てようとしたりする。それほどの才能のない女性を、金の力によって周囲の人間を動かしてしまう。これもある意味でアメリカのヒーローといいますか、アメリカ的なサクセス・ストーリーといえるでしょう。そんな人物を主人公に、彼の死後その実体を探っていくというつくり方、もちろん偶像破壊的な面もあり、ジャーナリスティックな感じもあり、ノンフィクション的な視点を感じたりしました。 「ローズバッド」というキーワードについて、その意味がよくわからないという説がありますが、映画の最後の場面で、ケーンが子どものころ乗っていたソリにローズバッドという焼き印が押してあり、それが暖炉で燃やされるとき「ローズバッド」の文字が浮かびあがってくる、という印象的な結末になっています。つまり、新聞王にも少年時代のイメージが根底のところにあったということでしょう、そういう解釈でいいのではないかと思っています。巨大な存在であっても、一介のささやかな人間と同じようなところに原点はある、ということだろうと私は理解しました。
監督・主演のオーソン・ウェルズはこのとき二十五歳。後年のように太ってもいないし、貫祿はもう一歩で、大成功者を演じるにはちょっと若い。ただ、精悍な感じとか野心に燃える感じというのはよく出ていました。ですから、老けのメイキャップをするわけで、そのこと自体がつまり虚像というか、贋の姿というものを考えさせるテキストになっているのではないかと感じました。
撮影はグレッグ・トーランド、この作品はパン・フォーカスで有名です。全焦点といいますか、奥のほうのものと手前のもの、両方にピントを合わせることで奥行きの深い画面をつくり出す。それはどういうことかというと、一か所だけにピントが絞られると意味がはっきり単一になるのに対し、すべての画面がシャープに写るということは、そこからいろいろな意味が出てくるということです。意味が複雑に、錯綜してくる。また、画面自体に密度が出てきます。
当時は今ほどカメラの性能がよくなかったわけで、パン・フォーカスというのは難しい撮影だったようです。その後、これはウィリアム・ワイラーも使っていますし、日本では戦後、吉村公三郎さんが縦の構図ということを意識して使った。画面に奥行きと、密度を出すためです。『市民ケーン』ではそういう技術が、画面に緊張感を生み、一種のサスペンスとかスリルというものも生んでいます。オーソン・ウェルズは映画をよく知っているなと思ったものです。
そのころは私もまだ若く、「映画とはいったい何か」とか、「映画の表現とは」あるいは「なぜ映像で表現するのか」とか、いろいろ考えたものです。映画を毎日みながら、いつも考えていたわけで、そういうことを勉強するのに『市民ケーン』はひじょうにいいテキストになった。そういう意味では、この作品のもつ価値は今も変わらないものがあると思っています。
ところが今の学生たちは、学校の授業で「映画史上の名作だ」といってみせても、あまり感動しないようです。それはジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』(1959)をみせたときの反応にも通じるものがある。私などにとって『勝手にしやがれ』というと、形式を破壊した直感的な映画表現で、たいへんな衝撃を受けた作品です。場面がポンポン飛んだり、映画表現の文法といったものを全部ひっくり返したような革新的な映画でした。しかし、ゴダールがオリジナルにつくり出した表現のスタイルも、今になってみると同様のものは周囲にあふれているわけで、その元祖をみたからといって、驚くほどのことはないということなのでしょう。
若い世代はいろいろな形の映像に接しています。『市民ケーン』のドキュメンタリーをとりいれた映画表現のスタイルにしても、何ら目新しいことではないわけです。そうすると、この作品のドラマ的な構造は何か。物語をたどってみたら「成功者の人生を追跡していくと、ふつうの人間と同じだった」という内容では、新発見でもなんでもない、ごく平凡な話になってしまいます。ということで、かつてこの映画がもっていた衝撃度も、若い世代にはまったく薄まってしまうのではないでしょうか。
(ビデオ CBS・ソニー発売)
監督 マイケル・カーティス
主演 ハンフリー・ボガート、イングリッド・バーグマン、ポール・ヘンリード、クロード・レインズ、ピーター・ローレ
製作 ワーナー、102分、1942年
【物語】
第二次大戦中の1941年、フランス領モロッコの首都カサブランカはナチス・ドイツから逃れてアメリカへ亡命するための中継地となっていた。アメリカ人リック(ハンフリー・ボガート)の経営する酒場も亡命希望者をはじめ、さまざまな人物でにぎわう。そんなある日、彼は昔の恋人イルザ(イングリッド・バーグマン)と再会する。イルザにもパリでの思い出とリックへの愛が蘇えるが、しかし彼女は反ナチス運動の指導者ラズロ(ポール・ヘンリード)の妻であった。ラズロにはイルザが必要と悟ったリックは自ら身をひき、ナチスの少佐を射殺して二人を脱出させる。
【解説】
『カサブランカ』がつくられたのは戦争中ですが、日本での公開は戦後一年ぐらいたってからでしょう、そのときの印象として、傑作とか秀作とか、そんなことは少しも思わず、ただひじょうにおもしろくみたことをおぼえています。そして、やはり驚いたのは、戦争中につくられているにもかかわらず、けっこうのんびりした恋愛映画だったということです。同時期の日本ではちょっと考えられなかったので、日米のゆとりの差というようなものを痛感したものでした。
もっとも、『カサブランカ』は戦争と関係がないわけではなく、ナチス・ドイツによってパリが陥落する状況が背景ですから、ヨーロッパ戦線も戦局が厳しくなってきているはずですが、そんな切迫感はあまり感じられない。アメリカではメロドラマの傑作といわれているとおり、まったくのメロドラマです。といって、メロドラマだからと評価を低くするのではなく、メロというのは音楽のメロディのメロと同じで、つまりおもしろおかしく、感情豊かに見せるということであり、『カサブランカ』はそういうメロドラマのおもしろさを堪能できる作品といえます。
反ナチ運動の闘士ポール・ヘンリードが妻のバーグマンといっしょにリックのバーにやって来て、ハンフリー・ボガートに出会う。バーグマンとボガートはかつてパリで恋愛関係にあったという、通俗といえば通俗なストーリーですけれど、通俗に徹すると、そこに一つの立派な作品ができるという、その見本のような映画ではないかと思います。実は、この映画は撮影に入ってからも脚本が完成せず、結末についても、二通りも三通りも案があったという、かなり場当り的につくられたようです。が、それにしてはよくできていると感心します。
また、せりふが決まっています。はじめのほうでハンフリー・ボガートがなじみの女に、「昨夜はどこに」と聞かれて、「そんな昔のことはおぼえていない」と、「今夜、会ってくれる」と聞かれると、「そんな先のことはわからない」。かっこいいせりふで、今あらためてみるとうれしくなります。もっとも戦後間もなく、はじめてみたときはそんなにうれしくなることはなかったわけで、われわれのなかにまだ戦争のショックのようなものが残っていたのでしょう。
ハンフリー・ボガートの苦み走った、ハードボイルド的な男の魅力と、バーグマンの一種の若さというか、ひたむきに生きる女性という取り合わせがうまく合っていたと思います。バーグマンは感情が高まったりするときの、パッショネイトな演技のうまい女優ですが、この作品ではういういしい清楚な美しさにあふれていた。そして、周囲の人物がみなおもしろい。ドイツ軍人、フランス警察署長、いわくありげな人物など、それぞれの典型として描かれています。
当時のフランスはドイツに占領され、ヴィシー政権ができています。つまり、カサブランカの警察はヴィシー政権の出先機関となるわけで、本来ナチスに協力しなければいけない、しかしそこにフランス人としてひそかに反逆の精神が出てくるという、そんな警察署長を演じたのがクロード・レインズ。一方、反ナチの闘士ラズロを追いつめるナチスの将校にコンラッド・ファイト。リックと同業の酒場の経営者に太ったシドニー・グリーンストリート。闇のパスポートをさばいているあやしげな人物にピーター・ローレと、周りの人物はみんなよかったと思います。
この映画を下敷きにしたような、つまりリックのバーのようなひとつの場所に全員が集まってくるという構成で、そこにさまざまな葛藤が生まれてくるといった作品はけっこうつくられていますが、この映画での、そうした多彩な人物のさばき方はやはりうまい。その場その場で脚本ができてきて撮ったとは思えないほどきっちりしています。監督はマイケル・カーティス。いわゆる商業監督というか、娯楽性豊かな作品をひじょうに多くつくっていることで実績があり、この作品でアカデミー監督賞を受賞しています。
せりふのよさということでは最後の場面で、ラズロ夫妻を飛行機で逃がしたボガートとクロード・レインズが肩を並べて歩いて行く、ボガートの「美しい友情の始まりだな」というせりふも効いています。この作品のメロドラマ性というのは、たぶん単に男女間のものだけではなく、男の生き方のメロドラマもあるのではないか。男たちが何かに情熱をかけ、かっこうよく生きているという、そこが魅力的だと思うのです。
アメリカ映画は今でも、男を主人公にしたメロドラマをよくつくります。これが、日本ではなかなかつくられないジャンルです。日本の今の映画やテレビドラマでは、ビデオゲームのノリでかっこよく生きる人物は出てきますが、もうちょっと歯ごたえのある、男の生き方そのものにかかわるドラマは乏しいと思う。平たくいって、男のロマンの感じられるものです。そういう意味でも、『カサブランカ』はいわゆるメロドラマの見本といってよいでしょう。
それから、この映画は一切ロケをやっていません。モロッコに行くことなく、すべてハリウッドのセットでつくられています。かつてはそういうつくり方が多かったので、効率よく製作を進めるためには撮影所のセットの中がいちばん早いということです。つまり、天候などに左右されることなく一定のコンディションのもとで撮影できる。雨が必要な場面にはそこだけ水を降らせればいいわけです。
このハリウッド式映画製作法は三十年代の終わりに完成したと思うのですが、以後五十年代までアメリカ映画は、ロケの部分の多い西部劇を例外として、セットで撮影されたものが多かった。ですから、よくご存じのように、車で走る場面や山の上に人が立っている場面などスクリーンプロセスで撮りますから、なんとなく違和感がある。また、風は扇風機でおこすので、安っぽさというか、そういう感じを否めないのですが、みるほうもそれで納得していた時代の映画です。
ついでながら、アメリカにいる友人に聞いた話で、『カサブランカ』には熱狂的なマニアがいるそうです。あの場面はどうだったかと、ひじょうに細かいところにこだわる。たとえば最後の場面で、双発の飛行機のエンジンは左右どっちが先に回ったかと、そういうことを問題にするマニアがいるらしい。バカバカしいことですけれど、それくらい熱狂的な愛好家のいる映画ということです。
(ビデオ発売 ワーナー・ホーム・ビデオ)
『自転車泥棒』LADRI DI BICICLETTE(142号)
監督 ヴィットリオ・デ・シーカ
主演 ランベルト・マジョラーニ、エンツォ・スタヨーラ
製作 デ・シーカ・プロ=イタリフィルム、88分、1948年
【物語】
第二次大戦後のローマ。長い失業生活の後で、アントニオ(ランベルト・マジョラーニ)はやっとポスター貼りの仕事にありつく。そこで何とか質屋から自転車を請け出し、息子のブルーノ(エンツォ・スタヨーラ)を連れて街角のポスター貼りに精を出す。ところが、ちょっとした隙に自転車を盗まれてしまう。アントニオ親子はローマの町中を探し回り、やっと犯人を見つけるものの、証拠がないため逆に追い返される。絶望したアントニオはつい他人の自転車を盗むが、すぐに見つかり捕えられてしまう。
【解説】
イタリアン・リアリズム(これはアメリカのジャーナリズムの呼び方で、イタリアでは「ネオ・レアリスモ」といいます)の代表作で、今みると暗い、救いのない話ですが、しかし感動しました。子役が自然で実にうまい。もともとイタリア映画は子役がうまいといわれていますが、『自転車泥棒』のようなリアリズム映画で子役の演技がいいのはと、不思議に思ったものです。
イタリアの戦中・戦後の現実をリアルに描いた映画はロベルト・ロッセリーニの『無防備都市』(1945)、『戦火のかなた』(1946)あたりから始まり、ヴィットリオ・デ・シーカの『靴みがき』(1946)や『自転車泥棒』、ルイジ・ザンパの『平和に生きる』(1964)、ピエトロ・ジェルミの『鉄道員』(1956)、『刑事』(1959)などが、イタリアン・リアリズムとして世界的な評価を受けるようになります。
われわれの大先輩で、亡くなられた飯島正さんによると、しかしイタリアは昔からリアリズムの面があったといいます。戦後になって忽然と出てきたのではなく、1910年代、20年代にイタリアでいわゆる古代史劇が多くつくられていたときは、実際に旧跡でロケをした、それは本当にリアルだったというのです。サイレント時代です。ですから、そういう伝統が、ちょっと隔世遺伝的なかたちで、戦後のリアリズムにつながったのかもしれません。
『自転車泥棒』のストーリーは前に記しました通り、失業中の主人公が就職活動に奔走して、やっとポスター貼りの仕事につく。それには、自分もちの自転車に乗って回りながら貼るわけで、自転車が必要です。金をかき集め、借金もして自転車を手に入れ、小さい男の子といっしょにポスター貼りをやっていると、途中でその自転車を盗まれてしまう。自転車がなくなったら、仕事にもあぶれてしまいます。それで、落ち込んでいるときにふと見ると、誰かが乗っていた自転車がそこに置いてある。出来心でつい盗むわけですが、そういう人は盗みも下手ですから、すぐ捕まってしまう。という、なんの救いもない話です。
そこに、これが戦後のイタリアの現実だ、という感じがよく出ているように思いました。主人公に素人を使っていることもリアリズムを際立たせています。そして子どもが、親の困った状態を一生懸命に心配したり、そのかわいらしさというか、そういうところはつまり、つき放したリアリズムというだけではなく、ちょっと情にからんでくるような、いわゆるイタリア的なところがあったかなという気もします。
デ・シーカという監督はあとで『ひまわり』(1969)のような作品をつくる人ですから、人情がらみの話は得意です。もともとは人気俳優で、監督になってからも、思想的にリアリズムを掲げて出てきたわけではない。その意味では、ネオ・レアリスモを主張したロッセリーニとは違って、従来の映画の文脈をもちつつ、なおかつ戦後の現実というものをうまくすくいあげていく。『自転車泥棒』も、映画づくりのノウハウをよく知っている監督が、当時の現実をリアルに切り取ったという感じの映画と思うのです。
ロッセリーニの『無防備都市』と『戦火のかなた』にちょっと触れますと、『無防備都市』は敗戦間近に撮った映画で、敗戦濃厚のローマが非武装都市宣言をする、そのローマで起こったゴタゴタの話です。この作品の原題名は「チッタ・アペルタ」、英訳して「オープン・シティ」となります。
『戦火のかなた』は南のほうから上陸した連合軍が北へ進攻して行く間の出来事を四つぐらい、エピソード風に描いています。ドラマ性はほとんどなく、ニュース映画を思わせるような、まさにリアリズムです。私などがみて驚いたのは、軍隊が死体を川に捨てる場面が、本当にニュース映画のように、ロングショットで情緒をまったく無視してポンと捨てていく。その即物性にたいへんショックを受けました。
このようなイタリアン・リアリズムに徹底したロッセリーニにくらべると、もう少し人間的なアプローチで映画をつくりつづけたのがデ・シーカといえます。その後、ちょっと宗教的な要素も入れた『ミラノの奇跡』(1950)とか、『屋根』(1956)をつくったり、一方で役者もしばらくつづけております。そこから、マルチェロ・マストロヤンニとソフィア・ローレンと組んで人情喜劇、『昨日、今日、明日』(1963)や『ああ結婚』(1964)など、ひじょうに達者な映画づくりをしていく。
『ひまわり』は戦争によって夫婦の間を裂かれた男女を描いたものです。夫(マストロヤンニ)がロシア戦線で消息を絶って帰って来ない。ずっとイタリアで待っていた妻(ソフィア・ローレン)が探しに行くと、そこでロシアの村の一面のひまわり畑が出てくるのですが、夫は助けてくれたロシアの女性と結婚して平和に暮らしていたという話です。こうなると、戦争の問題はいちおう入れているし、戦争に行く前の喜劇的な描写もおもしろいものであっても、やはりメロドラマといえる。デ・シーカはそういう意味で、娯楽的なものからシリアスなものまで、わりと幅広いジャンルをうまくこなした監督といえます。
イタリアは大女優の出る国といわれますが、いわゆる巨匠、イタリア風にいうとマエストロといわれる監督もけっこう出ています。車のデザイナーでもそうでしょう、いろいろな分野でチームワークではなく個人が目立つ国です。そういうところは、日本とは反対かもしれません。
(ビデオ発売 東芝映像ソフト)
監督 ウィリアム・ワイラー
主演 オードリー・ヘプバーン、グレゴリー・ペック、エディ・アルバート
製作 パラマウント、118分、1953年
【物語】
ヨーロッパ各国を親善訪問中の某国の王女アン(オードリー・ヘプバーン)一行はローマを訪れる。パーティの後、公式日程にいや気のさした王女はこっそり宿舎を抜け出し、偶然、アメリカ人の新聞記者ジョー(グレゴリー・ペック)と出会う。彼女が王女であることに気づいたジョーは、カメラマンのアーヴイング(エディ・アルバート)と謀って、王女をローマ観光に連れ出して盗み撮りし、特ダネをものにしようとする。王女とジョーはスクーターに相乗りし、ローマの名所を回るうち、お互いに魅かれ合うものを感じるのだった。そして翌日、王女の記者会見が行われる。
【解説】
私はこの三月、跡見学園女子短大の非常勤講師を定年で辞めました。なんと二十八年間勤めたことになります。いつの間にか過ぎてしまった感が強いのですが、そんなに長く非常勤講師をやった人はいないと、卒業式に花束を贈呈されました。
私の授業に登録する学生は視聴覚教室に入る人数にしぼられますから、毎年百人ぐらいが対象となります。まだ二十歳前ぐらいの女子学生ですが、彼女たちに必ず「私の好きな映画ベストテン」を書いてもらうことにしていました。十本選べない人は五本でもいいと、またできたら感想も書いてほしいということで、レポートを提出してもらう。すると、映画好きな学生はたくさん書いてきますし、逆に三本も選べないような学生もいます。毎年それを書かせておりますと、その時代、時代の女子学生の映画に対する好みというのがはっきり出て、おもしろいデータになっています。
たとえば、ジュリア・ロバーツの『プリティ・ウーマン』が上映された年は、この作品にワッと票が集まったり、一昨年から昨年にかけては『タイタニック』が断然一位でした。今年は『アルマゲドン』が去年からの流れで強い、といった動きはありますけれど、そういう流行にまったく関係なく強いのが『ローマの休日』です。これは常にベスト5には入っている。(今の学生はほとんどビデオでみているようです)。
かつて『風と共に去りぬ』が強かったことがありますが、最近はそれほどでもない。むしろ『サウンド・オブ・ミュージック』のほうが人気があるかなというところで、古典というか、古い映画のなかで頭ぬけているのが『ローマの休日』です。これは若い女の子が大人になっていく途中で通過しなければいけない、イニシエーションのような役割を果たしている映画という気がします。
監督はウィリアム・ワイラー、いろんな映画をうまくとる人で、『我等の生涯の最良の年』(1946、アカデミー監督賞、作品賞外五部門で受賞)、『探偵物語』(1951)、『大いなる西部』(1958)、『ペン・ハー』(1959)など、あげればきりがないくらい、よい映画をつくっています。真面目な映画から肩の凝らない、軽いコメディまで、エンターテインメントをかっちりつくる技術ももっている。
主演のオードリー・ヘプバーンは日本でひじょうに人気のある女優ですが、『ローマの休日』の成功はオードリー・ヘプバーンを発見したこと、彼女をヒロインに抜擢したことが最大の理由と思います。それまで二、三本の出演作しかなかったヘプバーンがこの映画で一躍スターになる(アカデミー主演女優賞受賞)。とりわけ日本では人気がでて、これ以後二十年ほど人気投票をすれば高い支持を受けることになります。
日本では、マリリン・モンローやエリザベス・テイラーのようなグラマー・タイプより、オードリーやグレース・ケリーのように痩せぎすで、つまり肉体というものを感じさせない、感じのいい女優を好む傾向があります。それに、西欧の感覚でみると美人ではないかもしれませんが、オードリーにはさわやかな、聡明な感じと気品がある。汚れ役をやっても品があった、そのへんが日本人の好みに合ったのでしょう。
『ローマのの休日』は逆シンデレラ物語といいますか、王女としがない新聞記者の淡い恋物語――永遠に受けるテーマでしょうが――、それが実にうまくつくられています。それに外国の恋愛映画では、肉体的な交渉があったかどうかというところに必ず触れるのが、この映画はそこをぼかして、きれいにまとめてある。それも日本人に受けた理由と思います。
それから、エディ・アルバートのカメラマンや王女のお付きの人々など、喜劇的要素も取り込んであります。また、王女が失踪したということで王女の国の情報部員がかけつけて来る。飛行機から次々と降りてくる彼らはみんな黒づくめの服装です。ロビーに出迎えた大使でしたか、「目立たないように来いといったのに」というと、「だから、あれは(つまり黒づくめは)私服だ」という答え、ああいうユーモアのある場面はうまいし、ひじょうに楽しくみました。
また、何度みても感心させられるのは、その時代の感覚をうまく取り込んでいることです。たとえばファッションや髪形など、王女が長い髪を切りますが(この美容院のシーンもまた楽しいものです)、その髪形が「ヘプバーン・カット」として日本で大流行します。当時はそれだけ映画というものが時代の先駆けというか、流行を生み出す力をもっていた。時代の風俗というものに対する映画の影響力は強かったのです。
グレゴリー・ペックがヘプバーンを乗せるスクーターはイタリア製のヴエスパという、当時、世界的に人気があったものですし、二人がめぐるローマの名所旧跡もうまくピックアップされています。ですから、今でもローマを訪れた観光客がヘプバーンをまねて、スペイン広場でアイスクリームを食べる。そういうマジックがまだ生きているのです。嘘をついていると手がぬけなくなるという真実の口も、私の聞いたところでは、それまで有名ではなかったのが、この映画で広く知られるようになったという。それだけの力を持っているのは、やはりすごい映画と思います。
『ローマの休日』のバリエーションといった感じの映画は、その後も何度となくつくられています。最近の『ノッティング・ヒルの恋人』でも、大女優(ジュリア・ロバーツ)と街の本屋(ヒュー・グラント)の恋物語、最後に記者会見になるという、骨組みは同じようなものです。そういう物語の決定版が『ローマの休日』だった。若い女性にとっては一種、青春のバイブルのような映画といえるでしょう。
ついでながら、「ローマン・ホリデー」という原題について論じた、慶應大学英文科教授の最終講義が英語雑誌に掲載されているのを私の弟が読んで、興味があるだろうと私にコピーを送ってくれました。「ローマン・ホリデー」を単に「ローマの休日」と訳すのは、正しい翻訳ではないというのです。つまり、「ローマ人の休みの日」とは何か。ローマ人は奴隷をライオンと闘わせて、それを眺めて楽しんでいた、それが「ローマ人の休日」だという。そんなことを分析・説明した最終講義です。なるほど、そうだったのかとおもしろく読んだものです。
私がそこで意外に思ったことは、オードリー・ヘプバーンはユダヤ人であるという。ウィリアム・ワイラーもユダヤ系ですが、オードリーはたしか父親がオランダ人、母親がイギリス人だったと思います。ユダヤ人であることはどうでもいいんですけれど、そういわれてみると、あの顔だちはいわゆるアングロサクソンとはちょっと違った、それがいい形で日本人にも親しまれる顔だちになっていたのかなと、そんなことを感じたりしました。
(ビデオ発売 CICビクタービデオ)
監督 チャールズ・チャップリン
主演 チャールズ・チャップリン、ヴァージニア・チェ
リル、ハリー・マイヤーズ
製作 ユナイト、87分、1931年
【物語】
浮浪者チャーリー(チャールズ・チャップリン)は盲目の花売り娘(ヴァージニア・チェリル)と知り合う。彼女の目を治すため手術代を稼ごうと、チャーリーは掃除夫になったり、ボクサーになったり大奮闘。たまたま酔っ払いの百万長者(ハリー・マイヤーズ)と出会い大金をもらう。しらふにもどった百万長者に泥棒扱いされるが、何とか追っ手を逃れ大金を娘に届ける。しかしチャーリーは逮捕され、刑務所に入ることになってしまう。出所したチャーリーは街角で目の見えるようになった娘と再会。恩人とは知るすべのない娘だが、手をふれあって初めて彼と気づく。
【解説】
1930年代に入ってだんだんトーキー化が進むなかでも、チャップリンは頑として無声映画をつくり続けます。それは彼の伝記を読むと、無声映画が映画の王道だと思っていたということですけれど、意地悪な見方で、「チャップリンは自分の声が悪いことを自覚してトーキーをつくらなかった」という人がいます。実際、それほどいい声ではなかったことはたしかですが、『黄金狂時代』(1925)は無声映画の傑作であり、『街の灯』の次の作である『モダン・タイムス』(1936)でも、ほとんど無声映画に近いつくり方をしています。 『モダン・タイムス』の社会性とか、『黄金狂時代』のギャグを利かせた人間喜劇にくらべると、『街の灯』はちょっと影が薄いのですが、これはチャップリン風のラブストーリーとして、名作といってよいと思います。目の見えない花屋の娘に、チャップリンのいつも演じる浮浪者が好意をもつ。ところが、ちょっとした行き違いで、娘のほうが浮浪者を大金持ちだと勘違いしてしまいます。
浮浪者チャーリーは娘の目をなんとか治してやりたいと、懸賞金のかかったボクシングの試合に出る。ここがまたおもしろい場面で、チャップリンの動きが見せ場のひとつになっています。結局、ノックアウトをくらってしまう。しかし、泥酔した大金持ちと知り合いになったことから、大金を用立ててもらうことができます。ところがこの酔っ払い、しらふになると泥酔中のことをまったく覚えていない。チャーリーは大金を盗んだものとされ、警察に追われるはめに。なんとか娘にお金を渡したあと、彼は捕まってしまいます。
そして数か月が過ぎ、刑務所から出てきたときはもう尾羽打ち枯らしてというか、チャーリーはひじょうにすさんだ顔をしている。あの顔がすごいので、ああいうすさんだ表情までみせるのがチャップリンのすごいところという気がします。それで街を歩いて、新聞売りの子供たちにからかわれながら、その花屋の前にさしかかる。すでに彼女は目が見えることがわかるけれど、娘のほうは彼が恩人だとはわからない。
浮浪者を気の毒に思った娘が小銭を恵もうと、手が触れあう。そのときに、かつて手を触れたときの思い出がよみがえってくる。これはすごいアイディアです。前にもいいましたように、一作品にひとつ、名場面があればいいと思っているのですが、ここはまさにそれです。そして一行のせりふが字幕に出る。日本語の翻訳で「あなたでしたのね」。つづいて「もう見えるようになったのですね」、「ええ、見えるようになりました」。いい字幕であり、二人の顔が交互にクローズアップになって終わるという、ロマンティックな結末です。
チャップリンはたいへんな女たらしといわれ、実際にそうだったようで、私生児騒動とかスキャンダルまみれの時代もありましたが、しかし人の心のつかみ方は実にうまいと思います。男女の思いの機微を鮮やかに、的確にとらえている。そしてチャップリンの映画ではだいたいにおいて、トランプ(浮浪者)というキャラクターからもわかるように、しがない男の主人公が幸せになりかけるけれど、結局それは得られず、繰り返し放浪していくというストーリーです。そこには、叶えられないけれど、いつまでも追い求めている夢があって、それが余韻を残すのだろうと思います。
よくチャップリンと比較される、バスター・キートンという天才的なコメディアンがいます。彼は絶対に笑わず、表情を変えない。ストーン・フェイスとかデッド・パンといわれる大真面目な顔で笑いを追求します。そうすると、彼の場合は、いかに笑わせるかと追求するあまり、一種シュールレアリズム風のシチュエーションになってしまう。たとえば、嵐のなかを歩いていると、風に逆らって歩くものだから、だんだん前のめりになって地面と平行になってしまう。そこまでいきます。
ところが、チャップリンの場合はほどほどのところで笑わせ、泣かせる。ホロッとさせるような要素を必ず入れます。笑いと涙をうまくからませるというところに、物語づくりとしての天才があると思うのです。そういうテクニックを使うことに対して、純粋に笑いというものを考える人は、「チャップリンはずるい」と、泣かせるからずるいといいます。しかし、それがうまくできるというのも天才ではないか。
私がいつも感心するのは、寄席芸といいますか、ボードビルで鍛えた芸です。『黄金狂時代』のパンのダンス、『モダン・タイムス』ではデパートで目隠しをしてローラー・スケートという名場面、それをワンカットで見せる。『街の灯』のボクシング場面もそうで、いわゆる寄席芸人として鍛えたパントマイム芸を必ず作品にもりこんでいます。そうした場面をみると、芸人として一流だということがよくわかる。それに、チャップリンは楽譜が読めなかったのに、音楽は全部自分が書いたとか、実に多彩な才能を持った人だと思います。
私は好みからいえば、バスター・キートンを選ぶのですが、キートンはひじょうに生真面目にコメディを追求して、ついにあまり成功しなかった。最後には、『ライムライト』(1952)でチャップリンに拾ってもらい、チャップリンがバイオリンを弾く隣でピアニストの役をやっています。ここでもキートンはにこりともせず見事な芸を披露する。面白い場面ですが、つまり晩年、キートンはそれほど幸せではなかったと思うので、そういう幸せでない人間に肩入れしたくなります。
しかし、そうしたキートンにくらべて、チャップリンはやはりコメディアンとして文句のつけようのない天才かなという気がします。もちろん、その才能の根底には今いった寄席芸、鍛えられた芸の確かさがあり、それが大本になって、彼の世界が成立しているのでしょう。それにしても、チャップリンはうますぎるというか、しゃくにさわるぐらい、いい映画をつくりやがる、といった気持ちが私にはあるのです。
1940年代の終わりに例の赤狩りが起こると、チャップリンは非米活動委員会の喚問をきっかけに、出頭しないまま52年、イギリスへ去ります。彼はコミュニストだという噂もたてられていましたし、またユダヤ人でもあって、そういうところは嗅覚が鋭いといいますか、自分の身の危険を感じたのでしょう。ハリウッドが謝罪の意味をこめて、チャップリンにアカデミー名誉賞を贈ったのは1972年のことでした。
私生活では最後の夫人となった、劇作家ユージン・オニールの娘ウーナと43年に結婚しています。ウーナ十八歳、チャップリン五十四歳のときでした。チャップリンはまたも、何もわからない娘をだましてと、悪しざまにいわれたりしましたが、このウーナとは円満に添い遂げて、二人の間にできた最初の娘がジェラルディン・チャップリンになります。ジェラルディンはデヴィッド・リーンの『ドクトル・ジバゴ』などに出演し、スペインの映画監督と結婚したりした後、今もときどきヨーロッパの映画に顔を見せているようです。
(ビデオ発売 朝日新聞社)
監督 深作欣二
主演 菅原文太、梅宮辰夫、松方弘樹、伊吹吾郎、名和弘、田中邦衛、金子信雄
製作 東映、99分、1973年
第二作「広島死闘篇」100分、1973年
第三作「代理戦争」103分、1973年
第四作「頂上作戦」101分、1974年
第五作「完結篇」 99分、1974年
【物語】
終戦直後の呉。復員後、広能昌三(菅原文太)は、度胸と気っぷの良さが山守組組長(金子信雄)の目にとまり、その組員となる。当初は微々たる勢力の山守組だったが、敵対する上田組と手を結び、当面の敵、土居組との抗争に全力を注ぐ。一方、土居組では組長(名和弘)と若頭・若杉(梅宮辰夫)が対立。若杉は破門され山守組に加入することで、土居殺害計画は一気に進み、広能は土居暗殺に成功する。勢力の拡大した山守組内部でも抗争はとどまることなく、山守の後継者と目された坂井(松方弘樹)も山守の策謀により無残に殺される。坂井の葬儀の日、広能はヤクザ社会に空しさと怒りを抱きながら山守の前を去って行く。
(第一部)
【解説】
深作さんと親しくお話をするようになったのはそれほど古いことではないんですが、もちろん昔から知っていましたし、会うとお互いに黙礼するくらいのお付き合いはありました。亡くなった田山力哉さんは、深作さんとは飲んべえ同士でよくご一緒したらしくて、飲むと、「飲みながら深作とこんな話をした」ということを私に話してくれたものです。
以前お話した『キネマ旬報』の懸賞論文、私がたまたま一等になったときのことですが、そのとき深作さんも田山さんも応募して二人とも選外佳作になった。ですから二人の話題として、「あれは器の小さいやつが先走りするので、われわれは大器晩成だ」ということを話していると、田山さんはよく冗談めかして言っておられた。深作さんは、その私の懸賞論文を読んで、映画批評なんかやめようと、東映を受けて助監督になったということです。結果的に映画の製作現場に行かれてたいへんよかったと思いますが、まあ、そんな話も聞きました。
深作さんの映画は当初から、テンポがよくスピード感があり、編集がうまく、これは抜群だという印象を私は持っていました。カッティングにすごい切れがあります。それは単にテクニック的にうまいというだけでなく、映像というものに対する、彼の身についた感覚というものが、特別優れていると思っていたわけです。そしてそれが、いちばんすばらしい形で実ったのが、『仁義なき戦い』だったと思うのです。
広島のヤクザの抗争をドキュメンタリー風に描いたこの映画は、ヤクザの世界をわりと醒めた眼で見ています。要するにヒロイズムではない。金子信雄その他の演じるヤクザの大物にしても、みんな人間的にだらしなかったり、こすっからかったり、ケチだったり、あくどいけれど憎めない、そういう人物像がうごめいている、という描き方です。あくの強い人間喜劇のような、そのへんの人間の捉え方も面白いと思います。欲と色にまみれた人間世界を描いて、その根底にあるのは、権力をもっている者に対する絶対的な不信というものではなかったでしょうか。
深作さんの思想というのは、おそらくアナーキズムではないかと私は思っています。要するに、体制というものを認めないという基本的な考えがあるのではないか。ですから、ある種の権力のシステムがあると、それは本来壊れるべきものであり、そしてどういうふうに壊れるかをみていきたいという思いが彼の基本にある。自分の組長からもうとまれるような、一匹狼的な主人公(菅原文太)にも、深作さんの考えが端的に出ているように思います。『仁義なき戦い』は、そういうアプローチをした任侠映画だったのです。
アクション・シーンの演出は抜群にうまいし、痛快な場面もあれば滑稽なところもある。音楽がよく、またナレーションがドキュメンタリー風に、緊迫感を高めています。ですから、よくできたエンターテインメント作品といえますが、それと同時に、『仁義なき戦い』はそれまでの東映の任侠映画、高倉健とか鶴田浩二の伝統的な任侠美学というものの命を早く終わらせる役目を果たしたといえる。そういうものに対する批判になっていたように思います。
任侠の世界は美しいという、それも結構だけれど、そうでない見方もあっていいのではないか。それを、一種の人間群像ドラマのような形で描いた深作さんの仕事は、東映任侠路線の幕を引くという、日本映画の流れの上でひとつのターニング・ポイントになったわけです。深作さんにとって『仁義なき戦い』シリーズは代表作といえるでしょう。とくに第一作はよかったと思います。
ところが、映画というのはどこか偶像みたいなもので、その偶像に憧れながらみるところに、一種、夢の世界が存在するわけです。夢はないんだ、現実はこうだとやることは、それはそれで面白いんですが、しかし夢がなくなるという、そこがちょっと難しいところです。アメリカのニューシネマでも同様の経緯があって、アメリカの現実はこうだと差し示す。最初はインパクトがあったわけですが、そんな嫌な現実なら、みにいく必要はないと、だんだん観客が減っていったということがありました。任侠の美学を地に引きずりおろした『仁義なき戦い』も、同じ問題を課されていたように思うのです。
(ビデオ発売 東映ビデオ)
『美女と野獣』LA BELLE ET LA BETE(146号)
監督 ジャン・コクトー
主演 ジャン・マレー、ジョゼット・デイ、ミシェル・オークレール、マルセル・アンドレ
製作 アンドレ・ポールヴェ、95分、1946年
【物語】
破産の危機に瀕した商人(マルセル・アンドレ)が港から家へ帰る途中、道に迷い野獣(ジャン・マレー)の城に入り込む。末娘ベル(ジョゼット・デイ)のために庭の一輪のバラを折った商人は、野獣に見つかり、その命を投げ出すか、替りに娘を寄こすかと迫られる。父の話を聞いたベルは自ら野獣の城に赴く。醜い風貌の野獣を見て気を失った彼女だったが、毎日の晩餐を共にするうち、野獣がやさしい心の持ち主であることを知る。野獣とは、実は魔法によって醜い姿にされた王子であった。魔法をとかれた王子は、自分の城へ帰るべく、ベルと手をたずさえて空を飛んで行く。
【解説】
この映画は学生のときにみて、「フランスは芸術の国だなあ」と感心したものです。映像の、イメージの独創性というものにショックを受け、こういう映像の世界があるということにたいへん感動した。説明的な描写はほとんどなく、映像そのものが詩になってるという感じです。それはジャン・コクトーという、マルチ芸術家に感心したことにほかなりませんが、その後、『恐るべき親達』(1948)や『オルフェ』(1950)という作品をみて、やはりすごい才能だと思いました。
たとえば、野獣の面のメーキャップが(一説に、日本の能の影響があるといわれますが)、いかにもデモーニッシュな感じがありながら、どこか悲しみみたいなものがほの見える。また、野獣の城で、壁に燭台がありますが、それを支えているのは人間の手です。壁から人間の手が出て燭台を持っている、というイメージはやはり詩人の世界なのでしょうか。それから、胸像の置物が生身の人間で、目が動いたりする、そういった場面は今だに鮮烈な印象として残っています。
最近では、『英国式庭園殺人事件』(1982)のピーター・グリーナウェイが、シンメトリックな構図にこだわった映画をつくっていますが、左右対称の庭園に男性の裸像を置いたりする。それがグリーナウェイの場合には、一種の官能性というか、生な感じが伝わってくるのに対し、コクトーでは、そういう部分が止揚され、象徴的な美的世界、誰も真似のできないイマジネーションの世界が展開します。
あるいは、ひじょうに静かな美しい場面があったかと思うと、急に子どもっぽい場面に変わるというように、その変化の仕方が実に面白かった。そういう変幻自在といった感じのコクトーの虚構の世界、また詩的なイメージの世界に、ほとんど引き回されたように思います。芸術はフランス、映画はフランスという気持ちになったものです。
主演のジャン・マレーはギリシア彫刻のような、彫りの深い古典的な美貌で、知的であり、アメリカ映画には出てこないタイプの美形といえるでしょう。彼の涙は宝石のようだともいわれた。ジャン・マレーとジャン・コクトーと、二人のジャンが深い関係にあったことはよく知られたところです。相手役の女優ジョゼット・デイも均整のとれた美人で、コクトー作品では『恐るべき親達』にも出ています。
「美女と野獣」という話自体は昔からあるおとぎ話のようですが、コクトーの資質でしょうか、おどろおどろしい場面もないではないのが、こけおどしのようなところはまったくなく、そういう怖さみたいなものまで、一種の軽みをもっているような印象を受けました。何か自由な、軽やかさというもの。それは、フランス映画が伝統的に持っているものかもしれません。ですから、当時、これからフランス映画を勉強しなければと思った、そのきっかけがコクトーとの出会いだったのです。
そのころのフランス映画といいますと、ジャン・ルノワール、ジャック・フェデー、マルセル・カルネ、ルネ・クレール、ジュリアン・デュヴィヴィエなど、彼らの素晴らしい作品を溯ってみたりしながら、同時に、『鉄路の闘い』(1946)のルネ・クレマンが出てきます。(クレマンは『美女と野獣』の助監督をつとめています。)こうしたフランスの作家にひじょうに惹かれた時期があったわけです。
またその一方で、アメリカ映画の面白さというものもだんだんわかるようになってきます。ヨーロッパの伝統的な文化とは違う、アメリカという新しい国の文化に心を惹かれるようになった。私がまだ学生で、札幌にいたころのことですが。
(ビデオ発売 CICビクター・ビデオ)
『勝手にしやがれ』 A BOUT DE SOUFFLE(146号)
監督 ジャン=リュック・ゴダール
主演 ジャン=ポール・ベルモンド、ジーン・セバーグ、ダニエル・ブーランジェ
製作 レ・フィルム・ジョルジュ・ド・ボールガール、90分、1959年
【物語】
自動車泥棒の常習犯ミシェル(ジャン=ポール・ベルモンド)はマルセイユからパリに向かう途中、追って来た白バイの警官を射殺してしまう。パリに着き、アメリカの留学生パトリシア(ジーン・セバーグ)と再会、ベッドを共にする。当てにしていた金が手に入らず、警察の指名手配を受けたミシェルだが、ジャーナリスト志望のパトリシアのもとを離れることができない。金ができたら一緒にイタリアへ行こうと誘うミシェル。が、パトリシアは衝動的に警察に密告してしまう。警官に撃たれたミシェルは「まったく最低だ」といいながら、自らの手で瞼をとじて死んでゆく。
【解説】
以前、『大人は判ってくれない』の回でもお話しましたが、フランソワ・トリュフォー『大人は判ってくれない』、クロード・シャブロール『いとこ同志』、そしてこのゴダール『勝手にしやがれ』の三本は同じ19五九年につくられ、ヌーヴェル・ヴァーグの出発点となった作品です。このなかで私が最初にみたのは『いとこ同志』でしたが、これは一種のニヒリズムといってよいでしょう。 『いとこ同志』についてちょっと説明しますと、田舎出の純情な勉強家が試験に落ち、女にも振られて、最後はロシアン・ルーレットで死んでしまう。それに対し、パリのいとこが、遊んでばかりいたのに試験にも合格する。つまり、ついてない人間はとことんついてないという考え方で、どこかで救われるというのは幻影にすぎないという主張をもった映画でした。
右の三人の映画監督のなかでいちばんオーソドックスだったのがトリフォーです。前にお話したとおり、映画のつくり方をよく知っているように思いました。ところが、ゴダールとなるとまったくの型破りで、彼はほとんど映画を知らないでつくったのではないか。その無手勝流のよさが生き、ひじょうに独創的な世界がつくられたのです。
つまり『勝手にしやがれ』では、映画の文法といいますか、映画の基本みたいなものにとらわれない描写が随所にありました。そのことがかえって新鮮で、ジャン=ポール・ベルモンドの演じる主人公が躍動しているというか、自由に呼吸をしている感じが出ていたように思います。それは、たとえば最後の場面です。ベルモンドが撃たれて死ぬときに、タバコを吸っていて、さらに自分の手でまぶたを下げるという、なんともマンガ的な描写です。ですから、この映画によって教えられたことは、まず映画は約束事によって縛られる必要はないということ。私は、それこそ目からウロコが落ちるとはこういう感じかと思った。
他にもいくつか例をあげますと、登場人物がカメラに向かって、つまり観客に向かって語りかける。ふつうは、映画は芝居と違うのだから、登場人物は観客に向かって話してはいけないとされていた。そういう約束を平気で破ったわけです。そんなものはどうでもいいよ、というのがゴダールの映画でした。あるいは、ベルモンドとジーン・セバーグのベッド・シーンで、二人が白いシーツのなかにもぐり込んでいるところが、画面がつながっていかない。ポンポン飛んでしまう。昔の描写技法からすれば、アクションとしてつながらなければいけないんですが、そういうことをまったく無視する。ただ、二人の会話が一貫していることで、飛び飛びの画面でも映画が流れていくわけです。
また、ヌーヴェル・ヴァーグの手法といいますと、手持ちカメラが有名です。これもそれまでの映画では、画面が揺れてはいけないという常識があった。画面は水平にきちんと安定していなければいけない。画面が傾くとすれば、ヒッチコックのサイコ・スリラーで不安感を表現したように、それなりの意味がなければいけなかったわけです。画面が斜めになったりするのは下手だといわれていたのを、『勝手にしやがれ』(撮影、ラウール・クタール)はまったく無視して、十六ミリ手持ちカメラで撮った。
ゴダールは画面が揺れ、構図も不安定になることを平気でやってのけ、それがその後の新しい映画文法の基本になったといえます。『勝手にしやがれ』の翌年の作品『太陽がいっぱい』(この監督ルネ・クレマンはむしろヌーヴェル・ヴァーグの作家たちから批判された人ですが)でも、ヌーヴェル・ヴァーグ作品を手がけたカメラマンのアンリ・ドカエが手持ちカメラを使っています。とりわけ魚市場の場面で、カメラがずっとアラン・ドロンを追って行く描写が有名です。
日本でも、大島渚監督の『青春残酷物語』(1960)で、川又昂さんが手持ちカメラを使っている。だから逆に、今の若い人たちは『勝手にしやがれ』をみても、ちっとも驚かない。今は、あまりに一般的な表現方法になってしまったということです。だから、私たちが『勝手にしやがれ』から受けた衝撃が、若い人には伝わらないわけです。
『勝手にしやがれ』の衝撃ということでは、主人公ベルモンドの存在が大きいと思います。いとも簡単に人を殺したり、ものを取ったり。つまり、ある種の感情から行動するのはフィクションにおける人物のふつうのあり方でしょうが、そういう感情の部分が、今風にいうと、消去されている。それはたぶん、先祖はアメリカのハードボイルド小説につながっていくのかもしれません。
しかし、ハードボイルドの場合、一種、行動の規範というか、モラルみたいなものが必ず伴うのに対し、ゴダールの場合はそれまで無視しています。そこがゴダールの新しいところなので、やはりそうすると、ニヒリズムかアナーキズムということになるでしょう。その後のゴダールの作品をみていくと、毛沢東の思想に共鳴したり、いろんな揺れはありますけれど、基本的な思想は反体制、すべての権威の否定ということだろうと私は思っています。
ただ、ゴダールはひじょうな勉強家ですから、作品のなかで引用がたくさん出てきます。映像だけではいい足りないと思うのか、言葉があふれてくる。とくに最近のゴダール作品では、一回みただけではとらえきれないところがあります。言葉と映像が重なって、全部はキャッチできない。あふれ出てくる感じです。あれも面白いところで、映画だから映像中心でなければという考え方もゴダールはもっていないわけです。年をとらないというか、常に変わっていくような感じが、ゴダールにはあります。
それから、ゴダールの作品をずっとみてきて思うのは、映像がきれいだということです。何とはない映像がとてもきれいなので、たとえば青空にジェット機の白い雲がスーッと走っていく。ゴダールの映画によく出てくる場面と思いますが、そういう映像のもっている美というものを、ただ美としてとらえるのではなく、ある瞬間の詩的イメージのようにとらえているのではないか。すばらしい映像感覚をもった人と思います。
最後に、日本題名について。『勝手にしやがれ』というのは、よく感じを出していると思います。原題は「息が切れる、へたばる」といった意味ですから、この作品を輸入配給した会社(新外映)がつけたのだと思いますが、これは邦題として成功した例ではないでしょうか。
(ビデオ発売 パック・イン・ビデオ)
『明日に向かって撃て!』BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID(147号)
監督 ジョージ・ロイ・ヒル
主演 ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、キャサリン・ロス
製作 二○世紀フォックス、110分、1969年
【物語】
1890年代、仲間たちと家畜泥棒や銀行強盗を重ねていた無法者、ブッチ・キャシディ(ポール・ニューマン)とサンダンス・キッド(ロバート・レッドフォード)の二人は、列車を襲ったあと鉄道会社の追跡隊に追われ、サンダンスの恋人エッタ(キャサリン・ロス)の家にたどり着く。三人は荒稼ぎを目論んで南米ボリビアへ行くが、貧しい国であてがはずれ、エッタは帰国する。ブッチとサンダンスは護衛に雇われた鉱山で偶然大金を手に入れたものの、ある日、ボリビア警察と軍の追撃を受け、「今度はオーストラリアへ行こう」と、包囲した銃口の前に飛び出して行く。
【解説】
アメリカン・ニューシネマの先駆けになった作品といわれる『俺たちに明日はない』(1967)あたりからアメリカ映画がちょっと変わってきて、その代表作『イージー・ライダー』が1969年です。同じ年の『明日に向って撃て』も、ひじょうに新しいということはないのですが、やはりいろんなパターンからおして、ニューシネマ系列の映画かなという感じがあります。
まず主人公が犯罪者であり、アンチヒーローのような形で、ひたすら逃げるという構造。これは『俺たちに明日はない』と似ていますし、男二人の友情という点(キャサリン・ロスの演じる女性がからみますが、わりと淡彩)も、ニューシネマタッチです。レッドフォードという二枚目に髭をつけさせるのも、今までの正統的な映画の作り方とはちょっと違う。
西部劇で男同士の友情といえば、たとえば『荒野の決闘』(1946)のワイアット・アープとドク・ホリデーがあります。そのジョン・フォードの世界にくらべると、『明日に向って撃て』ではなんとなく心優しい男になっている。男っぽさの衰退といいますか、そういう流れがアメリカ映画にみられるように思うのですが、その転換点がアメリカン・ニューシネマだったのではないか。
監督のジョージ・ロイ・ヒルは『スティング』(1973)、『華麗なるヒコーキ野郎』(1975)という、新しい感覚の映画を撮る人です。男たちの友情というテーマが多く、どっちかというと、あまり美女が出てきませんし、少々ホモ的傾向があるのかなという感じがしないでもない。その一方で、映像化するのは難しいといわれた、ジョン・アービングの小説『ガープの世界』も巧みに映画化(1982)しています。ハリウッドでは個性的な感じのする監督であり、私の好きな監督の一人です。
主演のポール・ニューマンとロバート・レッドフォードの二人は後の『スティング』でも共演しますが、なかなかよい組み合せで、ポール・ニューマンはちょっと渋く抑えて、レッドフォードはまだ若かったこともあり、いかにも二枚目です。それに加えて、清純派タイプのキャサリン・ロスですから、うまく合っていた。だから、けっこう悪いことをしている三人組なのに、あまり悪人という感じがしない。
この映画でちょっと考えさせられたのは、西部で追い詰められてボリビアに行き、ボリビアで追い詰められると、最後の場面で「今度はオーストラリアへ行こう」という。つまり、アメリカ人はフロンティア・スピリットで、西へ西へと移動して行き、カリフォルニアまで来て太平洋にぶつかって行き止まりになった。そして現代になると、『真夜中のカーボーイ』(1969)では逆に西から東へ戻って行く、テキサスの田舎育ちの主人公(ジョン・ボイト)が一旗揚げようとニューヨークに出て行く。
そういうふうに変わってきたことも面白いのですが、アメリカ人のメンタリティの問題として、その一歩手前のところが『明日に向って撃て』に出ていたのではなかったか。私の知っているアメリカ人でも、一カ所に定住して、そこでしっかりした生活を築くという考え方よりも、どこかいい所があれば移りたいという考えが強い。この映画には、そういうアメリカ人の特性が出ていたように思うのです。
それから当時は文明開化の時代で、西部がだんだん開けていった。鉄道も敷かれ、また自転車のセールスマンも出てきます。そういう時代の推移を、この映画は的確にとらえていた。そして追跡隊を振り切れず、追われる者の落ち着かない感じというか、一種のサスペンスがありますし、その間に休止符のように、自転車に乗って遊ぶ主人公たちには、その心優しいところがよく出ています。
追跡隊に断崖絶壁まで追い詰められた場面では、崖から下の川へ飛び降りようというブッチに対し、サンダンスは嫌だと、「俺は泳げないんだ」と答える。二人のやりとりのユーモラスな感じもいいなと思いました。実際は血なまぐさい話ですし、西部劇というのはだいたい埃まみれのはずですが、自転車で遊ぶ場面に流れる「雨に濡れても」は、実にしゃれた感覚の主題曲でした(音楽のバート・バカラックはアカデミー作曲賞と主題歌賞を受賞)。
色彩も、パステルか水彩かという感じで、この映画に合っていたように思います。追跡隊が迫ってくるところでは、暗がりのなかに明かりが点のように、『アラビアのロレンス』ではないけれど、彼方から明かりが少しずつ大きくなって近づいてくる。そういう感覚は西部劇には珍しいものだったでしょう(撮影、コンラッド・ホール。アカデミー撮影賞受賞)。
そして、ラストの死ぬ場面です。幾重にも囲まれた銃口に向かって飛び出し、一斉射撃を受ける直前にストップモーションで終わる。射撃音だけが響きわたるという、ひじょうに印象的なラストシーンです。その後、最後にストップモーションを使う映画は数多くつくられますが、強く印象に残るのは『大人は判ってくれない』と『明日に向って撃て』の二本だけではないでしょうか。そういう意味で、この映画は、西部劇というもののイメージをちょっと変えたかなという感じがするわけです。
これは余談ですが、私が髭を生やしたのは19七一年の正月だったと思います。暮に風邪を引いて、年明けに、髭を伸ばしたまま映画関係の人たちの名刺交換会に出かけて行った。そうしたら、二○世紀フォックスの人が「レッドフォードの真似をしましたね」という。この映画の公開直後だったのです。先輩の映画評論家の方は、「君は髭を生やしてないと目立たないから、そのほうがいいよ」とおっしゃる。全体に評判は悪くなかったものですから、それから伸ばしたままになった。ですから、『明日に向って撃て』という題名を聞くと、そのことをふと思い出すことになります。
(ビデオ発売 CBS/フォックスビデオ)
『ティファニーで朝食を』 BREAKFAST AT TIFFANY'S(148号)
監督 ブレイク・エドワーズ
主演 オードリー・ヘップバーン、ジョージ・ペパード、パトリシア・ニール、ミツキー・ルーニー、バディ・イプセン
製作 パラマウント、115分、1961年
【物語】
ニューヨークのアパートへ越してきた作家志望の青年ポール(ジョージ・ペパード)は、下の階で猫と気ままな暮しを楽しむホリー(オードリー・へップバーン)と知り合う。彼女は早朝、ティファニー宝石店の前でパンをかじるのが好きで、週一回シンシン刑務所に服役中のマフィアのボスに面会したり、ハリウッドのプロデューサーなどいかがわしい連中が訪ねて来たりと正体不明の女性だが、そんな彼女にポールは惹かれる。ブラジルの富豪と結婚寸前に麻薬密輸の嫌疑で逮捕され、しかしすぐに保釈されたホリーはポールのひたむきな愛に気づき、彼の求婚を受け入れる。
【解説】
『ティファニーで朝食を』はトルーマン・カポーティの短篇小説が原作ですが、ブレイク・エドワーズ監督はしゃれた風俗映画に仕立てています。『ピンクの豹』(1963)をはじめコメディが得意な監督で、ハリウッドを舞台にしても、ニューヨークを舞台にしても、いかにも都会的という感じの映画をつくる監督です。都会のいいところというか、なぜ人々は都会に魅了されるかという部分をうまく取り上げて映画をつくっている、そんな印象を受けます。
都会的でしゃれた感じをよりつよめているのがヘンリー・マンシー二の音楽でしょう。主題歌「ムーン・リヴァー」は映画を離れてもヒットしましたし、マンシー二はこの映画でアカデミーの作曲賞と主題歌賞を受賞しました。ブレイク・エドワーズとヘンリー・マンシー二のコンビでは翌62年の『酒とバラの日々』でも、アカデミー主題歌賞をとっています。
田舎から出てきた得体の知れないヒロイン、ヘップバーンが演じるこの女性は実はあまりきれいなキャラクターではなくて、夜の世界の危ない渡世をしている。朝帰りに、ニューヨーク五番街の宝石店ティファニーの前でフランスパンをかじったりするわけです。毎週木曜日、刑務所へ行ってマフィアのボスに会い、その連絡係のようなことをして百ドルの報酬を得ている。テキサスから初老の獣医(バディ・イプセン)が訪ねて来れば、彼はホリーの夫だということもわかる。彼女は十四歳で結婚し、すぐに家出をしてしまったというのです。
一方、若い作家にも、パトリシア・ニール演じるパトロネスがついていて、要するに彼はヒモで、富豪の人妻に養ってもらっているのです。というように、あまり誰も指摘しないことかもしれませんが、この映画にはあちこちに毒が仕込まれていて、わかる人にはチラチラとわかるような、暗い部分がずいぶんあります。ところが、全体を通してみると、そういう一種、危ういところはあからさまに出さない。きれいにすり抜けている感じです。
そうした暗い部分に深入りすると、全体のバランスが崩れて、都会を舞台にしたロマンティックなラヴストーリーには合わなくなるということを、つくるほうは賢明にも知っていたのでしょう。毒気のない風俗映画になっています。あからさまと感じるのは、ミッキー・ルーニ-が演じた日本人の写真家の役で、度の強い眼鏡をかけ、出っ歯という、既成の日本人イメージでしょうが、それをみるわれわれとしてはちょっとつらいところです。
そしてヒロインです。いったいこの女は何者なのか、そのわかりにくさというのはオードリー・ヘップバーンが演じているから余計わからないのではないか。ニューヨーク五番街のティファニーの前に、こういう女が立っていたら、やはりさまになります。きれいすぎる感じはありますが、まあ、そういう嘘もいいかと許せる。なぜ許せるかというと、ヘップバーンだからということになるのではないでしょうか。
へップバーンについてお話しますと、以前取り上げた『ローマの休日』(1953)が主演作としては初めての作品で、いきなりアカデミー主演女優賞を受賞した。そのあと、『麗しのサブリナ』(1954)、『昼下りの情事』(1957)、『シャレード』(1963)、『マイ・フェア・レディ』(1964)、『いつも二人で』(1967)など、わりとしゃれた映画に出て、『ティファニーで朝食を』でも、都会に暮す謎の女性の役をうまくこなしています。といいますか、彼女が演じたから抵抗なく受け入れられたのでしょう。
当時、アメリカの女優ではへップバーンと対照的な存在として、マリリン・モンローがいました。グラマーでセクシーでという、それがアメリカの女優の条件だったのですが、ヘップバーンは肉体にものをいわせるのではなく、ファッション・モデルのように細い体で、全体の雰囲気で魅力を感じさせた。日本ではむしろそういう女優のほうが好まれるので、ヘップバーンはアメリカより日本で人気が高かったのです。
私の持論ですが、コメディのうまい女優は頭がいいという考えをもっています。逆にいうと、頭のいい人でないと、コメディはできない。というのは、演じている役柄を客観視できるということ、演じている自分と、それをみている自分のバランスがうまく取れたときに笑いとかユーモアが生まれてくる。そう思うのです。オードリー・ヘップバーンはそれができる女優だった。できないふりをしてうまくやったのがマリリン・モンローです。二人とも、頭のいい女優だったと私は思います。
それにオードリー・へップバーンには一種の品のよさがありました。それはスターとして、ひとつの大きな宝物だったような気がします。役者ずれしていないというか、初々しさのようなものをずっと持っていて、それがファンにアピールしたのではないか。変なたとえですが、隣にマリリン・モンローが座ったらどうでしょう。落ち着かないのではないでしょうか。オードリー・へップバーンだったらどうか。気持ちよくお付き合いできそうな気がします。もちろん、比喩的にいえばの話で、実際にそうなったら、なかなかそうはいかないでしょうが。
(ビデオ発売 CICビクタービデオ)
『お熱いのがお好き』 SOME LIKE IT HOT(149号)
監督 ビリー・ワイルダー
主演 マリリン・モンロー、トニー・カーティス、ジャック・レモン、ジョー・E・ブラウン
製作 アシュトン・プロ、1959年、122分
【物語】
1929年、禁酒法下のシカゴ。サックス奏者のジョー(トニー・カーティス)とベース奏者のジェリー(ジャック・レモン)はギャングのボス(ジョージ・ラフト)が裏切り者を射殺する場面を目撃してしまう。二人はギャングの追手をかわし、女装して女性ばかりの楽団にもぐりこみマイアミへ逃げる。ジョーは楽団の歌手シュガー(マリリン・モンロー)に一目ぼれ、一方ジェリーは富豪のオズグッド三世(ジョー・E・ブラウン)に求婚される事態に。そこへシカゴのボスもやって来て……ドタバタの末、ジョーとシュガー、ジェリーとオズグッド、二組のカップルができるが。
【解説】
この映画は一種の「ギャングもの」のパロディといいますか、シカゴ・ギャングの抗争、有名な聖ヴァレンタイン・デイの虐殺を下敷きにしたようなところがあって、その殺しの現場を目撃したミュージシャンのトニー・カーティスとジャック・レモンがギャングに追われて逃げる。それで、むりやり女性だけのバンドに入り、ということは二人が女装して、列車に乗ったりマイアミの海で泳いだり、という倒錯したコメディになっています。
このバンドの歌手がマリリン・モンローですが、いろんな女性が出てくるなかで、モンローだけがおっとりしているというか、周囲はドタバタしているのに、一人だけのんびりしている、その感じがとてもよかったと思います。それからマイアミの大富豪に扮したジョー・E・ブラウン、この人は「大口ブラウン」と呼ばれた有名なコメディアンですが、女装のジャック・レモンに惚れて結婚を申し込む。その間に、モンローとトニー・カーティスの恋が進行してゆく。
そして最後の場面で、大富豪のプロポーズに女装のジャック・レモンが、子供が産めないとか何とか、いろいろ理由をあげて断るのに対し、大富豪はまったく動じない。ついにレモンが「俺は男だ」と告白してもケロッとして、Nobody is perfect. (完全な人間はいない)という有名なせりふを吐く。このせりふが、この映画の落ちになっています。
ビリー・ワイルダー監督はもともとオーストリアの裕福なユダヤ人の家庭に育ち、ベルリンへ出て映画の脚本家になります。ところが、時あたかもナチスの台頭で、彼はやむなくアメリカへ亡命し、ドイツ出身の監督エルンスト・ルビッチのもとで脚本を書くようになった。そんなこともあって、ワイルダーはルビッチ流の艶笑喜劇、男と女の惚れたはれたという話をユーモラスに巧みに語るという点で、ハリウッドでもナンバーワンといってよいのではないかと思います。それに話の転換がうまい、話術のうまい監督です。語り口のうまさにおいても、アメリカ映画随一といっていいのではないでしょうか。
一方には、アルフレッド・ヒッチコックというスリラーの話芸の天才がいますが、ビリー・ワイルダーも人間関係の倒錯したドラマとか、一種頽廃的な気分というものをよく知っていて、うまく描いた。たとえば、ウィリアム・ホールデンとグロリア・スワンソンが出た『サンセット大通り』(1950)では、冒頭にプールに浮んだウィリアム・ホールデンの死体が出てきて、その死んだ人物が全編のナレーションをするという、ちょっと意表をついた展開でハリウッドの内幕を描いた人間ドラマが語られる。
そういう彼の語り口というのは、何か落語の話術に似ているような気がしてなりません。内容よりも語り口でみせるとか、キャラクターの面白さでみせる。また、『アパートの鍵貸します』(1950)など、人情噺的な展開と読めないこともない。そういうところが、日本の話芸の世界と通じるように思うのです。
男女が転倒した姿といえば、アメリカ映画では『トッツィー』(1982)のような作品があります。しかし、これはウーマンリブの主張からか、一種アメリカ流の野暮ったさがあるのに対し、ワイルダーの世界はもっと柔らかい、艶があり、大人の世界を感じさせるものです。逆にいえば、要するにアメリカ映画の特徴は子供っぽいということなので、それはごく最近のクリント・イーストウッド監督『スペースカウボーイ』(2000)をみても、宇宙へ出かけて行く老人たちが、若々しい心意気みたいなものを持ちつづけているという話です。年を取っても、ちっとも人間が丸くならない。
そういう、純真で単純であるところにアメリカ映画の特色がある。それは子供っぽいということでもあると思うんですが、ビリー・ワイルダーはまったく違った、洗練された大人の世界を描いた。それは、たぶん彼が生まれ育ったヨーロッパの伝統に裏うちされているに違いない。そういうところが、ハリウッドでは貴重な存在だったと思うのです。
最近、『あの頃ペニー・レインと』の新進監督キャメロン・クロウが三年前、九十二歳のビリー・ワイルダーに長時間のインタヴューを行った、その本の翻訳がキネマ旬報から出版されました。邦題『ワイルダーならどうする?』というものですが、ワイルダーの言葉遣いなどなるべく生かすようにまとめられていて、おもしろく読みました。
(ビデオ発売 ワーナー・ホーム・ビデオ)
監督 ヴィットリオ・デ・シーカ
主演 ソフィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤンニ、リュドミラ・サヴェーリエヴァ
製作 カルロ・ポンティ・プロ、1970年、107分
【物語】
第二次大戦中にアントニオ(マルチェロ・マストロヤンニ)と結婚したジョヴァンナ(ソフィア・ローレン)は、ロシア戦線へ出征した夫の帰りを何年も待ち続けた。ある日、復員兵から、アントニオを瀕死のまま置き去りにしたと聞いた彼女は、意を決してソ連へと旅立つ。探し歩いた末に彼女が見つけたのは、ロシア女性マーシャ(リュドミラ・サヴェーリエヴァ)と平和な家庭を営むアントニオの姿だった。彼は戦争中マーシャに助けられ、そのまま結婚したのだ。ジョヴァンナは逃げるようにミラノへ戻る。数か月後アントニオはジョヴァンナを訪ねてイタリアへ来るが……
【解説】
ヴィットリオ・デ・シーカの作品では前に『自転車泥棒』(148)を取り上げました。これはイタリアン・リアリズム(ネオレアリスモ)の代表作といわれるもので、デ・シーカは前作の『靴みがき』(1946)その他で、戦後混乱期のイタリアをリアリスティックに描いた。そして、『ウンベルトD』(1952)、『屋根』(1956)になると、リアリズムが精神性や象徴性を色濃く漂わせる。ところが、そこから彼は人情劇を手がけるようになります。あるいは人情劇のほうが、彼にとってより居心地のいい世界だったのかもしれません。
そこが、たとえばロベルト・ロッセリーニと違うところです。ロッセリーニはそうした作家性みたいなものによって失敗したり、自ら破滅していく。デ・シーカはそのへんが、世の中のことをよく心得ていたということでしょうか。彼はもともと、二枚目スターとして出発したので、戦後、監督をするようになってからも、俳優として何本かの映画に出ています。
さて『ひまわり』ですが、デ・シーカ監督、マルチェロ・マストロヤンニ、ソフィア・ローレン主演というトリオでイタリア人情劇をいくつか作っています。『昨日・今日・明日』(1963)とか『あゝ結婚』(1964)など、ソフィア・ローレンのグラマラスな魅力だけでなく、イタリア人気質のようなものを彼女に託して、うまく表現した作品です。そうした一連の作品の集大成が、『ひまわり』といえるのではないかと思っています。
第二次大戦下、召集によってロシア戦線へ出征した男とその妻の話です。初めはたいへんなコメディ調で、新婚なのにすぐ戦場に行かなくてはいけない、今のうちに思いきりセックスをしておこうと、精力をつけるために大きなオムレツをつくって食べるとか、そういった馬鹿馬鹿しいお笑いから始まる。出征を逃れるため狂気を装って精神病院に入るものの、それがバレて極寒のロシア戦線へ送られてしまいます。
しかし、男は戦争に行ったまま音沙汰がない。戦争が終わっても帰ってこない。そのへんからだんだん新派悲劇調になってきます。ソフィア・ローレンは意を決して、夫は絶対に死んでいないはずだと、ソ連へはるばる探しに出かける。外務省の人の案内でロシアの村々を歩き回る、そこで広大なひまわり畑が出てくるのですが、探して探して、やっと探し当てたときに、夫はかわいいロシア女性と、子供までもうけて一緒に暮らしていた。
彼女は愕然として、マストロヤンニと言葉も交わさないままイタリアへ帰ってしまう。それからしばらくして、ソ連当局の旅行許可も下り、マストロヤンニはローレンをたずねてイタリアへ戻ってきます。ところがそのときにはもう、彼女にも子供がいて、お互いに愛し合いながら別れざるをえなかった、戦争の悲劇です。後半からはソフィア・ローレンの演技、表情、メイキャップ、また演出もそうですが、ひじょうに悲劇的なものになっています。
ソフィア・ローレンという女優はコメディもうまいけれど、深い悲しみの表現にも長けています。同じデ・シーカ監督『ふたりの女』(1960)は戦争の悲惨さ残酷さを描いたものでしたが、ソフィア・ローレンはこの作品でアカデミー主演女優賞、カンヌ映画際の女優賞を受賞しています。そして『昨日・今日・明日』では、ヴァイタリティあふれるイタリア女性を演じた。いわゆるコスチューム・プレイ、古代史劇から貴族の役、またナポリが似合う庶民の役まで、イタリア女性の代表といってよいようなスケールの大きな女優です。そのソフィア・ローレンの代表作が『ひまわり』といえるのではないでしょうか。
(ビデオ発売 CICビクタービデオ)
監督 浦山桐郎
主演 吉永小百合、浜田光夫、東野英治郎、加藤武、市川好郎、杉山徳子、菅井きん
製作 日活、1962年、100分
【物語】
埼玉県川口市は零細な鋳物工場が多く、その屋根には「キューポラ」と呼ばれる溶鉱炉の煙突が林立していた。そんな町工場に勤める昔気質の職工(東野英治郎)がクビになってしまう。妻(杉山徳子)は四人目の子供を産んだばかり、中学生の娘ジュン(吉永小百合)は高校受験を控えているが、父の失業で進学を断念せざるをえない。長男タカユキ(市川好郎)は十二歳、ガキ大将で、在日朝鮮人のサンキチ(森坂秀樹)を子分に遊び回っている。サンキチが北朝鮮への帰国運動で日本を離れることになり……貧しさに負けず力づよく生きる姉弟の姿を中心に庶民の哀歓を描く。
【解説】
浦山さんは松竹の助監督試験に三番でパスしたものの、面接で不合格にされてしまいます。公式には「身体検査で落ちた」とされているようですが、浦山さんの印象が暗かったため、あれは左翼ではないかとか、あの顔色は結核なのではないか、といろいろ言われたという伝説があります。この試験に一番で合格したのが大島渚、六、七番目に山田洋次がいたという。そして、このとき試験にあたった鈴木清順助監督が間もなく日活へ移籍し、その縁で浦山さんも日活へ入社することになります。
実際、浦山さんは小柄で酒好きの暗い感じの人ではありましたが、音楽はクラシック、モーツァルトがお好きだという、ひじょうに好みのはっきりした人でした。いつか一緒に飲んだときのこと(といって私は飲めないんですが)、同席した人が当時はやっていたモダンジャズを推奨したら、浦山さんは「あんなの駄目だ、音楽はクラシックしかない」と。彼の映画づくりも、ケレンがないというか、正統的なものだったといえるでしょう。
日活では川島雄三監督(『洲崎パラダイス赤信号』19五六、『幕末太陽伝』1957、『貸間あり』1959、『雁の寺』1962)の助手をつとめ、川島監督のチーフ助監督・今村昌平(『にっぽん昆虫記』1963、『楢山節考』1983、『黒い雨』1989、『うなぎ』1997)が監督に昇進すると、浦山さんは今村監督のチーフ助監督をつとめることになった。ですから浦山さんの監督第一作『キューポラのある街』でも、脚本は今村さんと浦山さんが共同で執筆にあたっています。
この映画は、昔ながらの鋳物の街に構造的な変革が起こってきて、それに対応できない労働者階級の生き方というものにきっちりと焦点をあてた。町工場が企業に買収され、昔気質の職人は切り捨てられてゆく。そういうなかで貧しさや差別にめげず、元気に生きていこうとする子供たちをうまく描いています。
ユーモアもあり、私の好きな場面ですが、在日朝鮮人の人々が北朝鮮へ帰国するというので友人、知人に見送られて帰還船の出る新潟へ出発する。ところが、主人公の友人サンキチ少年は日本に残る母親が恋しくなって、途中下車して川口へ帰ってきてしまう。みんなの見送りをうけた手前、恥ずかしいからアルバイトの新聞配達をするにも、顔を見られないよう風呂敷で覆面をするという、そういうユーモアが楽しい。今みても、いい映画だなと思います。
そして『キューポラのある街』はその年の日本映画監督協会新人賞に浴し、キネマ旬報ベストテンの第二位に選ばれる。処女作にして代表作をものにしてしまったわけで、以後、いい加減なものはつくれなくなったということもあるかもしれません、日本の映画監督としてはきわめて寡作です。企画を選び、すすめてゆく上で妥協しなかった。自分が納得できる作品しか手がけなかった、ということでしょう。そういう点では、浦山さんにはもっと摂生して、長生きしてもらいたかったという気がします。
だいぶ前ですが、NHK教育テレビで浦山さんの映画について何回か話をしたことがあります。『キューポラのある街』を取り上げたときには、吉永小百合さんも出演してくれて、いろいろ話をしました。浦山さんというのは、私生活では飲んべえでも、仕事に関してはやはりひじょうに厳しい人だったようです。それに吉永さんをはじめ、『非行少女』(1963)の和泉雅子、『私が棄てた女』(1969)の浅丘ルリ子、小林トシエ、『青春の門』(1975)の大竹しのぶ、『暗室』(1983)の芦川よしみというように、浦山さんは女優をしごき育てるのがうまかった。
その一方で、私生活ではずいぶん無茶苦茶な飲み方をしていたらしい。浦山さんは『暗室』を撮ったあと、モスクワ映画祭で審査員をつとめましたが、このときは私もモスクワへ行き一緒になりました。審査期間の一週間ぐらいは酒を絶って頑張ったものの、それが終ったら安心してあびるように飲んだといいます。最後の作品は吉永さん主演の『夢千代日記』で、この映画が公開された1985年、浦山さんは五十四歳で亡くなっています。
考えてみると、あの時代の日活は、一方で石原裕次郎や小林旭、赤木圭一郎といったスターによる商業路線の映画、いわゆるプログラムピクチャーを大量につくりながら、他方、浦山さんや今村さんのような芸術性の高い作品をつくっていたわけで、それは日活映画全体のエネルギーになっていたように思います。この時期、田坂具隆監督(『路傍の石』1938、『土と兵隊』1939、『ちいさこべ』1962、『五番町夕霧楼』1963)は日活で裕次郎を使い、『乳母車』(1956)や『陽のあたる坂道』(1958)といった秀作を撮っています。
先に名前をあげた鈴木清順監督(『野獣の青春』1963、『肉体の門』1964、『けんかえれじい』1966、『ツィゴイネルワイゼン』1980)も、はじめはプログラムピクチャーを量産していたのが、だんだん作家性の強い作品をつくるようになった。その様式美や独特のタッチで鈴木作品が注目されるようになります。ところが、『殺しの烙印』(1967)を撮ったところで、商業路線に固執した当時の日活の社長と喧嘩になり、日活をクビになってしまう。
鈴木清順監督には何度かインタビューしたことがあります。鈴木さんは、「私はNGのない監督です」という。撮ったとおりにつなぐと映画になる。無駄なことはしないと自慢していました。映画づくりの職人として、いかにたたき上げてきたかという、そんな自信もお持ちなのでしょう。
(ビデオ発売 日活)
監督 今村昌平
主演 左幸子、吉村実子、北村和夫、北林谷栄、
長門裕之、春川ますみ
製作 日活、1963年、123分
【物語】
昭和17年、製糸工場の女工とめ(左幸子)は父親(北村和夫)が危篤との知らせで山形の実家へ帰る。実は地主の家への足入れ婚のため呼び戻されたのだ。その相手との間に子供ができるが、女中にも彼の子がいたことで、とめは再び製糸工場へ。終戦を迎え、係長の松波(長門裕之)の愛人となったとめは、彼の感化で組合活動に精をだす。しかし松波が課長代理になると、とめは捨てられ会社もクビに。東京へ出たとめは米兵のオンリー(春川ますみ)のメイドや旅館の女中兼売春婦となり、やがてコールガール組織のマダムに……激動の時代をたくましく生きた女の一代記。
【解説】
『にっぽん昆虫記』は私の好きな映画で、今村作品としてはカンヌ映画祭でグランプリを取った『楢山節考』(1983)とか『うなぎ』(1997)より、この作品や前作の『豚と軍艦』(1960)のほうがよかったと思います。人間の欲望、生命力といったものをエネルギッシュに描く、そのひとつの完成したかたちが『にっぽん昆虫記』であり、そこから突き抜けた作品が次作の『赤い殺意』(1964)だった。そして今村世界の集大成が、『神々の深き欲望』(1968)といえるのではないかと私は思っています。
今村さんははじめ松竹に入社し、小津安二郎監督(『晩春』1949、『麦秋』1951、『東京物語』1953、『秋刀魚の味』1962)に助監督としてつきますが、小津さんの映画のつくり方には反感をおぼえたといいます。まあ、今でこそ小津さんの評価は高いものの、当時の若手監督、助監督はみんな小津さんを批判的にみていたようです。
そして今村さんは日活に移り、監督第一作が『盗まれた欲情』、それから『果しなき欲望』(ともに1958)というように、「欲望」という中心モチーフでヴァイタリティーあふれる映画をつくった。この二作の間に『西銀座駅前』というプログラムピクチャーを今村さんは撮っています。地下鉄丸ノ内線の西銀座駅ができたことを記念してつくられた、フランク永井の歌謡曲「西銀座駅前」がヒットし、そこから企画された映画でした。
今村さんの真価が発揮されるのは『豚と軍艦』あたりからと思いますが、その作品には、自分の欲得だけで生きているような人間が多く出てきます。むしろ悪いやつが出てきて、いい加減に、勝手に行動することが意外と社会の問題の核心に触れてしまう、というところがある。『にっぽん昆虫記』でも女の主人公(左幸子)が、そのヴァイタリティーによって世の中を動かしてしまう、そういうとらえ方を今村さんはしていたのではないか。
それは今村さんが脚本を書いた川島雄三監督『幕末太陽伝』(1957)に、すでにその萌芽はあったと思います。他人のこと、世の中のことはなにも考えない、自分のことだけやってる人間、それが絡み合って時代をつくっていく。あるいは時代の病巣みたいなものを暴いていく、という仕組みになっている。そうしたつくり方はずっと後年の『うなぎ』でも変わっていないような気がするのです。
かつて『にっぽん昆虫記』について書いたことですが、自分の映画のなかの人物を今村監督はまるで虫を観察するようにみています。「昆虫記」とはまさに題名そのもので、そこに登場する人物たちを物珍しそうに、好奇心をもって観察している。そうすることによって、人間のいろんな虚飾を取り払うだけでなく、裸の生き物としての人間といったものがみえてくる、というとらえ方をしているように思います。
それは人間を大所高所から見下ろすというのではなく、微視的にずっと観察している。人間を馬鹿にしていないというか、ひじょうにおもしろがって観察しているところが今村さんの特色です。そして、そういう生き物が突然ものすごい存在になったりする。『赤い殺意』がそうです。犯された女がだんだん強い女に成長していく。そのことによってかえってエネルギーを、生活力とか生命力をもってしまう。それは『豚と軍艦』についても、処女作の『盗まれた欲情』についてもいえるでしょう。
そして、『にっぽん昆虫記』では主演の左幸子の演技が印象に残ります。左さんは先日、惜しくも亡くなりましたが、今村流の「上昇していく女」といいますか、なにもないところから出発して、自らの根性と才覚でひとかどの人間にのしあがっていく女を熱演した。それはまさに昆虫があらゆる困難に打ち勝って生き延びていくような感じで、したたかに生きていく。そういう今村さんの描き方ですが、左さんはその役柄をひじょうにうまく演じていたと思います。
(ビデオ発売 日活)
監督 ロバート・アルトマン
主演 アンディ・マクダウェル、ブルース・デイヴィソン、ジュリアン・ムーア、マシュー・モディーン、アン・アーチャー、マデリーン・ストウ、ティム・ロビンス、ジェニファー・ジェイソン・リー、クリス・ペン、リリー・テイラー、ロバート・ダウニー・ジュニア、リリー・トムリン、フランシス・マクドーマント、ピーター・ギャラガー、アニー・ロス、ロリー・シンガー、ジャック・レモン
製作 ショート・カッツ・プロダクションズ、1993年、188分
【物語】
ロサンゼルスの上空、殺虫剤を散布するヘリコプターが飛んでいる。それを報道するTVキャスター夫妻(ブルース・デイヴィソン、アンディ・マクダウェル)の子供が九歳の誕生日を迎える前日、車にはねられ意識不明に陥ってしまう。隣の家ではジャズシンガーの母(アニー・ロス)とチェリストの娘(ロリー・シンガー)が互いに芸術家としての葛藤のようなもので悩んでいる。この二つの家から依頼されたプール掃除屋(クリス・ペン)は妻(ジェニファー・ジェイソン・リー)がテレフォン・セックスを仕事にしていることを快く思っていない。ヘリコプターの操縦士(ピーター・ギャラガー)の別れた妻(フランシス・マクドーマント)は警官(ティム・ロビンス)と不倫の仲、警官の妻(マデリーン・ストウ)は画家である姉(ジュリアン・ムーア)のヌード・モデルになり……九組の男女と四人の男が織りなす人生模様。
【解説】
ロバート・アルトマンは『M★A★S★H』(1970)で一躍注目された監督です。これは面白い映画で、朝鮮戦争のときの移動野戦外科病院(この略語がMASHです)が舞台、そこへ三人の軍医(ドナルド・サザーランド、エリオット・グールド、トム・スケリット)が着任して騒動をひきおこすという話。
堅物の少佐(ロバート・デュバル)と新任の女性将校(サリー・ケラーマン)の仲をとりもち、そのベッド・シーンの会話を隠しマイクで全スピーカーに流してしまったり、女性将校の陰毛は何色かという賭けをして、野戦病院ですからシャワーはテントのなか、あらかじめ仕組んでおいて、彼女がシャワーを浴びているときにサッとテントを巻き上げる。そんなバカバカしいエピソードを重ねながら、いくつもの物語を交錯させ、多くの人物を登場させて、ブラック・ユーモアあふれる群像ドラマになっています。
アルトマンは映画的にも面白い試みをする人で、たとえば『ザ・プレイヤー』(1992)です。ハリウッドの内幕物といいますか、メジャー・スタジオの脚本担当重役(ティム・ロビンス)が主人公ですが、その冒頭の七分間、主人公についてカメラが全移動していきます。まったくカットを切らない。これはオーソン・ウェルズ『上海から来た女』(1948)からの引用といえるでしょう。
『ナッシュビル』(1975)では、テネシー州ナッシュビルはカントリー・ウェスタンのメッカで、その祭典の開かれる町、そこへ歌手になることを夢みる若者たちや、すでにプロとして名のある連中も集まってくるという群像ドラマ。やはりアメリカの現代生活の一面を生き生きと描いています。
総じてアルトマンは反体制の作家、反秩序の作家といわれます。正統的な文化よりも、いわゆるサブカルチャーに関心がつよく、エリートよりも、そうでない平凡な人間に愛着を感じる、そういうつくり方をする監督です。自らアウトサイダーになっているようなところがあって、反ハリウッドの大物監督とされてきました。彼の代表作は『ナッシュビル』と思っていたのですが、『ショート・カッツ』ができてみると、これはやはり彼の集大成といってよいのではないかと思うのです。それぐらい立派な作品と思っています。
『ショート・カッツ』は、地中海ミバエを抹殺するため、殺虫剤を散布するヘリコプターが飛び交うシーンから始まります。TVキャスターの子供が学校へ行く途中、車にはねられ、その場はなんともなく家に帰るものの、意識不明に陥りそのまま死んでしまう。このエピソードが縦軸になって、隣の家の音楽家母娘の話、子供をはねた中年のウエートレス(リリー・トムリン)とその娘夫婦(ロバート・ダウニー・ジュニア、リリー・テイラー)、そしてその友人のプールの掃除屋夫婦の話などなど、現代の市民の日常生活がアラベスクのように描かれていきます。
そのなかには、男友達三人で山の中へ泊まりがけの釣りに行く。すると川の淀みに全裸の若い女の死体が浮かんでいる。どうしようか、警察に知らせたほうがいいけれど、携帯電話もない。とりあえず死体が流れないように留めておいて、そのまま三日間釣りを楽しんでしまう。あるいはプール掃除人の奥さんはテレホン・セックスの相手をするのが仕事で、自分の赤ちゃんのおむつを替えたり、いつもの料理をしながら猥褻な会話を交わしている。
そして最後、その掃除人夫婦と友人夫婦がピクニックに出かけ、奥さん同士が子供たちの世話をやいている間、男二人は若い女の子をひっかけようと、二人づれを岩陰に連れて行ったものの、騒がれて掃除人は女の一人を殺してしまう。するとそのとき、ロサンゼルスが大地震にみまわれ、そのニュースがテレビに流れているところで終わりとなります。
本当に世も末というか、世紀末的といってもいいでしょう、終末観というものをもった監督であり、作品です。それもごく瑣末な日常生活のつみ重ねによって、現代の頽廃の極みみたいな状況を描く。現代の黙示録といってよいかもしれません。テーマは大きいし深いし、それを大げさにみせず、さりげなく描いているところが素晴らしいと思います。
ついでながら、アルトマンの映画はよく裸が出てきます。この作品でも、夫婦喧嘩の行きがかりからジュリアン・ムーアがドレスを引き裂くと、下は素っ裸。またTVキャスターの家のプールを掃除している掃除屋が隣のプールを覗くと、そこではチェリストが全裸で泳いでいるという、女優という仕事も大変だなと思っていつもみていますが、そうした描写も反秩序的、反体制的です。プロヴォカティヴといいますか、刺激的かつ論争を起こすような描写の多い監督といえます。
このアルトマンの影響からか、最近のアメリカ映画は群像ドラマが多いように思います。昨年のアカデミー作品賞を取った『トラフィック』(2000)も、三つの異なる場所、人物による物語が、麻薬を共通のテーマとして同時進行で描かれる。70年代のポルノ映画界の内幕を描いた『ブギーナイツ』(1997)、一部で評判になった『ハピネス』(1998)、トム・クルーズの出ていた『マグノリア』(1999)も群像ドラマでした。ひじょうにおもしろい傾向だと思っています。
(ビデオ発売 アミューズビデオ)