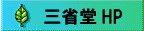◆苦境の中での「ぶっくれっと」創刊
(社史「三省堂の百年」から)
 会社更生がはたして成るのか、更生計画案承認までの二年間は不安の毎日であった。広告・宣伝量の多寡は出版社の士気に影響するところが大きい。しかし、更生計画案も承認されていない倒産会社としては、広告など思いもよらないことであった。いくつもあったPR誌はすべて廃止の状況であった。
会社更生がはたして成るのか、更生計画案承認までの二年間は不安の毎日であった。広告・宣伝量の多寡は出版社の士気に影響するところが大きい。しかし、更生計画案も承認されていない倒産会社としては、広告など思いもよらないことであった。いくつもあったPR誌はすべて廃止の状況であった。
そんな中で、三省堂はいち早く、五十年の九月には総合PR誌「ぶっくれっと」を創刊させている。新書判46~64ページ、年4回刊、書名は平仮名で、どこか三省堂の脱皮を象徴するような瀟洒な冊子だった。誌名は社内から公募し、出版部の北田明の案が当選した。賞品はバーボンのウイスキー一本であった。
 辞書づくりのむずかしさ
辞書づくりのむずかしさ
 <読者のページ> 暮らしの中で
<読者のページ> 暮らしの中で
 <三省堂出版小史> 地名辞典60年
<三省堂出版小史> 地名辞典60年
 三省堂だより
三省堂だより
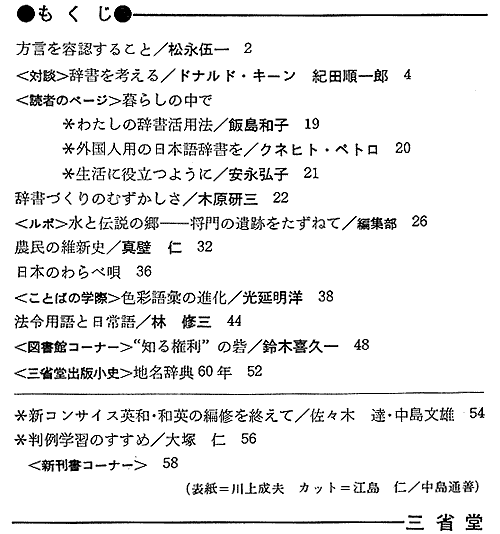
木原研三
学窓を出て間もないころ、恩師のお手伝いに辞書編集に参加させていただいてから約三十年の間、断続的とはいえ何らかの英語辞書の編集に関係してきた私であるが、かけだしのころに比べて辞書づくりのむずかしさが幾分なりとも減ったという実感はない。ただひたすらに誤り無きを期するだけで私などの乏しい精力は使い果たされてしまうというのが偽らざる状況である。私が関係してきたのは主として英和辞書で、以下述べることも英和辞書編集を通じての経験におのずから限定されることを前もってご了承いただきたい。
「親がめこけたら…」
国語学者が国語辞典を作る場合と違って我々が英和辞書を書く場合、自分がファーストハンドに知らない事柄について海外の辞書の語釈を頼りに筆を進めることが多い。実際、昭和の初期に英和辞書を書いた人たちはPODやCODをせっせと翻訳していたそうであるが、これらの辞書の定義や説明は、その語句が実際に使われている文脈なしにはnative speakerでない者にとってはしばしば難解であり、これが英和辞書における誤りの原因となるケースが少なくない。このような誤りを犯すのを避けるには、回り道のようであるが、独自に用例を集めてその文脈の中で当該語句の意味を判断するよりほかに方法はない。
このような地道な方法を取らずに安易な引写しをしたために英和辞書編集者の犯した誤りはまことに多い。一例を挙げれば、have two strikes against one という成句に「ツーストライク・ワンボールを取られる」という訳を与えている辞書がある。これなど He had two strikes against him というような用例さえ見ればこのような誤訳など起こるはずがないのである。
これとちょうど反対のケースが slip one over on という成句である。ウェブスター二版に既に出ている句であるが、戦後いち早く出た辞典が気をきかしたつもりでこれを slip a person over on と変えて出したため、以後この成句を載せた英和辞書は(手許に十五点ほどあるが)二点を除いてことごとく間違ってしまった。もちろんこの one は日本語で「一本取られる」という場合の「一」のようなもので、人称一般を指しているのではない。
まさに「親がめこけたら」の典型的なケースで、いったいこれらの辞書の編集者は何を見て書いているのだろうかと疑いたくなる。ところで右に挙げた例外の二点は「三省堂ホルト」と「小学館ランダムハウス」とで、両者とも特定の外国辞書の日本語版であることはいかにも意味深長ではないか。
もちろん、このような誤りは、執筆者に十分な学識があれば犯すことのないものであるが、神ならぬ身には思い違いということもある。そのような場合、よるべき用例の有無は決定的な重要性を持ってくる。
第一に用例の収集
およそ辞書づくりの第一歩が用例の収集であることは自明の事実であるが、英和辞書編集の場合、範とすべきモデルが既に多く存在するため、この基礎作業がとかくなおざりにされる。それどころではない。ある英和辞典の序文でその編者は最近出版された英米の辞書を幾つか挙げて、それらの業績を適宜摂取したなどとうそぶいているが、これなど正に辞書づくりの何たるかを解さぬ人の言であろう。
その適切な例文やシャープな語釈の故に私が日ごろ愛用している「新明解国語辞典」もその背後に100万に近い用例の収集があると聞く。もちろん私のささやかな収集はそれに比すべくもないが、それでもこの30年ほどの間に徐々に集まった用例によって、今回の「新コンサイス英和辞典」改訂になにがしかの寄与をすることができたのは幸いであった。
しかし欧米の一流の出版社の辞書編集部では平生から完備した用例収集を心がけているらしく、私が昨年訪英の際見学したオックスフォード大学出版部の OED New Supplement 編集部の用例収集も見事なものであった。
私がそれほど珍しいとは思われないある単語について、どうして New Supplement に入れなかったのかと、案内してくれる編集員の一人に訊ねると、彼はずらりと並んだ用例カード箱のわきに置かれた Rejected Cards の箱からその単語の用例カード数枚を引き出し、用例が少ししかないので入れなかったのだろうと立ち所に答える。やっぱり本場は違うものだと感心した次第である。
辞書づくり、特に小型辞書の編集での最大の難関はスペースの制限であろう。限られたスペースに最大量の有効な情報を盛りこまねばならぬ編集者は、さながら翼を切られて飛ぶことを強いられる鳥の思いである。あれこれとメキャニカルな手段でスペースを切りつめてもそれには限度がある。最後は有効性の少ないと思われる情報を省くほかないが、その判定がむずかしい。こんな単語はいらないと思っても、それはたまたま自分がその単語に出会ったことがないだけのことかもしれない。
このようなことを書きつらねればそれこそ際限がないのであるが、要するに辞書編集者のぐちだと言われればそれまでの話だ。むしろ沈黙して、でき上がった結果に語らせるにしかずである。
国語学者へのお願い
一つ、執筆中にしばしば感じたことであるが、国語学関係の方々にお願いがある。それは英和辞書を書いたことのある人ならだれでも経験したことと思われるが、英語の語句を前にして頭をひねっても、適切な訳語がなかなか思い浮かばないことがある。
このような時、もし英語なら Roget のThesaurus が助けてくれる。これは英語の全語彙を概念によって分類したもので、意味上類似した語句がまとめて並べてあり、索引によって該当するグループを探し当て、そこに羅列してある語句を見ていけば自分の求めているのにピッタリの語句が見つかるという仕組みになっている。英米人は主としてこれを作文に利用するので、初版出版後100年以上たった今日でも需要は衰えず、新しい改訂版が絶えず出版されているのである。ドイツ語ではもっと学術的な Dornseiff, Der Deutsche Wortschatz があり、フランス語では Dictionnaire analogique というような標題で類似の書が売り出されている。
私は訳語を考えながら、こういう辞書が日本語にあったらどれだけ労力が節減されることであろうか、またどれだけ良く洗練された訳語を得ることができただろうかと思わざるを得なかった。
なるほど我々にも国立国語研究所の「分類語彙表」や東京堂の「類語辞典」があるが、これらは今述べた目的にはほとんど役立たない。20回引いて満足な答が得られるのが1回ぐらいの効率では割に合わないので、ついにはどちらも敬遠してしまうことになった。現代の教養ある日本人の使う全語彙を網羅してそれを意味に従って分類した辞書、そういう辞書をぜひ作ってもらいたいものである。
「辞書の限界」ということ
最後に、やや主題から離れるが、辞書の限界ということについて一言したい。自分で辞書を書きながら辞書の限界について特に近ごろ痛感するからである。これは例えば happy に当たる日本語がないといった種類の個々の単語の意味範囲の問題とはいささか異る性質の問題である。
私の勤務する女子大のクラスで使っていた英文法の教科書に She is not the kind of girl to encourage lovers という文があった。クラスの学生だれに当てても「彼女は恋人を激励するタイプの女ではない」という訳しか出てこない。確かに辞書で encourage を引けば「激励する、鼓吹する、元気づける」といった訳語しか出ていないのである。
そこで、こんな恋の手管を教えるのは僕の月給の中には入っていないことなのだがと前置きして、異性から言い寄られた場合、女性はある程度好感を持っていても単に coyness からそっけない態度をとることがある―そう期待されていた時代もあった―が、それを続けると男性のほうが気落ち( lose heart )して女性から離れてしまう恐れがある。そこで女性のほうとしても適当に男性に「気を持たせる」ように振舞う必要があるわけで、それがつまり encourage することなのだ、決して末は総理大臣になれとか大学者になれと言って「激励する」ことを指しているのではない、と説明すると、学生一同あっけにとられたような顔をするのであった。
実際、辞書というものは言語事実の最大公約数的なものしか記載できないので、辞書と現実のテキストとの間には越え難いギャップがある。例文を提示し、語のニュアンスを説明し、類義語との異同を指摘するなど、辞書の側からこのギャップをいかに埋めようと努力しても、そのギャップを越えることはできない。
右の例で言えば encourage のあのようなコンテクストでの意味まで辞書は面倒見きれないのだ。結局コンテクスト、それを把握する読者の人生経験の広さと深さだけがこのギャップを越えさせるのである。辞書にある訳語で置きかえるだけで英語が日本語になるというのだったらこんなに楽なことはない。
辞書はこのギャップを飛び越えるための踏切り台であり、英語を学ぶ者は、辞書から学ぶべきものをすべて学んだ末に辞書を越えなければならない。そこに初めてテキストの完全な理解があるということを銘記すべきであろう。
(きはら けんぞう・お茶の水女子大学教授・「新コンサイス英和辞典」編集協力者)
*わたしの辞書活用法
飯島和子(翻訳家)
大学の英米科などというところに籍をおいていた時も、翻訳家のハシクレたらんとしている現在も、熱心に辞書を引くということをあまりしない。
したがって、使う辞書の数も多くはない。しかも、そのなかのいくつかに限定されてくる。どういうものが最も使用頻度が高いかといえば、英和辞典では、語法の説明があり、語義の分類や訳語が適当で、それぞれに合った用例が豊富に出ている本の、ということになるだろうか。そして、内容もさることながら、大きさや重さといった物理的条件も、使いやすさのけっこう重要なファクターになっているような気がする。
英英辞典では、 Webster's New World Dictionary あたりが、いつもかたわらに置くには手ごろな気がする。もっとも、私が翻訳するのは子供向けのものがほとんどなので、この中型の辞書はあまり使うことがない。むしろ使うのは、大型のもののほうである。辞書にあたるのは、少し詳しく調べたいと思うときであるし、それには、小型や中型のものではとてむものたりないからだ。大きい辞書にもやはり好みがあって、使うものはきまってくる。私の場合は、もっぱら、 Webster's Third New Internatinal Dictionary のお世話になっている。これに出ていないとなって、はじめて The Oxford English Dictionary (OED) などの他の辞書にあたってみる。
ところが、私の今までの経験では、Third New Internatinal Dictionary にないものは、たいてい他の辞書にもないのである。数年前、初めて翻訳の仕事をした時、二、三度そういうことが続いて、すっかりこの辞書のひいきになってしまったというわけだ。たまたま、いくつかの語についてそうだったというだけのことなのに、思えばたわいのない話だが、なんによらず、出会いというものはぞんなものではあるまいか。
ところで、目的の語や用法が辞書に載っていないときはどうするか。私の場合は、手近のものにあたって出ていなければ、これこそ一番てっとり早くて正確だとばかり、直接原作者に問い合わせるという方決をとってきている。でなければ、だれか適当な人にきいてみるよりしかたがない。特に固有名詞はやっかいで、例えば Biro (イギリスの子供などが使う安ボールペンの商標名)とか Gobstopper(同じくキャンディーの名)とか言われても、現地に生活している人にしか分かるまい。
しかし、考えてみれば、これはあまり感心できるやり方ではない。第一、作者が生存していないときはどうするのか。聞いた人が必ずしも正しい説明をしてくれるとも限らない。もっと辞書を知って、最大限に活用することを覚えなければならないと、遅ればせながら思い始めている。
最近、 bull ant というのがどの辞書にも出ていなくて、大変苦労した経験があるが、これなども、そんなに手をかけずに調べる方法があるのかもしれない。もっとも、この場合は、 bull ant に日本名がなく、急遽動物学者に作っていただいたりした。これでは、どんな大辞典でも訳語をのせるのは不可能であろう。
訳語といえば、どうもいい訳語が思いあたらなくて困っているときなど、訳語だけを大量に列記した英和辞典ができないかと思ったりするが、実際にそんな辞書ができたら、がっかりするのではあるまいか。なぜといって、原文の意味とイメージをより正確に伝える表現を自分で作りあげていく、その苦しい過程こそが、また翻訳の最大の楽しみでもあるのだから。
*外国人用の日本語辞書を
クネヒト・ペトロ(学生)
本屋に立ち寄るたびに棚に並べたたくさんの外国語辞典とその種類の多さに感心するばかりである。ただし、種類が多いと言ってもそれは主として買手の知識のレベルに適応した種類のことである。日本人なら、様々なものから自分にちょうど良い辞典を選べるので値段の面だけではなく、勉強にも大変便利なことに違いない。
そこで観点を少し変え、諸外国語に当てられた辞典の率をそれぞれの外国語に対する一般人の興味の程度を表わすものさしと考えれば、英語が絶対的王座を占めているようである。
スイスから日本に来て、こうした辞典の状況がわかった時、自分の母国語が英語でないために少しがっかりした覚えもあるが、英和・和英辞典はいいと聞いてさっそく和英辞典を手に入れることにした。しかしそこでまた意外なことに気がついた。見出しのローマ字が読めても、その当時日本語の知識を全然持っていないといっていい私にはその単語を応用した例文の日本語を読む力はなかったのである。英和辞典になるとなおさらそうであった。こうした辞典は主として日本人を相手にしたものであり、日本語を身につけようとする初段階の外国人にとっては価値が限られていることを痛感した。
辞典を編集した先生方のリストを見て名高い方々が協力していたことは印象的であったがなかに外国人が混っているのは稀なようであった。こうした人が日本語ができるかどうかという問題もあろうが、外国語の例文の古さ新しさとか、ある言い方をよく使うか稀にしか使わないかなどのことを判断するためには、手許にある有名な辞典だけではなくて生きている言葉との接触が必要だと思う。辞典というのはピンで板に刺した乾燥した虫のコレクションに似ている。せっかく保存したこの虫は格好悪いものばかりなら、これのみによって虫のことを研究しようと思ってはなるまい。
*生活に役立つように
安永弘子(主婦)
最近、テレビなどで外国語が流行語になったりして、その意味がわかりにくいことが多いですね。略語や新語もどんどんつくられたりする。辞書では略語や新語がわかりにくい。付録に流行語の解説があると便利だと思います。子どもが使うときには特に必要じゃないでしょうか。
外国語辞書を引くのは週三回くらいですが、電車のなかで退屈なときに、字を引くのでなくて文法なんかをみるのも楽しみです。
パリっ子と話したりして、「プロヴァンスはどこをいうんですか」というと、「パリ以外はプロヴァンスだ」なんて、会話にユーモアを感ずることがあるけど、辞書にもユーモアがほしいですね。
前に外地の島にいたことがありますが、お菓子用のメリケン粉に、英語・フランス語で説明書きがあって、それはわかりいいですね。お菓子をつくる材料でショートニングというのがありますけど、料理の本をみればいいことだけど、辞書にもわかりやすい説明が出ていればたすかりますね。飲みものの材料でも、外国のものにはかならず説明があって便利です。
広辞林や古語辞典にやっかいになることが多いですけど、小説を読んでいてわからないことば、引いても出てこない場合がよくあります。とくに読み方には困らされる。「新嘉坡」とか外国地名の漢字のあて字なんか子どもではとても読めません。子どもが旧字を読むのに困って新しい文学全集を買ってくるものだから、家には新しいのと古いのと二冊ずつになっています。
とにかく、辞書は長くつきあうと愛着がわくし、じょうぶでしゃれた感じのものがよいですね。ハンドバックにはいるくらいのサイズで、活字は大きく、電車のなかでもらくに見られるようにつくれないものでしょうか。
▼太田為三郎編『帝国地名辞典』(上・下巻、索引別冊。1,800余ページ)は、明治45年に刊行された。当時は、日露戦争直後であり、勝利に巧みに酔わされた国民が、急速に富国強兵策に引きずり込まれた時期であった。全国に鉄道建設が進められ、現国鉄の本線はおおよそその骨格を完成し、資本主義の第一段階が達成されたころでもある。民衆の動きも活発になり、今日からみれば何倍も時間をかけて旅に出たり、都会に職を求めて郷里を棄てたものも相当な数にのぼった。
この動きに合わせて、旅行を楽しませる出版物もかなり出はじめたようである。その多くは経典型式の製本になる『鉄道道中図』(明治25年刊)の類で、今日見られるガイドブック形式のものもあったろうが、古書としてあまり残っていないために推測の域を出ない。
▼地名辞典の誕生もこれらの背景と無縁ではない。明治40年、吉田東伍の著作になる『大日本地名辞書』が完結した。全11冊、5,180ページの大冊であった。最初の「第一冊上」が富山房から刊行されたのが明治33年であるから、実に7年7か月を要している。
この大著は、その構成、地名の選択・配列が『和名類聚抄』の区分・配列に従っていること、過去の文献による多分に主観的な解説で終始し、この著の成立した時期の各地の客観的な地理的解説はほとんど見られないことなどから、今日的な意味での地名辞典とはいいがたい。しかし、全国各地におよぶ地名の歴史的解説について、いまなおこれを凌駕する書はなく、地誌学上の価値はいささかも失われていないとの評価が一般的である。
▼その後五年を経て初めて、三省堂が名実ともに備わった本格的な『帝国地名辞典』を刊行した。当時にあって、本書の刊行がいかに画期的な意義のある事業であったかは、本書の巻頭を飾る推薦・序文の執筆者陣容(床次竹二郎・蜂須賀茂*(昔に召)・神保小虎・喜田貞吉・和田万吉など)からも推測できる。起稿から15年を要し、その間に稿を改めること三回におよんだといわれる。しかし、本書成立の経緯については、刊行時点で数えても60数年以前のことで、当時の事情を伝える資料もなく、全容ははっきりしない。
編者大田為三郎は、帝国図書館に勤務のかたわら、大部分独力で原稿を執筆したとある。その強靭な精神力は、吉田東伍に勝るとも劣らないといえよう。
▼企画あるいは起稿の当初から、出版元三省堂がどう対応していたかは、ときの店主亀井忠一 (創業者)が本辞典にかけた意地ともいえる一面をたまたま吉田東伍が寄せた序文から知り得て妙である。すなわち、忠一は何ページか組み上がると少しも臆せず吉田のところへ持参して、逐一意見を求めたというのである。吉田も自分のあとを追い、あるいは追い越そうとしている本書に心よく協力したとある。現今では考えられないことで、まさに、明治文化人・出版人の文化創造に対する気慨や気宇の壮大さを伝えるエピソードであろう。
▼政界でも活躍した地理学者志賀重昂は、本書に寄せた序文で、以下の特色をとくに賞揚している。
第一に、地名ごとの解説が、吉田の主観的なのに対してきわめて客観的に記述され、地域の事情を要領よく伝えていること。第二に、大字に至る四万を超える地名を採録し、所在地(原地)の読み方を中心に単純明快な五十音順に配列していることなどである。
ともに今日みればなんの変哲もないことであるが、客観的に記述すること一つをとっても、当時にあっては一大難事業であったろう。交通・通信がかなり発達した明治末年とはいえ、情報量はとぼしく、今日のようにダイアルを回すだけで沖縄とも北海道とも話し合える情況になかったことは確かである。
編者が帝国図書館という、ときの情報センター的部署にいたとしても、そこに集まった資料だけで全国の津々浦々が解説できたとは思えない。凡例にいみじくも書いているように手紙によるたびたびの確かめや出向いての調査を積みあげた結果であって、その苦労は今日の想像を超えるものであったと思える。
五十音順配列にふみ切ったことも、吉田東伍の大著を目前に置いては、三省堂の経験と自信がリードしたとしても相当の決断を要したことであろう。
すなわち、これらの特色が随所にある細かい数値データと相まって、今日までも資料的価値を失わせないのである。明治後半時代の各地の事情をかなりな精度で伝えておればこそ、本書が最近複刻された(昭和49年、名著刊行会刊)所以でもある。
▼三省堂は本書を刊行するにあたり、逐次の改訂を約束していたにもかかわらず、なかなか果たせなかった。60余年後の今年、ようやく『コンサイス地名辞典-日本編-』を刊行して、これにこたえた形である。谷岡武雄・山口恵一郎という現在の権威者を迎え、今日的情報化社会にフィットした内容で再び世に間うた次第である。前者を遺産として、9年近い日時を費して完成した。
この書の編集担当者として、今日に至ってもなお地名に関わる決定的な機関・資料がなく、散々に苦労したことを思うとき、『帝国地名辞典』の大冊を完成した努力に対し、ただただ頭を下げざるを得ない。
(T・O)
▼読者の皆様と新しい三省堂とがより強く結ばれることを願って、この小冊子「三省堂ぶっくれっと」をつくりました。当面年4回の刊行を予定しております。ご愛読ください。
▼昨年末、小社の会社更生法申請という事態に際しましては、ご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。幸い関係者各位をはじめ、読者の皆様の温かい励ましとご協力により、短時日のうちに再建にふみだすことができました。その後、業務も順調に進行し、読書の秋に向けての新企画も着々と進行しつつあり、社の体制も刷新して新しい飛躍を目ざしております。この間のご支援、ご協カにあらためて厚くお礼申し上げるとともに、今後とも小社出版物によろしくご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
▼中学生以上の方なら「コンサイス」をご存知ない方はまずないのではないかと思いますが、このコンサイス英和、和英辞典を全面的に改訂した“新”コンサイス英和辞典、和英辞典を9月に二冊同時に刊行いたします。コンサイス英和〈第10版〉、和英〈第8版〉が発刊されてから10年ほどたちますが、この間変化し続ける日本語と英語を追う周到な作業を積み重ね、その成果を盛り込んだ文字通りの“新”コンサイスです。日本語と英語の最新の接点が集約されています。
▼判例六法としてますます評価の高まっている「模範六法」の昭和51年版を10月上旬にお届けします。「追録請求カード」により判例速報を送呈するという特典も非常に喜ばれています。
▼わが国初の企画としてさまざまの反響を呼びおこしている「日本民衆の歴史」〈全11巻〉も完結に近づきました。9月には第7巻(第9回配本)を刊行いたします。
《編集後記》
▼本誌の目的は、何よりも長い間にわたってつくられた読者と小社との交流を深めることにあります。次号からはさらに読者のページの充実をはかります。
▼第1号は、10年ぶりにコンサイス英和、和英辞典の新版刊行に当たりまして、“ことば”“辞書”論に焦点をおきました。長年日本文学の研究をなさっておられるドナルド・キーン先生の示唆に富んだご発言など、時代とともに生きる辞書づくりの糧にしたいと思います。
▼実りの秋となりましたが、みなさんはいかがお過ごしですか。来年のNHK大河ドラマは「平将門」ですが、編集部では、田舎の埃道を歩いて将門の遺跡をたずねました。東国の民衆の中に生き続ける将門を、はっきりと見ることができました。
次号よりさらに充実した誌面にするよう心がけますので、みなさまのご協力をお願いいたします。(W)