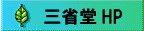池内 紀(いけうち・おさむ ドイツ文学者)
1 カフカと機械 (145号)
2 カフカと文房具 (146号)
3 カフカと健康法 (147号)
4 カフカと金銭 (148号)
5 本づくり (149号)
6 カフカと性 (150号)
7 カフカと映画 (151号)
8 カフカと女性 (152号)
9 カフカの家族 (153号)
 「ぶっくれっと」一覧
「ぶっくれっと」一覧
 カフカ事典
カフカ事典
ライト兄弟がはじめて空を飛んだのは、1903年12月17日のこと。所はアメリカ・ノースカロライナ州キティー・ホーク。浮空時間59秒、飛行距離261メートルと記録にある。自転車の組立・修理業をしていた兄弟が、人類最初の「飛ぶ乗り物」を実現した。
それから6年後、チェコのプラハで出ていたドイツ語日刊紙「ボヘミア」の9月29日朝刊に、「ブレシアの飛行機」と題するルポルタージュが掲載された。筆者はフランツ・カフカ。名前にそえて「プラハ」とあるのは、筆者が無名であって、プラハ市の住人であることを告げていた。
このときカフカ、26歳。労働者傷害保険協会という半官半民の役所に勤める平凡なサラリーマンだった。この年の9月初めに休暇をとって、友人2人と北イタリア旅行をした。その途中、ブレシアの町で飛行ショーがあることをポスターで知って、旅程を変更して駆けつけた。
「ブレシアの飛行機」は、20世紀に現れた新しい乗り物をめぐる、もっとも早い文献の一つである。いかなる技術者、またジャーナリストでもなく、一民間人が興味の赴くままにルポとして書きとめた。
カフカはまず飛行場にたどり着くまでのことを、くわしく報告している。前夜、ブレシアの町に入るので辻馬車に乗ったところ、料金をボラれた。馭者と口論して、ようやく半額にまけさせたこと。そして翌日、同じく辻馬車で郊外の飛行場へとやってきた。
木造の粗末な建物がズラリと並んでいた。飛行機の格納庫だというのだが、カフカにはそれが「旅廻りの劇団の舞台」のように見えたそうだ。前はカーテンで仕切られていて、上に国旗が立てられ、飛行士の名前がついている。カフカは順にメモしていったのだろう。コビアンキ、カーニョ、カルデルラ、ルジェ、カーティス、プレリオー、ルブラン……。そんな名前からも、イタリア人、アメリカ人、フランス人などの合同の国際飛行ショーであったことが見てとれるのだ。
ある飛行士はシャツ1枚になって忙しく格納庫を出入りしていた。アメリカ人飛行士は椅子を持ち出してニューヨークの新聞を読んでいる。
「目を転じると、前方に広大な野原がひろがっていた」
26歳の青年は、それなりにルポの手法を身につけていた。地上に新しく出現した奇妙な空間を、ことこまかに記録している。出発、標示、信号シグナル、連絡用自動車、風向指示旗。あまりにだだっ広いので人工物がすべて孤立悄燃としているように見えた。
「ふつう、こういったショーにつきものの華やぎが少しも感じられない」
引きくらべるようにしてカフカはあげている。競馬場の馬の勢揃い、テニス場の眩しい白線、サッカー場の緑の芝生、自転車や自動車競走のときのパレード。飛行場には、その種のものが何一つない。ときおり野の果てを汽車が煙りをなびかせて通っていくだけ。
飛行士が乗り込んでも、飛び立つまでにひまがかかった。助手がプロペラを廻すのだが、なかなかモーターが始動しない。機械工が油をさし、点検し、ネジをしめ直す。部品を取り換えたりした。やっとモーターが始動してプロペラが廻り出すと、こんどは4人がかりで後尾を押さえている。合図があって、4人がいっせいに離れると、飛行機はゆっくりと走り出し、ついで空に飛び立った。
飛行機のおおかたが2葉式で、羽根のまん中に操縦席があった。下から眺めると、飛行士の下半身と両方に突き出た膝がのぞいている。何度も空中飛行をくり返して、ときには観覧席の真上ちかくにやってくる。
「地上20メートルのところで、一人の男が木製の台に陣どり、みずから選んだ危険に抗がっていた」
ブレシアの飛行ショーではアメリカ人飛行士カーティスが優勝して、3万リラの賞金を獲得した。滞空時間49分34秒、総飛行距離50キロ。またフランス人飛行士ルジェが高度198メートルを記録したことも、カフカのルポからわかる。これは当時、世界初のレコードだった。
カフカはしめくくりにも辻馬車のことを述べている。ショーの終わりを待っているとこみ合うので、少し早目に安いのを見つけ、町に向かった。ルジェがまだ飛行をつづけており、馬車から振り返ると、空の果てをめざすように高度を上げていた。機体の下で沈みかけている夕日が見えた。
*
カフカは飛行機という新しいメカニズムに人一倍の興味があった。この乗り物の異質さ、異様さに、いち早く気がついていた。だから日ごろないことだが、大群衆のただ中へ馬車で駆けつけ、たのまれもしないのにルポルタージュを書いた。日刊紙の記者は筆者の無名をいいことに、あちこちで勝手に原稿をちぢめたらしい。
ルポのはじめとしめくくりを馬車にしたのは、ひそかな理由があってのことではなかろうか。というのは同じ発明品のなかでも飛行機は、まるきり勝手がちがうのだ。汽車にせよ、自動車にせよ、またオートバイや自転車にしても、いずれも車輪にもとづいている。丸い車が足の代用をする。その点では、いずれも馬車の変形であって、どれほどスピードアップしようとも車輪の原理に変わりはない。
ところが飛行機はまるでちがうのだ。これが車輪を必要とするのは助走と着陸の短い時間だけであって、あとは無重力状態で虚空を移動していく。空中に飛び立ったあと、車輪がスッポリと機内に収納されるのが象徴的だ。車が回転して地上にしるしていくはずの距離をそっくり体内に収めている。飛行中、人が微妙なバランス感覚を強いられるのは、そのせいだろう。虚空にあって巻きとられていく空間と時間の平衡状態のなかを浮遊している。
カフカと北イタリア旅行をともにした友人マックス・ブロートは、すでに知られた作家だった。彼は「醜悪なものの美」というテーマの本を企画して、そこにカフカの飛行機ルポを収録したいと言ったとき、カフカは首を横に振った。「未熟な文章」というのが断りの理由だったが、友人に気をつかってのことではあるまいか。カフカはあきらかに美と醜といった審美的なカテゴリーなどで飛行機を見ていなかった。
1911年1月2日付の「ガブロンツ新聞」雑報欄が、「書記官フランツ・カフカ氏の来訪と講演」を伝えている。
ガブロンツは北ボヘミアの工業都市であって、2世紀に入り急速に発展した。織物、ガラス製造、自動車工場などが進出してきた。工場で事故が起きると、労働者傷害保険協会に保険金請求のための申請書が届く。記載事項に不審が生じた場合は協会職員が現場へ出かけ、事故を査定して保険金を決定した。ガブロンツはカフカが担当した重点地区の一つだった。
正しく査定するためには機械や技術に通じていなくてはならない。生産や製造のシステム、またプロセスを知っていなくてはならない。法学部出身のカフカには未知の分野であって、就職の翌年、プラハ商業専門学校の技術者コースに通って、あらためて勉強した。
ハプスブルク・オーストリアのなかでも、とりわけ北ボヘミアで工業化が進んでいた。旧来の職人的手工業から近代的な工場生産へと移行していたときで、つぎつぎと新しい機械が登場してくる。不慣れな労働者に事故がたえなかった。
カフカは労働者傷害保険協会の年次報告書に、毎年のように寄稿していた。その一つは製材機械をめぐっている。これまでの機械とくらべて何倍も効率はいいが、操作が複雑で、うっかりすると指をとばされる。腕を切断されたケースもある。
カフカは指や指先を失った手の図とともに、新しい機械の欠陥を、構造にわたってくわしく分析している。たしかに「安全装置」がついているが、覆いが不完全で、肝心のときに金属板がはね上がり、刃の部分がむき出しになる。1瞬にして労働者の腕をとばしかねない。
年次報告に発表した「製材機械の扱い方」は、フランツ・カフカの名のもとに活字になった、もっとも早い「著作」の一つだった。のちに彼は「流刑地にて」と題する風変わりな小説を書いたが、そこには一つの処刑機械が語られている。上部に「製図屋」とよばれる部分をもち、その指示に従って末端の針が1寸刻みに刑を執行していく。小説の最後ちかくでは、機械が指示を無視して勝手に動きはじめ、とどのつまりは心臓を串刺しにしたまま激しく上下動をつづけた。
1911年1月の「ガブロンツ新聞」は、書記官ドクトル・カフカ氏が「特有の熱意と誠実さ」をもって、保険金制度について語ったことを伝えている。こまかい数字をあげて掛け金の増額にいたった経緯を説明した。改正案につき協会幹部が議会に働きかけているが、いまのところ、めだった成果を上げていない…。
この書記官は産業勃興期の事業家たちが、いかなる素姓の者たちであり、どのような労働条件のもとに短期間で財をなしたか、よく知っていた。時代の波にのり、抜け目なく投資して、一代で金満家に成り上がったことも知っていた。当時の流行だったが、工場の全景をパノラマにして、まん中に自分の肖像を花環で飾って挿入する。そんな絵ハガキが出まわった。いくつかが後世にのこったのは、書記官フランツ・カフカが出張先から、そんな絵ハガキに1筆書いて妹や友人に送ったからである。
事故を正しく査定するためには、機械のことや労働現場の状況だけでなく、労働者の生活環境も見ておかなくてはならない。経営者たちは工場のパノラマに加えて、労働者用の住宅や食堂を絵ハガキに仕立てて宣伝した。カフカはそういったものも買い集めた。
カフカの独自性のよって立つ一点である。彼は作家として、およそ珍しい経歴と体験をもっていた。プラハの友人と、もの静かなカフェやサロンに出入りしたが、その一方で、誰よりも労働者の食堂や住宅にくわしかった。書類カバンを下げて出張に出かけると、車中で数字に目を通していた。彼が日常的に相手にしたのは、教養ゆたかな文学者などではなく、才覚と押しの強さ、それに抜け目なさで成り上がった人物たちだった。あるいは会計係や帳簿主任である。彼らは協会本部からの職員を迎えて、丁寧な挨拶のかたわら、ひそかに相手を推しはかり、なるたけ条件よく補償金を引き出すべく、したたかな策をねっていたはずなのだ。
カフカは勤務を通じて、さまざまな産業機械に通じていた。生々しい労働現場に立ち会い、会計主任しか知らない帳簿の数字を知っていた。やがて「プロレタリア作家」とよばれて登場した者たちよりも、よりひろく、よりくわしく承知していた。ただ小説を書くにあたり、ついぞプロレタリア作家のようなリアリズムの手法はとらなかった。
カフカは機械を通して、近代産業の内幕というものをよく知っていた。その点、2世紀の作家たちのなかで、ほとんど唯1の例外だった。
(以上、145号)
タイプライターとペン
カフカの勤め先は「労働者傷害保険協会」といった。ハプスブルク・オーストリアの官僚組織の末端にあたる。いわゆる「お役所」であって、固苦しい文書を用いた。タイピストがいて、文書類はタイプで清書する。急ぎのときには職員が自分でつくった。 だからカフカはタイプが打てた。就職が決まったあと、専門学校の夜間コースに通って実務を修得した。
「――貴殿の申請に対し、該当条項の規定に従い、ここに受理されたことを通知いたします」
あたまに「ボヘミア王国国立プラハ労働者傷害保険協会」などと、ものものしい刷りこみのある用紙に、タイプで打って手紙を書いた。
機械好きだったカフカはタイプライターそのものは好きだったが、それを用いるのは仕事にかぎられていて、私信には使わなかった。友人、知人、また妹などに宛てた多くの手紙が残されているが、その大半はペンで書かれている。万年筆を使った。ペン先が太めの、書きやすいペンを愛用した。
その一方でタイプライターの効用も認めていた。ベルリンの女性フェリーツェ・バウアーとは1912年に知り合い、5年後に最終的に別れるまで5〇〇通にあまる手紙や葉書を送っているが、その際、カフカはタイプとペンとを併用した。はっきりとした用途を意図してのことである。
「もしかすると、あなたはわたしのことなど、もうお忘れになっているかもしれません」
最初の手紙の書き出しである。友人の家で偶然、出会ってのちに、ひと月以上もたってから出した。もう記憶にないかもしれないと、危ぶみながら書いた。正確にはタイプを打った。2世紀に書かれたラブレターのなかで、もっとも特異な「フェリーツェへの手紙」の第一信は、勤め先のいかめしい用箋にタイプライターでつづられていた。それについては、書き手自身が説明している。
「わたしは筆まめではありません。もしこの世にタイプライターがなければ、もっとひどいことになったでしょう」
「筆まめでない」というのはカモフラージュだったが、タイプについては正直なところだろう。それのおかげで、たとえとりたてて用件がなくても代わりに書いてくれる。人間には、キーを打つための指先があるのだから。
カフカはあきらかに警戒していた。相手の女性に忘れられているのではないか、かりに相手が覚えていても返事をくれないのではないか、たとえ返事がきても、ごくお座なりな断りではないか。
そこでタイプライターを用いた。機械的なタイプ文字という「匿名性」に隠れることができる。願いどおりの返事でなくても、指先は悲しまない。相手の女性が本気で文通を承知してくれたとわかったとたん、愛用の万年筆がとって代わって、日に何通もの手紙、速達、葉書、あるいは電文があふれ出た。
タイプで打たれた第一信にはタイプミスが12ある。そのうちの4つ、つまり3割にのぼって、「わたし」と「あなた」を打ちまちがっている。日ごろ公文書に親しんできた指先が、私的な思いのこもる「あなた」や「わたし」に不慣れであって、キーがなじんでいなかったせいにちがいない。
カフカはフェリーツェと2度婚約して、2度にわたり解消した。感情の起伏が筆記用具からも見てとれる。タイプライターからペンに移って以後も、感情を抑えて即物的に伝えたいときにはタイプを用いた。1916年の発信では、葉書の両面にわたってタイプライターで記されている。これは感情の起伏以上に時代のせいだった。第1次大戦が泥沼化して、郵便の制約が厳しくなり、検閲が強化された。手書きのもの、それも手紙類は何日間も棚ざらしにされる。プラハからベルリンに送るにあたり、戦時検閲をすみやかにすり抜けて、もっとも速く恋人に届けるため、カフカは屈折した思いを、ぶしつけな葉書のタイプ文字に託して送った。
4つ折と8つ折ノート
カフカは生前、ほとんど無名のままに終わった。代表作の長篇3作、および短篇のおおかたはノートのかたちで残されていた。ながらくそれは友人マックス・ブロートのもとにあったが、1968年のブロートの死後、いわば一般に「解禁」になった。ノートの使い方を通して、カフカの書き方が見てとれる。
カフカは2種のノートを使い分けた。一つは大判で俗に「大学ノート」とよばれているもので、紙型から4つ折などとよばれる。もう一つは小学生の学習帖などによく見かける小型のもので、8つ折とよばれるノートである。カフカは長篇には4つ折、短篇には8つ折をあてた。長い小説は大きなノート、短い小説は小さなノート。あきらかにカフカにはノートの大小が少なからぬ意味をもっていた。
長篇3作はいずれも未完である。順調に章をかさねてきたものが、きまってあるところから書き悩み、難渋しはじめる。そののち最終的には放棄されるのだが、書き上げた章と未完の章とに、カフカは自分なりの処置をほどこして区分した。書き上げたものは綴じて手製の扉をつけ、章名あるいは中味にふれる一語をつけておく。未完のものは包み紙でつつみ込むかたちで扉がない。
執筆ノートの写真版があるが、やわらかなペン字が流れるようにつづいていて、ほとんど直しがない。直しがあるのは、何行かにわたり、そっくり斜線で消す場合だけ。この作家は推敲や文飾というもの、文章の改変にあたるものを必要としなかった。小説はつねに直線的に進み、書かれたものが次の1行を生み出していく。方向がズレたと思われるときだけ、ズレの部分をそっくり抹消した。
とりわけ『城』の場合だが、奇妙な難渋のあとがある。全体は1冊の4つ折ノートに書かれていたが、ノートの変わり目、つまり1冊が終わりかけると、しだいに抹消が多くなる。どのノートにも同じようなペンの跡がのこされている。ノートの白い紙が、のこり少なくなってくると、カフカは集中を乱されたらしいのだ。余白が気になってならず、小説が「手からそれ」て、あらぬ方向に転じたがる。1冊分が終わり、新しいノートに入ってからも、しばらくは行き迷う。しばらくして揺れが収まると、踊るような手跡が絵文字のようにあふれてくる。
よく見ると、文字そのものにも特徴がある。同じ4つ折に書かれても順調なときは文字数が多い。1頁あたり350語前後でつづられていく。同じ時期のほかの作品はそうではないのだ。そこではきまって1頁あたり220語前後がいいところだ。
最初の長篇『失踪者』をカフカ自身は「とめどない物語」と名づけていた。青年カール・ロスマンがアメリカを放浪したあげく、ついには大陸の1点で失跡する。
その「とめどなさ」を反省してのことらしい。カフカは次作の『審判』では、第1章にあたる「逮捕」と最終章にあたる「最期」を先に書いた。主人公ヨーゼフ・Kが処刑され、消されてしまうシーンを先に仕上げた。ワク組みを用意したわけだ。
そのなかに奇妙なことがはさまってくる。小説のタイトル『審判』のドイツ語はプロツェス、つまり「過程」といった意味である。カフカのノートは奇妙な断面をのぞかせる。語られていく物語の主人公と語り手とが同じプロセスをたどっていることだ。悪いことをした覚えがないのに逮捕され、自分の知らない罪によって裁判にまきこまれ、往き迷い、追いつめられていく。そんなヨーゼフ・Kと同様に、作者フランツ・カフカもしだいに往き迷っていく。そしてついには作品を放棄した。
ワクを決めた上で部分を埋めていくのは、カフカ自身の小説『万里の長城』に語られている建造方法と似ているだろう。万里の長城の建造は、東西の始まりを決めたあと、作業班ごとに一定の区画を受けもって、あとから一つ一つ継ぎたしていく。長大な全工区を埋めようとしても、どうしても空隙ができる。長城は、とどのつまりは未完に終わったが、カフカの長篇『審判』もまた、一応の終わりはあるにせよ、空隙だらけで終わった。
工区方式によったせいか、『審判』のノートはまた変わった使い方を見せている。章によって使いのこしがあるとき、カフカはノートを逆さまにして利用した。べつの章はうしろ頁を前にして書いていった。外側からレンガの積み上げをしたようなものだろう。カフカは日ごろ、きわめてつましい生活者だったが、ノートの余白を活用するにも、そんな生活者が顔を見せている。
短篇用に使われた8つ折ノートは、紙がうっすらと青味がかっている。まさに小学生がカバンに入れていたしろものである。1916年から17年にかけて、カフカはしきりに寓話風の短篇を書いた。そのかなりが1頁か2頁のもの。『審判』を中絶にしたあとであって、新しいスタイルを試みるにあたり、カフカは粗末な8つ折ノートを1冊ちかく買ってきた。最小に切りつめた散文を書くに際して最小のノートを用意した。カフカにとって文房具がモチーフと密接なつながりをもっていたことがうかがえるのだ。
ちょうどこのころ、いちばん年少の妹が部屋借りをしていた。それはモルダウ河を渡った先の旧プラハ城内の一廊にある「錬金術師通り」にあった。むかし、ボヘミア王が気前よく錬金術師や魔術師を召しかかえたことがあって、4方からやってきた連中を住まわせたところだ。いまもむかしのままに伝わっているが、屋根の低い2階建てが細長くつづき、それが小さく区切られている。妹が借りた小部屋に兄貴がのこのことやってきて仕事場にした。痩せて背高ノッポだったカフカは、低い戸口で何度となく頭をぶつけたのではあるまいか。
勤めから帰ってくると、2時間ばかり仮眠をとる。夕食のあと、小さな包みをもって家を出て、モルダウ河の橋を渡り、何百段もの王城への石段をのぼっていった。包みには、ちょっとした夜食と、小型ノートが入っていた。夜ふけまで小説を書き、また翌日の勤務にそなえて市中の家にもどってくる。
小さなノートに小さな物語を書くにあたり、カフカは小さな空間を求めた。まったくそれは、4畳半ほどの小ささなのだ。いったい、どのような気持ちで、発表のあてのない小説をせっせと書いていたのか、感慨めいたことは彼は一切書いていない。
いずれにせよ、コッペパンに小さなノートの包みをぶら下げ、長い石段をのぼっていく姿は、2世紀の文学的風景のなかで、もっとも美しい一つではなかろうか。
(以上、146号)
カフカは好んでサナトリウムに出かけた。2代はじめから2数年にわたっており、この点、フランツ・カフカは2世紀の文学者のなかで、とりわけサナトリウムにくわしかった一人である。
それというのも出かけるに先立ち、いつも慎重に比較検討して、決めたからだ。環境、設備、ホテルと客層のこと。薄給のサラリーマンには、いつもホテル代が気になった。一度入ったホテルから、近くにもっと安いのを見つけて引き移ったこともある。
1903年、ドレスデン近傍のサナトリウム「白鹿園」を訪れたのがはじまりだった。法律の第1次国家試験をすませた直後である。試験疲れの保養という名目だった。そのとき2歳の青年に、はたして保養の必要があったかどうか疑問だが、両親はそれを許した。わが家ではじめてのドクター誕生を心待ちにしていたからである。医者をしている叔父がいて、その勧めもあった。
当時の医学が、しきりに自然療法を推奨していたことがうかがえる。応じてヨーロッパ各地に新しい理論と新しい療法を標榜するサナトリウムがつぎつぎに生まれた。「白鹿園」は正式には「ラーマン療養所」といって、ドクトル・ラーマンの開設になり、北ドイツで知られた施設だった。大きなホテル式の建物に、ゆったりした談話室と広い庭やプールやバンガローがそなわっていた。カフカが両親に送った絵ハガキには、パンツ1枚で9柱戯をしたり、鉄棒をしたり、新聞を読んだりしている人々が見える。陽のあるかぎりデッキチェアで日光浴をした。
カフカはのちに菜食主義に傾いたが、きっかけは、サナトリウムの食事だったと思われる。一人で食事をとるときは肉を食べない。家族いっしょのときは、母親が心配するので少しは食べた。
1905年、最後の国家試験をなんとか「可」の成績で通過して、その夏をサナトリウムで過ごした。このたびは当時オーストリア領だったシレジア南部の小都市ツックマンテル(現チェコ)にあったもので、くわしいことはわからない。ただカフカがのちの手紙に書いているところによると、そこである女性と恋愛をした。初恋の人は人妻だったようで、いまも「心がしめつけられる思い」と述べており、ずっと記憶にあったようだ。そのころ「田舎の結婚準備」と題して長篇小説を試みていた。未完に終わったが、そこに語られている年上の女性は、夏の体験がもたらしたものだろう。翌年の夏にもツックマンテルを訪れているのは、記憶が引き寄せたからにちがいない。
しばらく空白があるのは、勤め先の出張や、友人マックス・ブロートとのパリ旅行、イタリア旅行がはさまるからだ。1912年7月、299歳のとき、ドイツ中央部ハルツ山地のサナトリウム・ユンクボルンへ出かけた。こののちは毎年、サナトリウムを訪れた。
ユンクボルンは医学博士ルドルフ・ユストなる人物が開いたもので、「自然へ帰れ」をモットーにして、山の南斜面にさまざまな設備をそなえていた。文明を捨てて自然に帰るにあたり、肉体をしめつける衣服も取り去る。野外活動は全裸で行う。すっ裸の男たちがボール遊びをしたり、芝生を4つ足で歩いたりしている写真がのこっている。リクリエーションで芝居をするにもそうだったようで、いかめしいカイゼル髭に帝国帽をのっけた男が、まる裸の腰にサーベルをぶら下げていたりする。
カフカは2週間いたが、日光浴だけで、むしろ多少とも皮肉な目で自然に帰った人々をながめていた。そして小説に没頭した。短篇「流刑地にて」と長篇小説「失踪者」の一部がこの間にできた。
ついでながら同じ1912年の7月、トーマス・マンがスイスのタヴォスで療養中の従兄を見舞いにサナトリウムを訪れ、3週間ばかり滞在している。この間の体験をもとにして長篇「魔の山」を書いた。まさしくサナトリウム小説というべきもので、物語は終始、タヴォスの療養所を一歩も出ない。
その少し前、ロシアの劇作家アントン・チェーホフが南ドイツ・バーデンワイラーのサナトリウムにいた。結核を病んでいたから、チェーホフにはたしかにそこに滞在する理由があった。専門医が日常のこまごましたことまで処方をする。当人が医学博士だったチェーホフは、いたって冷静に見ていたにちがいない。ドイツ人医師の療法を妻に書き送っている。朝7時起床、夜7時の就床まで日課がきまっており、寝る前に安眠用のイチゴ茶を飲む。チェーホフは書き添えている。
「すべてにひどく、いんちきくさい匂いがする」
カフカにも似た思いがあったらしい。サナトリウムはどこも「ホメオパティー」とよばれる療法や、菜食、裸体生活、瞑想をうたっていたが、菜食以外、彼が積極的に取りくんだ形跡はない。何よりも職場から、また家族から離れて一人でいられるのがうれしかった。たっぷりとヒマがあり、天下晴れて小説が書ける。
1913年はイタリアへ出かけた。ガルダ湖畔のリーヴァのサナトリウムに3週間いた。18歳のスイス娘に恋をしたのもこのときである。ベルリンの女性フェリーツェ・バウアーと婚約を考えているさなかのことだ。サナトリウムがカフカには、日常とは異次元の別世界であったことがうかがえる。保養先の恋であって、それは保養地ではじまり、またその地で終わるべきものだった。チェーホフの小説「小犬をつれた奥様」のように、恋をわが家まで持ち帰ってはならない。カフカはつねにきちんと保養先に置いてきた。
1915年、北ボヘミアのサナトリウム・フランケンシュタインに2週間滞在。
1917年は西ボヘミアの寒村チューラウ。これはサナトリウムではなく、妹の親戚がもっていた庭と畑つきの別荘。
1918年、シレジアの保養地リボッホ。ユーリエ・ヴォリツェクという女性と知り合い、短期間だが婚約までした。
1920年、北イタリアの保養地メラーノに3カ月滞在。
この間にカフカにとってサナトリウムの意味が大きく変化していた。1917年8月に最初の喀血をみて結核と診断された。当時、結核は死の病とされ、空気のきれいなところで保養につとめるしか治療法がなかった。職場と家族からの逃避の場であったところが、本来の療養にはげむための場になった。しかし、カフカ自身にはサナトリウムの療法がつねにチェーホフのいう、「いんちきくさい匂い」があったのではあるまいか。勤め先から特別休暇をとりつけてサナトリウムに入ったわりには、そのことはほとんど報告していない。たとえ手紙に書いても、つねに皮肉をまじえている。メラーノは鉱泉が湧いていて、飲泉療法で知られたところだが、カフカは処方されたとおり飲んだのかどうか。少なくともメラーノ滞在中の時間の多くが、ウィーンにいる恋人ミレーナへ手紙を書くのに費やされたことはあきらかである。3カ月たらずの滞在で本1冊分を書いた。
1920年12月末、サナトリウム・タトラ別荘に滞在。チェコとポーランドの国境、標高千メートル近い高地にあった。真冬にどうして高冷の地を選んだのかはわからない。ホメオパティーは「同種療法」とも言って、凍傷の治療には雪を、火傷には熱湯にひたした布を、頭痛には刺激の強い珈琲をあてた。「病を病によって癒す」理論がうたわれていた。カフカ自身、共鳴はともかくも共感するところがあったのだろうか。結核を通してたえず死滅していく肉体は、カフカの変身幻想をなおのこと高めたと考えられる。病の親和力といったものをカフカがかなりの程度まで意識していたことは事実である。自分では「招き寄せた病」とよんだ。
高地タトラは病いは癒やさなかったが、雪に覆われた世界を存分に見させてくれた。やがて長篇『城』に取りかかったとき、全篇にそれが生かされた。とするとカフカはむしろ医学よりも文学のためにサナトリウムを選んだことになる。
1922年、南ボヘミアの田舎。
1923年、バルト海の保養地ミュリツ。最後の恋人ドーラ・ディマントとここで知り合った。その恋人が死のときまでつきそった。
1924年、ウィーン近郊キーアリングのサナトリウム・ホフマン館。喉頭結核のため食事がとれない。ふだんから痩せていた人が、なおのこと痩せ細った。出入りの理髪師は髭にあたろうとして、骨だけの顔に途方にくれた。そんななかでカフカは短篇集「断食芸人」のゲラ刷を校正した。何も食べないことを見世物にしている芸人の物語。カフカの場合、創作と実在とが奇妙なかたちで結びついていたことが見てとれる。
6月3日、サナトリウムで死去。その文学の展開に欠かせない場であったことよりすると、もっともふさわしいところで死んだといえる。
(以上、147号)
長篇小説『失踪者』の主人公は17歳で単身アメリカへやってきた。理由が冒頭に述べてある。
「女中に誘惑され、その女中に子供ができてしまった。そこで17歳のカール・ロスマンは貧しい両親の手でアメリカにやられた」
カフカは主人公を16歳にするか、17歳にするかで迷ったようだ。ノートに書いたときは17歳だったが、はじめの1章を独立させ、「火夫」のタイトルで発表したときは、一つ削って16歳にした。微妙な違いを感じたせいだろう。17歳だとすでに大人に立ち入っており、いわば「小さな大人」といったところだが、16歳はまだ少年であって、「大きな子供」というものだ。事実、小説の進展とともに、カール・ロスマンは大きな子供から小さな大人への変貌をとげていく。
「大きな子供」を印象づけるためだろう、カフカは冒頭すぐにヘマな主人公を語っている。船がニューヨーク港に着き、トランクを担いで下船にかかったとき、カールは船室に傘を忘れてきたことに気がついた。いそいで取りにもどろうとして、ほとんど見ず知らずの人に大切なトランクをあずけてしまう。なんとも無思慮で、軽はずみだ。すぐあと、「傘はむろんのこと、トランクもなくしたというわけか」とからかわれたが、そんなふうに言われてもしかたがない。
身一つであれ、「大きな子供」はさして苦にしない。上等の服を着込んでいる。トランクの服は予備のもので、出発のまぎわまで母がつくろっていたしろものだという。彼はむしろヴェローナ・サラミを残念がった。まるまる1本、手をつけないままトランクに残していた。
「母がわざわざ包みこんでくれたものだ」
酷い両親の仕打ちのような書き出しだったが、実はそうではなく、むしろ甘い親であり、世間体をはばかって泣く泣く息子を異国へ送ったことが見てとれる。母親は予備の食物だけでなく、いざというときのため、カールの上等の服の隠しポケットに折りたたんだ紙幣をしまっておいたらしいのだ。父親がそっと指示してのことだったのではあるまいか。
どこの馬の骨ともつかぬ2人組と職探しの旅をする羽目になって、隠しポケットの紙幣がかかわってくる。2人組はカールのふところをあてにしており、一方、カールは無一文を装っている。安食堂で食事したあと、カールは小銭だけを取り出そうとして苦労した。そして、ほんのなけなしを取りだしたはずなのに、うっかり中身をさとられてしまった。2人組の一方が毒づいたとおりなのだ。
「こいつはお金持の坊ちゃんなんだぜ。羨ましいじゃないか」
最初の長篇に苦心していた際、カフカは思わず知らず自分を移しこんだようである。友人や知人、また恋人たちの伝えるカフカには、小説の主人公そのままの「大きな子供」の面かげがある。カフカはたえず、世間をよく知っている、しっかり者の女性たちに愛されたが、彼女たちは期せずしていつも年齢とはかかわりなく、カール・ロスマンの母親のような役まわりを引き受けたらしいのだ。
大きなホテルのエレベーターボーイの口にありついてのち、カール・ロスマンは俸給をすべて調理主任にあずけ預金してもらった。これもしっかり者の女性であって、チップも毎週きちんともっていった。カフカがほとんど生涯を通じて取っていたやり方と同じである。俸給はそっくり母親に預けた。母親はフランツ名儀で貯金した。おりおりは自分のへそくりを少し足してやったかもしれない。
フランツ・カフカは3人兄弟の長男である。弟が2人いた。しかし、ともに幼いときに死んでしまった。あとは女の子ばかりが3人つづいた。
家長制を色こくとどめたユダヤ人一家のなかで、この長男がどのように扱われたか想像がつくだろう。実質的には一人息子であり、母はことのほか甘く、父はことさら厳しい。その厳しさもまた甘やかしの変形というものだ。同じく『失踪者』の冒頭に、カールの父親は仕事でかかわり合う連中を「葉巻で手なずけていた」と述べているが、カフカの父親を思いださせる。甘い母親に舌打ちしながら、父親は何かにつけて息子フランツに処世術を説いた。幼いころに体験した苦労を語り、世の中で生きていくすべを伝授しようとした。「葉巻で手なずける」など、世なれた商人ヘルマン・カフカのやりそうなことである。
カフカはのちに父から受けた「被害」を数え上げるようにして「父への手紙」を書いた。大型タイプ用紙で415枚にものぼる長文のものだが、それは一度中断している。
「生活無能者のおまえは、それでもなお――」このあと、小さな紙型の2ページあまりが手書きで添えられて終わっている。父の言葉を引用していて、「生活無能者」の一語が、とりわけカフカには痛切に思い当たったからではなかろうか。
1906年、カフカ23歳。プラハ大学法学部を終って、国家試験に合格。晴れてカフカ家に「ドクター」の肩書持ちが誕生した。
これまでハレものにさわるような扱いだった。ところがその長男は職探しに身を入れず、夜っぴいて小説を書いたりしている。父の命令で店の手伝いをさせられたのだろう。友人への手紙でボヤいている。
「しばらく顔をみせなかったが、申し訳ない。木箱を運んだり、棚を磨いたりしなくてはならないのだ。店の娘は覚えが悪くて困る……」
未完に終わった小説「田舎の婚礼準備」を書きはじめたのも、同じ1906年である。主人公はラバン、綴りでいうとRabanであり、Kafkaと母音のつくりがそっくりだ。『変身』の主人公ザムザ(Samsa)とは爪2つ。そして、たしかにいち早く『変身』のモチーフが顔をのぞかせている。ラバンは床につくとき、思ったものだ。
「ベッドに寝ているあいだに、ぼくは一匹の大きな甲虫、くわがた虫、あるいはフキコガネになっているはずだ」
ぶよぶよした腹に細い無数の脚がつき、それをもじゃもじゃさせているというのだが、6年あまりのちの『変身』では、ある朝、ザムザが目を覚ますと一匹の大きな毒虫になっていた。
23歳のときの作では、虫はまだ冬眠していた。カフカ自身の自画像というものだろう。いや応なく世の中へ出ていかなくてはならず、自分が虫になる想像は、失われた楽園へのせつない願望というものではなかろうか。だからこそ眠りのなかへ潜在的な夢がまじりこんだ。
カフカがはじめて金銭を稼ぐのは、翌1907年10月にイタリアの保険会社「アシクラツィオーニ・ジェネラリ」に就職したときである。プラハ支店へ「臨時雇」として入社。月給80クローネ。大卒、法学のドクター持ちには、およそ考えられないような安俸給だった。人事書類の備考欄につぎのような記述があった。
「当ドクター・カフカ氏については、アメリカ副領事で、マドリッド総支配人の父親ヴァイスゲルバー氏より強い推薦があった」
カフカの母親の兄の一人がマドリッドにいた。そのコネが使われたことが見てとれる。マドリッドの叔父が、イタリアの保険会社のマドリッド総支配人に声をかけ、総支配人がプラハにいる自分の父親、アメリカ副領事をしているヴァイスゲルバーに連絡し、その人が支店採用を働きかけた。情実づくの人事であって、法外に安い俸給は、そのせいだったと思われる。
それかあらぬか、この臨時雇はこき使われた。就職して半年ばかりのち、カフカは書いている。
「ひどい1週間だった。獣のようにひっぱたかれ、また獣のように駆けまわらなくてはならない」
ひそかにつぎの職探しをして、1908年7月、「学働者傷害保険協会」に移った。同じ保険業務だが、こちらは半官半民で身分が安定していて、仕事も少ない。はじめは「仮雇い」の身分で日給3クローネ。収入の点ではほとんど変わらないが、「本雇い」になれば昇給する。
このたびもコネがフルに使われた。友人の父親のユダヤ人でプラハ財界の重鎮だった人物が口をきいた。いかに例外的な人事であったか、つぎの事実からもわかるだろう。250人を数えた全職員のなかで、ユダヤ人はカフカを入れて2人きり。先の一人はドクター・フライシュマンといって、「4分の1ユダヤ人」といわれる人だった。しかもカフカの在職中、3人目はついに採用されなかった。 精勤につとめ、順調に地位が上がった。1910年、「書記官」の肩書き。名実ともに本採用となった。1913年、書記官主任、おおよそ係長にあたる。1920年、秘書官に昇任、課長である。勤めをやめるときは秘書官主任、つまり部長になっていた。
ベルリンの恋人フェリーツェとの結婚話が具体化して、家探しをしたことがある。両親が探してきた物件らしいが、カフカはかなり躊躇した。家賃が1300クローネかかり、月収の4分の1が消えてしまうからであって、どの程度の月給取りであったか、ほぼ推測がつく。
その結婚話がつぶれたとき、カフカは生涯に一度だけ、作家として立つことを真剣に考えた。小官吏をやめてベルリンに住む。旅先から両親に手紙で伝えた。これまで5000クローネを貯金しており、ベルリンかミュンヘンで2年は暮らせる。
「この2年間を文学に集中すれば、なんとか生活できるだけの力がつくでしょう」 手紙は書きさしで終わって、送られなかった。貯金に思いを馳せたとき、カフカはいや応なく思い至ったのかもしれない。子供預金のように、月ごとに母親の手で貯えられていたこと。とたんに自立の決心が萎えた。
1922年、依願退職。実働13年11ヵ月、恩給がつくぎりぎりの年月だった。以後は月額1450クローネの年金生活者。やっと自由の身になって、親元をはなれ、ベルリンで生活をはじめた。つましい年金がつましい生活を保証するはずだった。ところがその日常をおよそ途方もない金額がまかり通った。第1次大戦後にドイツを襲った激烈なインフレのさなかで、みるまに金銭が下落していく。両親からの送金の礼をかねた手紙に報告している。
「こちらでは公式の為替レートが低いのです(たとえば土曜日には1チェコ・クローネは180億マルク、闇では250億マルク、しかしプラハでは、1000億マルクをこえており、物価の方は残念ながらドイツ国外の為替レートに準じているのですね)……」
天文学的な数字の紙幣を束にして、タマゴ一つがやっと手に入る。つましい年金生活者が、およそ奇妙な状況に巻きこまれた。みずから小説で書いたようなへんてこな状況を身をもって実践したぐあいなのだ。
2年後の6月、カフカ死去。葬儀のあと、義弟がプラハの労働者傷害保険協会に死亡届を提出、やがて元官吏への慰労金支給の連絡がきた。死亡見舞い金1万1058クローネ、住宅手当4608クローネ、特別金4200クローネ、その他を合算して計3万3084ローネが遺族に下しおかれた。死亡者が独身だったことにつき、年金法第15条にもとづいて以後の年金の権利は両親に移行。これ以外の諸権利は当人の死亡により一切消滅した旨の注記がついている。
(以上、148号)
カフカの小説は生前、ほとんど本にならなかった。手稿を忠実に生かした、もっとも新しいカフカ全集は全6巻を数えるが、そのうちカフカ自身が発表したものは1巻だけである。あとはすべてノートのかたちで残されていた。
作者が本にするのをイヤがったから――少なくともそんなふうに言われてきた。カフカの死後、友人マックス・ブロートがノートを編集して最初の全集をつくったが、合わせて彼はくり返し語ってきた――カフカが自作を何度となく破棄しようとしたこと。病んでのちノートをブロートにあずけ、2度にわたり遺言として焼却を依頼したという。
しかしながら、その一方で、カフカは生前、7冊の本を出している。どれもごく薄っぺらなものではあれ、出すにあたり、表紙や扉や本文の組み方について、あれこれ注文をつけた。カフカの要求に対して版元が色よい返事をしなかったとき、ほかの出版社をほのめかしたりしたし、売れ行きのためといわれると、気の進まないことでも承知した。本になるとよろこび、書評を気にかけ、本屋に立ち寄って、何くわぬ顔で自分の本を買ったりした。
カフカは出版に対して、いたって奇妙な、あるいは微妙な態度をとっていたようだ。世に問いたいと思う一方で、とても受け入れられず、評価されないことを知っていた。手ひどい結果を見こしていて、惨めな思いをするくらいなら、強いて出さなくてもいいとしながらも、やはり本にしたいと願っていた。それ自体は、とりたてて奇妙でも、微妙でもない。表現する人間が、多かれ少なかれ抱いている誇りとたじろぎである。
カフカの場合、きわめて幸運に恵まれていた。まず、友人マックス・ブロートがつねについていた。ブロート自身が作家であって出版社とつながりをもっていたし、親友フランツ・カフカの才能をかたく信じ、世に出すことを自分の使命とすらみなしていた。それにブロートは、いわゆる感激好きの世話焼きと分類されるタイプで、自分の熱中することには労を惜しまない。友人のこのような性格を、カフカが多少ともあてにしていたふしがある。
版元の点でも運がよかった。ちょうどカフカが創作に本腰を入れはじめたころ、ライプツィヒで新しい出版社が産ぶ声をあげた。2人の共同出資により、ともに2代半ばの青年で、カフカよりも年下だった。
生まれたばかりの出版社は、名の知られた作者に相手にされない。若い書き手に向かうしかない。新進作家マックス・ブロートに目をつけ、ブロートを介してカフカを知った。
共同出資者の一人はエールンスト・ロヴォールト、もう一人はクルト・ヴォルフといった。出資の比率によったのか、出版にあたっては、「エールンスト・ロヴォールト書店」を名のった。これが「カフカの最初の本」の名誉をになっている。
ロヴォールト書店は現在、ドイツで有数の大手出版社である。しかし、カフカのために果たした役割を、あまり誇るわけにはいかないだろう。というのはカフカの最初の本を出すには出したが、その本が町の本屋に並ぶころ、エールンスト・ロヴォールトはすでに出版から手を引いていた。彼があらためて出版業にのり出すのは、7年のちのことである。
この点でも、カフカは幸運だった。ひとり残されたクルト・ヴォルフは、目はしのきくロヴォールトとちがって、文学青年の坊っちゃんだった。売れ行きを考えず、めあたらしいものに目がない。そんな相棒を危なっかしく思ってロヴォールトは身を引いたのかもしれない。正しい見通しだったと言わなくてはならない。ロヴォールトは大出版社として存続しているが、クルト・ヴォルフ社はあとかたもない。
新しい文学を世に問うにあたり、クルト・ヴォルフは案をひねり出した。叢書のスタイルにする。どんなに薄いものであれ、とにかく1冊にして、値段も安く、番号をつけて出していく。
”最後の審判”叢書といった。へんに気取った名前だが、1910年代には「最後の」といった形容詞がはやっていた。世紀末以後のデカダンスの産物であり、きたるべき第1次大戦の予兆もあったのだろう。より正確にいうと、叢書”最後の審判”のドイツ語は、聖書の説く ”世界審判”を借りており、期せずして的確に時代相をとらえていた。新文学のシリーズにふさわしかった。
シリーズであるからには定期的に、またつづけて出さなくてはならず、1点ごとの売れ行きにかまっていられない。たとえ売れ行きの見込めないものでも、冊数にはなるし、つぎの刊行で埋め合わせがきく。カフカが本にした7冊のうち4冊までは、叢書に入ってあらわれた。つまり到底、ほかからは出なかったからである。
最初の本を出す前のことだが、カフカはブロートとともにライプツィヒへ出かけ、ロヴォールトとクルト・ヴォルフに会った。その日の日記にカフカは書いている。
「ロヴォールトはわりと本気でぼくの本のことを考えている」
曖昧な書き方であって「わりと本気で」は「あまり熱心でなく」とも取れる。実際、ロヴォールトがそんな応対をしたからにちがいない。新進のブロートがつれてきたし、新しい書き手を求めているからには、無下に断れない。といって紹介されたカフカの作品は、実になんともへんなものであって、とても売れるとは思えない。
カフカが日記にロヴォールトの反応だけを書いているのは、出版者2人の関係をきちんと見通していたからだ。共同出資であれ、発言力は圧倒的にロヴォールトにあった。カフカはきっと、さりげなく合槌を打ちながら、注意深く相手の反応をうかがっていたのではあるまいか。
相談が終わって別れたあと、カフカはライプツィヒの街を散歩していて、クルト・ヴォルフと出くわした。この点でもカフカはきわめつきの幸運児だった。相談の場では、ともに脇役だった2人は気が合い、ひとしおの思いで語り合った。以後、カフカはクルト・ヴォルフ社の作家になった。半年ばかりして最初の本が出たとき、恋人への手紙に書いている。
「神はこの青年に美しい妻と、数百万マルクの遺産と、大きな事業欲と、ほんのわずかな経営的才覚を与えた」
『観察』 カフカが本にした最初のもので、それまでに書いてきた小品18篇を収める。1912年、エールンスト・ロヴォールト書店刊。全99頁。「800部限定」とうたってあって、扉うらに番号が手書きされていた。3年後の1915年に、なお500部以上が売れ残っており、1年後の目録に「在庫多数」としるされている。プラハのある書店で11冊売れた。その1冊は自分が買ったと、カフカ自身が語っている。
「あとの1冊は誰が買ったのでしょう?」
『判決』 1912年9月22日から23日にかけての夜に書き上げた短篇。1916年、クルト・ヴォルフ社刊。全28頁、”最後の審判”叢書34。
『火夫』 1912年に執筆、未完のまま放棄した長篇『失踪者』の第1章にあたる。1913年、クルト・ヴォルフ社刊、全47頁。”最後の審判”叢書3にあたる。
 『変身』 1912年11月から12月にかけて執筆。1916年、クルト・ヴォルフ社刊、全72頁。 最後の審判 叢書22/23にあたる。表紙にはオトマール・シュタルケによる絵がついていて、ナイト・ガウンにスリッパの男が顔を両手で覆っている。背後の両開きのドアの片方が開いていて、黒々とした闇が見える。クルト・ヴォルフの提案に対して、「主人公は描かない」という条件つきで、カフカはしぶしぶ承知した。
『変身』 1912年11月から12月にかけて執筆。1916年、クルト・ヴォルフ社刊、全72頁。 最後の審判 叢書22/23にあたる。表紙にはオトマール・シュタルケによる絵がついていて、ナイト・ガウンにスリッパの男が顔を両手で覆っている。背後の両開きのドアの片方が開いていて、黒々とした闇が見える。クルト・ヴォルフの提案に対して、「主人公は描かない」という条件つきで、カフカはしぶしぶ承知した。
全7冊のうちの4冊までが1912年に書かれるか、本になるかしている。かたわら、カフカは長篇『失踪者』を書き進めていた。創作熱が高まりをみせた第1期といえる。
『流刑地にて』 1914年、執筆。1919年、クルト・ヴォルフ社刊、全68頁、新しくはじまった ”ドゥルグリン”叢書4として出た。初版1000部と明示されている。クルト・ヴォルフ社の売り上げ台帳によると、1920年6月末までに607冊が売れた。
『田舎医者』 短篇14篇を収める。そのうちの12篇は1917年はじめに集中的に書かれたもので、創作熱が高まりをみせた第2期だろう。1919年、クルト・ヴォルフ社刊、全189頁。カフカの生前の本のなかで、並外れてぶ厚い。1000部出され、1920年6月末までに86冊が売れた。
『断食芸人』 1920年から24年にかけて書いた短篇4篇を収める。1924年、ベルリンのディ・シュミーデ社刊、全85頁。初版3000部。版元よりマックス・ブロートへの手紙によると、1925年3月末までに551冊が売れた。
出版社を取り換えたのは、カフカ自身の意向によった。一つには『田舎医者』を出す際、クルト・ヴォルフと気持のいきちがいがあった。いま一つには、カフカは1922年に勤めをやめ、ベルリンへ移って作家として自立することを考えていた。そのためにはライプツィヒの書店よりもよりもベルリンの出版社のほうが将来のために便利だと考えたのだろう。ディ・シュミーデ社は生まれたばかりの出版社で、書き手を求めており、3000部という、これまでになく多い部数は、そんな事情のせいだった。
カフカは『断食芸人』の刊行を見なかった。発行の2ヵ月前に世を去っていた。喉頭結核により喉を冒され、食事がとれなかった。強いられた「断食」のなかで、まさしく自分の文学を生きていたことになる。
(以上、149号)
『失踪者』はカフカがはじめて試みた長篇小説である。書き出しは、つぎのとおり。
「女中に誘惑され、その女中に子供ができてしまった」
主人公カールは17歳の少年。心ならずもの性が受難のはじまりだった。両親は世 間体をはばかって彼をアメリカへ追いやった。
誘惑の経過は第1章の終わりちかくで語られる。回想のかたちをとっているが、きわめてリアルだ。まずは誘惑の予兆といったもの。女中がそれとなく誘いかけてくる。じっとカールを見つめていたり、やにわにけたたましい笑い声を立てたり、台所で通せんぼをしたりする。わざと女中部屋の戸をあけておく。少年にも、ほのかな応じるけはい。
「カールは通りすがりに、少しあいた戸のすきまからおずおずとながめたりした」 ある日、女中がカールの名を呼んだ。予期しない呼びかけにカールがとまどっていると、やにわに彼の手を握りしめた。そして顔をゆがませ、息づかい荒く自分の小部屋につれこんで鍵をかけた。つづいて息がつまるほど強くカールを抱きしめ、裸にしてくれとたのみ、実際は自分から裸になった。そしてカールの服をぬがせ、ベッドに寝かせた。
「カール、わたしのいとしいカール!」
叫びながら見つめ直し、抱きすくめた。カールの胸に耳をあて、つづいて乳房をゆすり上げて心臓の鼓動を聞いてほしいと言った。カールが断わると、腹を押しつけ、片手でカールの股のあいだをまさぐった。カールは思わず首を枕からせり出した。
セックスそのものには、カフカはただ次の1行をあてている。
「女中の腹がなんどか自分のからだと衝突した」
少年は必死になって何かをこらえていたという。そのあと、泣きながら自分のベッドにもどった。
『失踪者』は未完のまま放棄されたが、カフカは第1章を独立させて短篇として発表した。その際、主人公の年齢を一つへらして16歳にした。
きわめてリアルな描写のせいだろう、女中の誘惑をカフカ自身の実体験とする解釈がある。そのときに受けた精神的な傷、心理学でいうトラウマが、のちの生き方にも見てとれるというのだ。カフカは愛した女性と婚約はしても結婚にはつねにたじろぎ、他人には不可解と思えるような行動をとった。
当時の生活資料からもうかがわれるが、市民の家庭には、たいていの場合、女中用の小部屋があり、住み込みの女がいた。カフカが十代のころ、住み込みの女中のほかに通いの女がいた。カフカ商会が軌道にのり出したころで、両親はほとんど店につめていた。そんな留守中、女中がいたずら半分に少年フランツを誘惑したとしても不思議はない。
カフカ研究家アンソニー・ノーシーの『カフカ家の人々』によると、カフカの従兄の一人は16歳のときに女中に誘惑され、その女中に子供ができたので、両親の手でアメリカにやられたという。何かのおりに父と母がそのことを口にして、わが子への戒めとするようなことがあったかもしれない。あるいは女中についての両親のやりとりのなかに、多感な少年がいち早く察知するようなことがあったのではなかろうか。ともに小説冒頭の即物的な書き方が告げている。そういった「事件」は、さして珍しいことではなかったはずだ。小説のなかの両親は世間体以上に、生まれた子の養育費のことがもち上がるのを恐れて息子をアメリカへ放逐したらしいのだが、その種のことも少なからず起きていたにちがいない。
仮に小説の主人公を作者自身と重ねると、カフカの17歳は、ちょうど1900年にあたる。同じこの年にフロイトの『夢判断』が刊行されている。そのなかでフロイトは夢を手がかりにして潜在的な意識にひそんでいる性願望をあばき出した。市民モラルの呪縛のなかでいかに性が抑圧され、その結果、潜在意識のなかに、なんとも奇妙な観念がまかり通っていること。市民モラルもまた表と裏の両面をもっていた。男たちは娘や妻を厳しく監視して、しかつめらしく純潔や貞淑を説くかたわら、こっそりと娼婦のもとへ通っている。
長篇2作目の『審判』の主人公ヨーゼフ・Kは31歳の銀行員である。なかなか有能で、支配人のポストにあり、将来の頭取候補と目されている。きちんと勤めを果たすかたわら、彼は週に一度、酒場の女のもとで泊っていく。
『審判』の未定稿の一つで、カフカはヨーゼフ・Kと親しい検事を語っている。検事の住居にはヘレーネという女がいて、いつもだらしなくベッドで横になり、安っぽい雑誌を読んでいる。Kがまだいるのに検事に挑みかかり、衣服をつけたままのセックスの際、2人はしきりに流し目をくれたりする。
いかなる説明もされていないが、ヘレーネが娼婦であることはあきらかだ。だから女に飽きたとたん、検事は「手のかかる獣」といったふうに容赦なく住居から追い出した。カフカがいかなる説明もつけなかったのは、説明するまでもなかったからだろう。カフカの友人また知人たちのそばに、しばしば一人のヘレーネがいたからである。 最後の長篇『城』の3章目は「フリーダ」と題されている。主人公Kは村の酒場の給仕女フリーダと知り合い、その夜にカウンターの下で抱き合った。床にはゴミがちらばり、こぼれたビールがたまっていた。そのなかを2人は抱き合ったままゴロゴロ転がった。その間、Kはずっと「自分がどこかに迷いこんでいく」ように感じていたという。
数日あとのベッドでの描写。2人は猛りたち、顔をしかめ、相手の胸に顔をうずめて、しきりに求め合う。ひしと抱き合い、さらに激しく抱きしめ合っても、求めることはやめない。
「犬が地面をかぎ廻るように、たがいに相手をかぎ合って、すべもなく裏切られ、最後の希望を託するように、舌を何度も相手の顔に這わせた」
2人が疲れはてて寝こんだあと、ベッドの上でどんな姿を呈していたものか、部屋をのぞいた女中たちのひとことで察しがつく。
「ごらんよ、なんてお行儀が悪いんだ」
一人が言って、布きれを1枚めぐんでやった。
いかなる恋人同士の抱擁でもないだろう。かぎりなく客と娼婦の営みに似ている。
カフカはいくつか「旅日記」にあたるものを書きのこしている。1911年の8月から9月にかけて、友人マックス・ブロートと共にしたミラノ経由のパリ旅行がとりわけくわしい。いずれ2人して共作の形で紀行記にまとめる計画があったせいだが、おかげではっきり見てとれる。大都市に着くと、2人はきっと売春街を訪れた。
ミラノの場合、カフカはことこまかく「エデンの園」の女たちを書きとめている。すわっているとき、また立ち上がったときの膝や腹のこと、品さだめをする客の眼差し、また女たちが、受けとった金を靴下に押しこむ手つき、あるいはステッキをついて巡回する夜警のこと。ベッドに入ったあと、カフカはその日、昼間に飲料水を口にしすぎたのを後悔したらしい。多少とも自分をコミカルに扱いたかったのか、わざわざ飲んだものを数えあげている。劇場で飲んだざくろシロップとオレンジエード、エコヌエレ通りの1杯、美術館喫茶店でのシャーベットとチェリー鉱泉水。
「重苦しい気持ちでベッドに入る。口がたえず乾いていた。やるせない目覚め」
パリの売春宿の合理さに目をみはったらしい。女たちが出迎えて、つぎつぎにポーズをとる。マダムに促される。すべてが「あっというまのこと」だったとカフカは書いている。記憶にのこっているのは、前の女の歯が欠けていたこと、やおらのびをし、恥部のあたりに手をおいて服をとりつくろったこと、ブロンドの髪、痩せぎみのからだ。そんな経過のしめくくり。
「わびしい、長い、無意味な帰り道」
ブロートとの約束から書いたのかもしれない。ひとり旅では書きとめられはしなかったが、ほかにも似たような訪問はあったにちがいない。あきらかにカフカもまた時代の子であった。フロイトが見つけたような性願望をもち、市民モラルの外で演じられた秘密の性をもっていた。ひそかな欲望と愉悦が作品のいたるところにその跡をとどめている。
(以上、150号)
プラハのヴァツラフ広場のすぐ西かたに「ルチェルナ館」と呼ばれる建物がある。東西2つの通りのパサージュでもあって誰でも入っていける。チェコ語のルチェルナは「ランタン、角燈」といった意味、それで東西それぞれの入口に鉄製の大きな角燈がつるしてあるが、もともとはパサージュ中央のガラスのドームから、眩しいほどの明かりが降ってくるところから名づけられたようだ。
1907年につくられ、はじめは映画館や小劇場、ギャラリー、カフェなどの入った文化ホールだった。のちに上階が建て増しされて、現在みるような建物になった。
ルチェルナ館のなかのキーノー・ルチェルナは、プラハで誕生した最初の映画館の一つであって、若いカフカが胸おどらせて訪れたところである。1907年当時、アール・ヌーボー様式がはやっていたので、正面入口からキップ売り場、ドアのつくりもすべてアール・ヌーボーで統1されている。映画館はいまも健在で、カフカと同じようにしてキップを買い、アール・ヌーボーのドアを押して暗闇のなかに入っていける。
2世紀のはじまりとともに、映画が民衆娯楽として頭角をあらわした。移動式の上映だったものが、映画専用の常設館に移っていった。カフカは新しい視覚メディアの誕生に立ち会った世代である。彼が日記をつけはじめるのは1910年以後であって、そこにしばしば「午後、映画」、「M・B(マックス・ブロート)と映画」といった記述がまじっている。当然、それ以前にも見ていたはずで、プラハ大学を卒業したばかりの安サラリーマンには、町歩きと映画館が数少ない慰めだった。
「映画に行く。泣いた。『ロッテ』。善人の牧師、小さな自転車……」
これだけでは何のことかわからないが、ベルリンの脚本家・映画ジャーナリストのH・ツィシュラーが『カフカ、映画へ行く』のなかで、丹念に古い映画を跡づけている。フィルムそのものは残されていないが、宣伝用のコピーや広告やプログラムによって、おおよそわかる。『ロッテ』は正確には『小さなロッテ』のタイトルで子役の活躍する映画だったようだ。不幸な運命にもくじけず、けなげに生きていく。涙と笑いの娯楽作。「もはや子供はいない!」がキャッチフレーズで、かなり当たったらしい。
映画はまだ「キネマトグラフ」の名で呼ばれ、何本かをセットにして上映した。『小さなロッテ』は悲劇『ドックの大事故』、コメディー『やっとひとり』との3本立て。喜劇、悲劇、喜悲劇を取り揃えていたことになる。全部見ると3時間あまりかかったが、カフカはそれぞれの映画にひとことずつコメントをつけているから、全部見たのだろう。暗闇の中でながながと過ごしたあと、外に出てくると、何やら空しく、わびしいものだが、カフカも同じような気持ちに襲われた。
「……自分が空虚で無意味に思えてならなかった。走り過ぎる電車のほうが、はるかに立派な意味をもっている」
1912年の夏、ベルリンの女性フェリーツェと知り合って文通がはじまり、カフカはそこでもしばしば、自分の見た映画を報告している。
「マックスと彼の妻、それに友人ヴェルチュと映画に行ったのですが、ロビーで『分身』の写真を何枚もみかけました……」
宣伝写真やポスターがずらりと貼ってあって、休憩のとき、客はロビーをぶらつきながらながめている。『分身』はベルリンの人気俳優A・バッサーマン主演なので、ベルリン娘の恋人に報告を思いついたのではあるまいか。バッサーマンがひとりで肘掛椅子にすわっているポスターが、なぜかカフカには気に入って、同行の友人を何度もそこへつれていき、あきれられたと述べている。
ツィシュラーによると、『分身』は1913年製作で、監督マックス・マック。バッサーマンの相手役がハンニ・ヴァイセ。そのころ映画はまだ戯曲と同じように幕で数えたので、「5幕、1766m」と長さが示されている。宣伝写真は、「次週当館上映・乞御期待」の意味であり、カフカはきっと見たにちがいない。
とはいえ当時は下っぱの小官吏であって、いつも金と暇があるわけではない。それに保険業務には調査や出張がつきものだ。そんなときは、むろん映画は見られない。 「ここのところはキネマトグラフにごぶさたですが、出し物はすべて知っています」 広告塔の壁にポスターが貼ってある。カフカはそれを人1倍熱心にながめていたようだ。フェリーツェへの手紙では、帰宅のとき乗っていた電車の窓から、「注意を集中させて」ポスターを追っていたと伝えている。
カフカの最初の小説『田舎の婚礼準備』は3つの未定稿として残されている。それぞれをA稿、B稿、C稿とすると、A稿はドイツ文字の筆記体、B・C稿はラテン文字の筆記体で清書されていた。カフカは1907年までは、ギムナージウムで習った旧来の字体を使っていたが、翌年から通常の書き方に移った。マックス・ブロートの証言からも、A稿は1906年から7年にかけて、B稿とC稿は1908/09年にできたと考えられる。
とすると、この小説が書かれたのはプラハにあいついで映画館が生まれ、新しい表現メディアが急速に若い人々を捉えていった時期にあたる。カフカは暇を見ては、せっせとキーノー・ルチェルナといったところに通い、そのあと夜っぴいて小説を書いていた。発表のあてはなかったが、3度までも書き改め、結局、どれも途中で放棄した。若いカフカがまだ小説技法に不慣れだったせいとされている。しかし、はたしてそうだろうか。未熟さだけだったのか。ほかにも理由はなかっただろうか。
『田舎の婚礼準備』のタイトルは、ブロートが遺稿を整理する際にあてたもので、カフカ自身はどの稿にもタイトルをつけていなかった。一人の青年が休暇を利用して田舎へ出かける。田舎には恋人とその家族が待っており、いずれ婚約から結婚に進みそうな雲行きだが、青年自身はさほど気乗りがしていない。なろうことなら、いっさいがご破算になればいいと思わないでもない――。
数年後のカフカその人とそっくりだが、小説は、青年が旅行用のトランクを下げて住居のある建物から出てきたところからはじまる。外に出てはじめて雨だと気がついた。しょぼついた雨。
「すぐ前の歩道を、いろんな人が思いおもいの足どりで歩いていた。ときおり脇へ抜け出て、車道を横断する人がいた。少女がぐったりした小犬を、両手を差し出してかかえていく。2人の紳士が話しこんでいた。一人は両の掌を上にして、まるで荷物を宙で支えてでもいるかのように、規則正しく上下に動かしている」
主人公が目にした風景であり、情景描写にちがいない。つづいて「帽子をリボンやバンドや花で飾り立てた女」がやってくる。つぎは細身のステッキを持った青年、つぎは3人づれ。
「通り過ぎていく人々の隙間ごしに、車道に整然と敷かれている敷石が見えた」
またつづいて首をのばした馬が大きな車輪の馬車を引っぱっていく。窓から見える乗客の顔。馬車がべつの馬車を追いこし、馬の首が下がる。何人かが建物の入口に駆けこむ。
「はやくも雨水が車道の端に筋を引いていた」
小説における情景描写以上に、映画のシーンを思わせないか、雨模様のなかをせわしなく人と馬車が往きかいしている。気乗りのしない旅立ち。それでもふっ切って行かなくてはならない。そんな気持を代弁するかのように、車道の雨水が筋を引いて走る。まるでカメラが一つ一つ追ったぐあいだ。
そのあとはじめて主人公ラバンが登場する。疲れぎみで唇に血の気がない。首に結んだネクタイのこと。それが幅広のネクタイで「ムーア風の模様」がついていることまでカフカは書いている。トランクは格子縞の布張り。映画ならほんの1瞬ですむところを、言葉がいちいち確かめていく。
ラバンが駅に向って歩き出す。広場の時計が4時41分を指している。向ってくる人々は傘を前に傾けていて、足元だけが見える。ブレーキの音がして馬車が急停車する。
「馬たちは高山のかもしかのような細い脚を大きく突っぱった」
主人公には、やはり気が進まない。田舎へ行くよりも、部屋のベッドで寝そべっていたいのだ。ラクダ色の毛布にくるまり、細目にあけた窓から流れこむ空気を吸っている。とたんに一つのイメージが主人公の頭をかすめた。
「ベッドのなかで大きな虫の姿になっているだろう。くわがた虫、あるいはこがね虫になっている」
初期の映画におなじみの技法である。心の思いをあらわすようなイメージが、やにわに画面に大映しになる。ここでは虫だった。
「大きな虫だ。そうだ、冬眠しているふりをするとしよう。細い脚を腹に押しつけている」
カフカが『変身』を書くのは、5年あまりのちのこと。そこでは主人公は空想ではなく、まさしく大きな虫になっていた。冬眠からさめたぐあいに無数の細い脚をワヤワヤと動かしていた。『変身』のあのとっ拍子もない書き出しは、実のところ映画技法が生かされた結果ではあるまいか。
3つの未定稿をこまかく検討すると、おもしろい結果が出ると思うが、それはべつの問題である。ツィシュラーの報告によると、カフカが長篇小説『失踪者』を書き出す少し前、ドイツの映画会社が新作の予告をしており、その中の一つは「失踪者」のタイトルだったそうだ。また小説『失踪者』は、ニューヨーク港に船が入っていくところからはじまるが、映画の宣伝プログラムには「ニューヨーク大活写」をうたったものもあるという。
そういった類似以上に表現の可能性に立ち入って、カフカが映画を活用したことはあきらかだ。『審判』『城』に共通しているが、薄明かり、あるいは薄暗がりのなかを黒い姿がしきりに往き来して、日常の脈絡を外れた世界が展開されるところにしても、初期キネマトグラフと瓜2つではなかろうか。
(以上、151号)
カフカには3人の妹がいた。弟が2人いたはずだが、ともに生後すぐに死んだ。そのため幼いころの写真には、いつも妹たちといっしょにいる。
カフカは3度婚約した。同じ人と2度、べつの人と一度。いずれの場合も結婚はしなかった。最初の婚約にいたる前にも、何人かと恋愛をした。3度目の婚約を解消してのちにも、ミレナという人妻に熱烈な手紙を書いている。死の前の数カ月、ともに暮らした女性がいた。41年の生涯にあって、少なからぬ女性的「経歴」というものではなかろうか。
その一方で死の2年前の日記に書いている。自分はとうとう「愛している」という言葉を知らずに終わったというのだ。
「期待のこもった静けさを体験しただけ。″愛している のひとことで、その静けさは破れただろうに。それをついにしなかった」
2度の婚約をした女性はフェリーツェ・バウアーといって、ベルリンに住んでいた。彼女とは5年にわたる。その間、たえずベルリンとプラハとのあいだを手紙が往き来した。カフカ作のどの小説よりも長大な『フェリーツェへの手紙』が残されている。
その書簡集を編み、解説をつけた文芸学者エーリヒ・ヘラーは、「宗教的な詩人による、もの憂い愛の歌」と名づけた。女性との現実的なよろこびに関しては、おそろしく不得手だったということ。カフカ自身、日記のなかに似たようなことを書いている。とりわけ性的なことについては、「たとえば相対性原理に対してと同様に、無知であり無関心だった」というのだ。
1920年、つまり死の4年前、カフカ37歳のときだが、ミレナへの手紙に自分の″初体験 を報告している。2歳すぎのときで、法律の国家試験を控え、バカバカしい事項を何が何でも覚えこまなくてはならないころのこと。部屋の向かいが洋服屋で、ドアのところにいつも店員の娘が立っていた。
「夏でした。とても暑かった。とりわけその日は暑く、とても我慢できないほどでした。味気ないローマ法の歴史を暗記しながら、窓のそばに立っていました。とどのつまり、手まねで娘に約束をとりつけました。夜の8時に迎えにいく。しかし、夜の8時になってみると、べつの男がいました……」
娘は男ともつれ合いながら、うしろからついておいでと合図した。モルダウ川の中洲の島にビヤホールがあって、娘と男とがビールを飲んでいるあいだ、カフカは隣のテーブルにいた。そのあと町にもどり、男が娘と別れを告げ、娘は家に走りこんだ。待っていると、やがて出てきて、2人して川向こうのホテルへ行った。
翌朝、橋を渡って帰る途中、自分は幸せだったと述べている。「ようやく肉体の責苦から解放されたし、それ以上に前夜のことのすべてが、それほど嫌悪をそそるものでも、汚ならしいことでもなかったからです」
このこと自体は何ほどでもない。むしろ37歳にもなった男が、新しくできた恋人に、わざわざ青春時のはじめての性的体験を告白していることが奇妙ではあるまいか。それも驚くべき正確さで、経過をことこまかに報告している。
カフカの手紙の背後に、たえず女性が透けて見える。22歳のとき、夏の休暇を過ごしたシレジアの小都市で知り合った人は、名前がつたわっていない。友人への手紙に述べている。
「彼女はちゃんとした妻で、こちらは少年同然だった」
イタリアのガルダ湖畔の町で知り合った女性のことは、日記にG・Wのイニシアルでしるされている、スイス人だった。たがいに秘密を誓い合って、別れたあと一度も会わず、手紙もとり交わさなかったが、「いとしさ、甘美さ」は、変わらずにあるというのだ。
1911年、当時、オーストリア領だったガリシア(現ウクライナ共和国)から東欧ユダヤ語であるイディッシュ語の劇団がプラハ公演にやってきた。カフカにとってみずからのユダヤ性を意識した最初の体験で、出し物が替わるごとに熱心に通った。
ユダヤ性の問題だけでなく、劇団の女優に惹かれたせいもあったようだ。一人はフローラ・クルーク、いま一人はマニーア・チシックといったが、舞台にいるときの2人を、まるで分解写真に収めたようにして書きとめている。
「唇もとと頬がふるえる。幼いときの飢えと、ベッドと、旅と、芝居のために削げ落ちたせいであり、生来は重いはずの口を訓練した結果であって……」
最後の公演には花束を持っていった。劇団がプラハを去る日、駅まで見送りに行って、走り出した列車を追いかけた。
1912年8月、ベルリンの女性フェリーツェ・バウアーを知った。彼女は口述録音器製作会社に勤めていた。当時の最新メディアであって、業務代理人として仕事のためプラハにやってきた。カフカより3歳年下だった。2年後に婚約。翌月、カフカの方から申し出て破棄。1917年、再度の婚約。やがてカフカは喀血し、それを理由に婚約を解消した。
カフカとフェリーツェの仲がこじれ、気づまりな状態がつづいたとき、フェリーツェの女友達が仲介を買って出た。グレーテ・ブロッホといった。カフカより5歳年少、ベルリンの会社に勤めていた。『フェリーツェへの手紙』には、グレーテ宛のものが、かなりの数に及んで収録されている。カフカはグレーテに対し、つねにつつしみをこめて書いた。ひそかな愛情もあったはずだ。フェリーツェと別れてのちもグレーテ・ブロッホに対して敬愛を持ちつづけた。
1919年の冬から翌春にかけて、カフカは結核の療養のため勤務先から長期休暇をとってシレジアの保養地で過ごした。そこでユーリエ・ヴォリツェクと知り合った。4歳年少。同じく療養のために滞在していた。父親はプラハ郊外の靴屋でユダヤ教の会堂の会堂守りを兼ねていた。
ユーリエを知ってすぐのころ、カフカは友人ブロートへの手紙に書いている。
「ごくふつうの、それでいて変わった娘だ。ユダヤ女ではなく、ユダヤ女でないこともなく、ドイツ女にあらずして、ドイツ女にあらずというのでもなし」
映画とオペレッタと喜劇が大好きで、プードルと飾りものに目がなく、威勢のいい下町言葉で、とめどなくまくしたてる。無邪気で、陽気だが、ときおり愁い顔を見せる・・。あきらかに知識人の友人には、まるで縁のない女であることを告げている。
カフカとユーリエは急速に親しみ、2人はプラハにもどってから婚約した。
しかし結婚には至らなかった。直接的には、第1次大戦終了直後のひどい時期であり、住むべき家が得られなかったせいだった。貧しい靴屋兼会堂守りの一家が、カフカの父親には不満でならず、陰に陽にその意志を伝えたことにもよる。婚約解消のあと、ユーリエ・ヴォリツェクはプラハの下町でモード店を開いた。
1920年、カフカはミレナ・イェセンスカを知った。彼女はチェコ人ジャーナリストで、翻訳家でもあった。カフカの短篇のチェコ語訳を申し出て、その相談で会ったのがきっかけだった。ミレナは銀行員エールンスト・ポラクの妻だった。出会ったとき、カフカ37歳、ミレナは24歳だった。
この場合もやはり急速に親しみが増し、はじめの3カ月で1冊の本ができるほどの手紙が送られた。2人は何度かウィーン、あるいはプラハで会った。カフカの死後のことだが、ミレナはブロートに宛てて書いている。
「彼と親しく知り合う前から、わたしはあの人の不安を知っていました。それがはっきりとわかったあと、わたしは闘う決心をしました。ウィーンで4日間をともに過ごしたとき、彼は不安をもっていなかったのです。わたしたちはそれを笑いとばしました。……不安がきざすと、彼はわたしの目を見つめていました」
半年後、手紙が絶えた。そのあとも、カフカは何度かミレナと会ったはずだが、くわしいことはわからない。
1923年の夏、カフカは療養のためバルト海沿いの保養地へ出かけた。そしてドーラ・ディマントを知った。ドーラの父親は正統派ユダヤ教団の信者で、ドーラは教団経営の保養所で働いていた。このとき、カフカ41歳。ドーラは21歳だった。
秋がきてカフカはベルリンに移った。勤めをやめ、念願の文筆生活に入った。ドーラが世話をした。第1次大戦の敗戦国ドイツを未曽有のインフレがみまった。結核が進行し、カフカはウィーン近傍のサナトリウムに入った。ドーラはつきそい、翌年6月も、カフカの死の床を見守った。死体が安置所に移されたときのドーラの言葉が残されている。
「この人は、こんなにもひとりぼっち。たったひとり。だのにわたしたちは、もう何もしてあげられない。なんてこと、ああ、なんてことが起きたのでしょう」
カフカの3人の妹は、いずれもアウシュヴィッツで殺された。カフカはとりわけいちばん末の妹ドーラと親しかった。ドーラはドイツ人と結婚した。カフカの死後のことだが、ナチス・ドイツの世となり、その法律では、アリア人を夫にもつユダヤ女性は、「ユダヤ人認定を免除される」ケースにあたったが、ドーラは夫の反対を押し切って離婚し、みずからユダヤ人認定を申請して、姉たちと死をともにした。
ユダヤ人フェリーツェは夫とともにアメリカに逃れた。その間もずっと、カフカからの膨大な手紙を保存しつづけた。
グレーテ・ブロッホはイタリアに逃れてのち逮捕され、その後の消息は不明。移送中に死んだか、あるいは強制収容所で死んだと思われる。
ユーリエ・ヴォリツェクはのちに精神を病んで、病院に入った。没年がわからない。「ナチス・ドイツによる人種整理」の犠牲になったと思われる。
ミレナ・イェセンスカはユダヤ人援護活動をつづけて逮捕され、アウシュヴィッツ強制収容所で死んだ。
ドーラ・ディマントはイギリスに逃れ、ロンドンで死去。
カフカの親しんだ女性たちに共通したものが見てとれる。いずれも男に従属せず、自立した、勇気ある女たちだった。カフカが書いている小説はほとんど知らなかったが、この人物のかかえている内面のこと、また何かを書きたがっていることはきちんと感じ取っていたのだろう。両手でローソクの火を囲うようにして、この男を庇護し、みずからは追われ、逃れ、あるいは死を選んだ。
(以上、152号)
長男フランツが生まれたとき、父ヘルマン・カフカは31歳、母のユーリエは27歳だった。若い夫婦は前年に結婚、同時に2人して「カフカ商会」をおこした。ステッキや傘、高級小間物を扱う。1880年代はプラハが大都市へと拡大をはじめていたころで、新しい富裕層が誕生していた。高級小間物の店は、きわめて適切な選択だった。
フランツ・カフカの祖父、つまり父親の父にあたる人はヤーコプ・カフカといった。プラハの南、100キロばかりのところの小さな村の住人で、フランツが生まれたころ、祖父はまだ存命だったが会うことはなかった。父からいろいろ聞かされたばかりである。
村はヴォセクといって「上の村」と「下の村」に分かれていた。上の村には地主や土地持ちのチェコ人が住んでいた。下の村はユダヤ人の集落だった。小説『城』に出てくる村と、ほぼひとしい構造である。下の村30番地にヤーコプ・カフカの家があった。藁ぶきで部屋は一間きり、そこに親子8人が住んでいた。
商売は畜殺業。牛を殺し、肉を荷車で売りあるく。ものごころつくと子供たちも手伝った。当時のユダヤ人の慣例では、子供は13歳で成人だった。世の中へ出ていく。先立ってわが家での修業時代があった。8歳で一丁前の労働力とみなされた。
子供はヘルマンのほか5人いた。齢の順でいうと、フィリップ、アンナ、ハインリヒ、ヘルマン、ユーリエ、ルートヴィヒ。とくに男子名に気をつけよう。ドイツの王侯貴族たちにお定りの名前である。貧しいユダヤ人ヤーコプ・カフカが何を念じて命名したかが見てとれる。
子供たちはいずれも13歳の成人をすぎると家を出た。使い走りや見習い、従弟奉公ののち商売につき、保険、不動産業、雑貨商などで成功した。フランツ・カフカが父方の特徴としてまとめたところは、つぎのとおり。
「強靭で、壮健で、弁舌が巧みで、我慢づよく、自己満足の傾きがある」
さらにこうも書いた。「生活力、事業欲、征服欲旺盛」、自分つまりフランツが、もっとも受け継ぐことの少なかったものだという。
母方の里はプラハから50キロばかり東の町で、住人の多くはチェコ人、そこにユダヤ人がゲットーをつくって住んでいた。ユーリエの父親はヤーコプ・レーヴィといったが、こちらのヤーコブ一族は当地のユダヤ人社会のなかでなかなかの名門だった。先祖には学識と英知で知られた教父がいた。学者、教師、また変人、奇人といわれる者もいた。
ユーリエは一人きりの娘で、あとは男の子ばかり。順にアルフレート、リヒャルト、ヨーゼフ、ルドルフ、ジークフリートといった。ヤーコプ・カフカと同じようにヤーコプ・レーヴィも子供たちに歴史的栄光にかかわるドイツ名をさずけたわけだ。同時代のボヘミア・ユダヤ人の処世法と生き方を示すものだろう。ユダヤ性と縁を切って、断乎としてドイツに同化する。ユダヤの慣習は捨てないまでも、ただ形どおりにとどめる。言葉はむろん、ドイツ語であって、何かのときに片ことのヘブライ語がまじる程度。
ヤーコプ・レーヴィは織物工場をもち、ビール醸造所を買い取って成功した。子供たちは夢を追うように異国へ赴き、長男アルフレートはスペインの鉄道会社の社主になった。3男ヨーゼフはベルギー領コンゴへ行って、コンゴ鉄道の建設にたずさわり、その後は中国へ渡った。ジークフリートは医者を開業。フランツ・カフカは父方よりも母方の叔父たちに親しんだ。幼いころジークフリート叔父の住む田舎町へ毎年のように出かけた。短篇「田舎医者」のモデルにしたと思われる。また書きさしの小説の一つは、こんな出だしをもっていた。
「わたしは当時、コンゴ中部の鉄道建設に従事していた……」
長男フランツ誕生の2年後に2男ゲオルクが生まれたが、1歳と少しで死去。ついで3男ハインリヒが生まれたが、半歳たらずで死亡。つづく4年間に3人の女の子が生まれた。順にガブリエレ、ヴァレリェ、オティリエ。それぞれ家庭ではエリ、ヴァリ、オトラの愛称でよばれた。
弟2人がはやく死んだので長男フランツは6歳になるまで、実質的には一人息子だった。父は終日、店にいた。母もおおかた店につめていた。乳母が通ってきて乳をやった。子守り娘が面倒をみた。一家の食事には台所女がいた。幼児フランツは強い父親と、夫に従順な母親のもとに孤独なひとり子として成長した。
この6年間に4度の引っ越しをした。商売が順調に発展していたしるしでもある。ゲットーからはじまった生活が、プラハの目抜き通りに住むまでになる。
6歳の誕生日とともに就学義務がはじまった。チェコ語の学校か、ドイツ語の学校かの選択を迫られ、父親は当然のようにドイツ語学校を選んだ。はじめは家族が送り迎えをしなくてはならない。カフカ家では、早朝から店にいる母親に代わり傭い女が手を引いていった。「小柄で、しわくちゃ、痩せっぽちで鼻の尖った台所女」だったと、カフカは述べている。
ユダヤ人の家庭には「バル・ミツヴァ」とよばれる大切な行事がある。息子が13歳になると、この名のもとに成人式を行う。暗記したモーゼの律法をシナゴーグ(ユダヤ会堂)で朗誦しなくてはならない。儀式のあと、親類一同と会食をとる。このとき13歳の成人は定められた言葉を唱えて両親への感謝を捧げる。
息子以上に父親にとって晴れがましい一日である。立派に子を育てたこと、そして儀式にかこつけて自分が築き上げた富と地位とを一族の者たちに示すことができる。
「ここにつつしんで、わが息子フランツのコンフィルマツィオーンのお知らせをいたします。式は1896年6月13日、午前9時半よりツィゴイナー通りのシナゴーグでとり行います。みなさまのご出席を心よりお待ち申しております」
ヘルマン・カフカの名前で招待状が送られた。これも作法どおり、差出人の下に小さく、「その妻」と添え書きがされていた。
伝統的な手続きを踏んでいるが、このヘルマン・カフカには、ヴォセクの村で自分の父が踏襲したような宗教性は失われていたと思われる。それはユダヤ教の儀式にもかかわらず、ヘブライ語の「バル・ミツヴァ」ではなく、「堅信礼」にあたるキリストの教会語「コンフィルマツィオーン」が使われていたことからも見てとれる。
法学部を終え、国家試験をくぐり抜けたあと、フランツ・カフカは就職に苦労した。父親はわが子がドクターを取得するまでは寛容だった。商人感覚よりして「採算性」を見込してのことと思われる。だがそのドクターが作家や詩人などと交わり、小説を書いているとなると話はべつである。カフカはのちに「父への手紙」のなかで、職業選択に悩んでいたとき、父からくり返し聞かされたお定まりの苦労ばなしを報告している。
「7歳のときには、もう荷車をひいて行商していた」
「冬用の衣服がなかったので、足はいつもヒビわれていた」
「成人前から自分の食いぶちはこの手で稼いだものだ」
何かにつけて、「優雅なドクター様」の皮肉がつく。このころに書いたカフカの小説「田舎の婚礼準備」に主人公の夢が語られている。ベッドで寝ている間に、自分は「1匹の大きな甲虫、くわがた虫、あるいはふきこがねになっている」はずだというのだ。それは冬眠中で、ぶよぶよした腹に細い脚をより合わせ、かぼそい声を出す。
「変身」のモチーフが、いち早く顔をのぞかせている。家庭におけるカフカの自画像にもあたるだろう。 1年の司法研修ののち、イタリア系の保険会社に8カ月あまり勤め、そののち半官半民の「労働者障害保険協会」に就職。父親のコネを通してのこと。初年度は臨時雇いの資格で、月給90クローネ。大学卒でドクターの称号持ちには考えられない安い俸給だった。それがまた「優雅なドクター様」にまつわる父親の皮肉のタネになった。
サラリーマン、フランツ・カフカ。当時の写真が残されている。髪を短く切り、きちんとまん中で2つに分けている。背広に白いワイシャツとネクタイ、冬はこれに厚手のオーバコートを着た。奥歯をかみしめるように口を結び、特徴のある大きな目をみひらいている。生涯ほとんど変わることのなかった生活者としての姿である。
3人の妹のうち、長女エリが1911年に結婚した。夫はカール・ヘルマンといった。同年、高級小間物商ヘルマン・カフカは娘婿とともにアスベスト工場を設立、共同経営者に息子フランツをつけた。薄給の息子に転進の道をひらく心づもりがあったようだが、当のフランツはひたすら逃げ腰で、一向に身が入らない。これがまた親子の諍いの原因になった。
31歳のカフカは一つの貸借対照表を書いている。父ヘルマンが店の帳場でつけていたような対照表であって、父親の場合は商品だったが、息子には結婚だった。その得失、プラスとマイナスを7項にわたり表にした。
長女につづき2女のヴァリが結婚を控えていた。フランツとベルリンの女性フェリーツェとの文通が深まりをみせはじめる。家族が期待の目で見つめていた。背後にはユダヤ社会の慣例と威嚇があった。父親がおりにつけ口にしたところである。キリスト者社会にあって有形無形の差別をはね返し、一族の共同体を守るためには、それがつねに拡大していかなくてはならない。生めよ、ふやせよ、地に満てよ、である。独身者は困った変わり者、それ以上に戒律の一つの説くとおり「妻のいない男は男ではない」だろう。
だが事態は家族の望んだほうには進まなかった。むしろ恐れたとおりになった。ベルリンの女性とは2度にわたり婚約しながら、どちらの場合も結婚にいたらなかった。2度目は結核の発病がかかわっていたが、それ以上に男性の方の意思が働いてのことだろう。結婚にまつわるフランツ・カフカの対照表は7項目のうちの6項目までがマイナスを指していた。
カフカは強い父親からたえず逃げた。虫のように自分の殻に閉じこもった。妹たちのうち、とりわけ末の妹のオトラと親しんだ。家族のなかの唯一の話し相手、相談相手だった。オトラには兄にはない決断力と実行力があった。オトラは父と衝突しはじめると、さっさとプラハ市中に貸し間を見つけて独立した。兄が小説執筆に悩んでいるのを知ると、自分の部屋をあけわたした。カフカの短篇の大半は、妹のところで居候中に生まれた。
オトラはまた女の自立をめざし、農業指導員の資格をとるため、ボヘミアの寒村の農家に住みこんだ。結核発病後、兄がそこにやってきて静養した。この妹は妹であるよりも兄の庇護者、母親代わりにひとしかった。そのオトラの自立に対し、父が反対してゆずらなかったとき、カフカは猛烈に抗議した。ただし、抗議は手紙のかたちをとり、最終的には母親のもとで預りとなって父の目には触れなかった。
カフカは35歳のとき、ユーリエ・ヴォリツェクと知り合い、婚約した。自分の家庭をもつ一歩手前にきていた。しかし、実現しなかった。1918年11月のことであって、第1次大戦終了のあと、チェコ共和国の誕生をはじめとして、世情が騒然としていた。プラハは難民でふくれあがり、たとえ独立しても住むべきところがなかった。
とともに陰に陽に父親の反対もあずかっていた。婚約者の父親はプラハの下町のしがない靴屋兼ユダヤ会堂の守り役だった。どちらの職だけでも食えなかったせいだろう。ヘルマン・カフカにとっては、まさにそこから上昇したはずの底辺にもどることになる。何度となく家族の小悲劇がくり返された。不機嫌な父と、オロオロする母と、黙りこむ息子。婚約は1年後、双方の合意のもとに解消された。
カフカが自分の家庭をもったのは死の前年である。バルト海の保養地で知り合った女性ドーラ・ディマントと2人して、1923年9月、ベルリンで部屋を借りた。おりしも敗戦国ドイツでは天文学的なインフレが進行中で、パン一つ買うのに1兆マルクが必要だった。そんななかで病んだ男と、2代はじめのユダヤ女性との新婚家庭がいとなまれた。その奇妙さは、カフカの小説ともひとしい奇妙さであったかもしれない。厳しい冬を迎え、2人は灯油を手に入れるのに苦労した。空瓶にローソクを立てて明かりに代えたこともある。その無理が結核の進行を速めたにちがいない。とともにカフカの生涯にあって、もっとも幸せな家庭生活だった。それは半年とつづかなかった。
(以上、153号)
1 カフカと機械 (145号)
2 カフカと文房具 (146号)
3 カフカと健康法 (147号)
4 カフカと金銭 (148号)
5 本づくり (149号)
6 カフカと性 (150号)
7 カフカと映画 (151号)
8 カフカと女性 (152号)
9 カフカの家族 (153号)
 「ぶっくれっと」一覧
「ぶっくれっと」一覧
 カフカ事典
カフカ事典